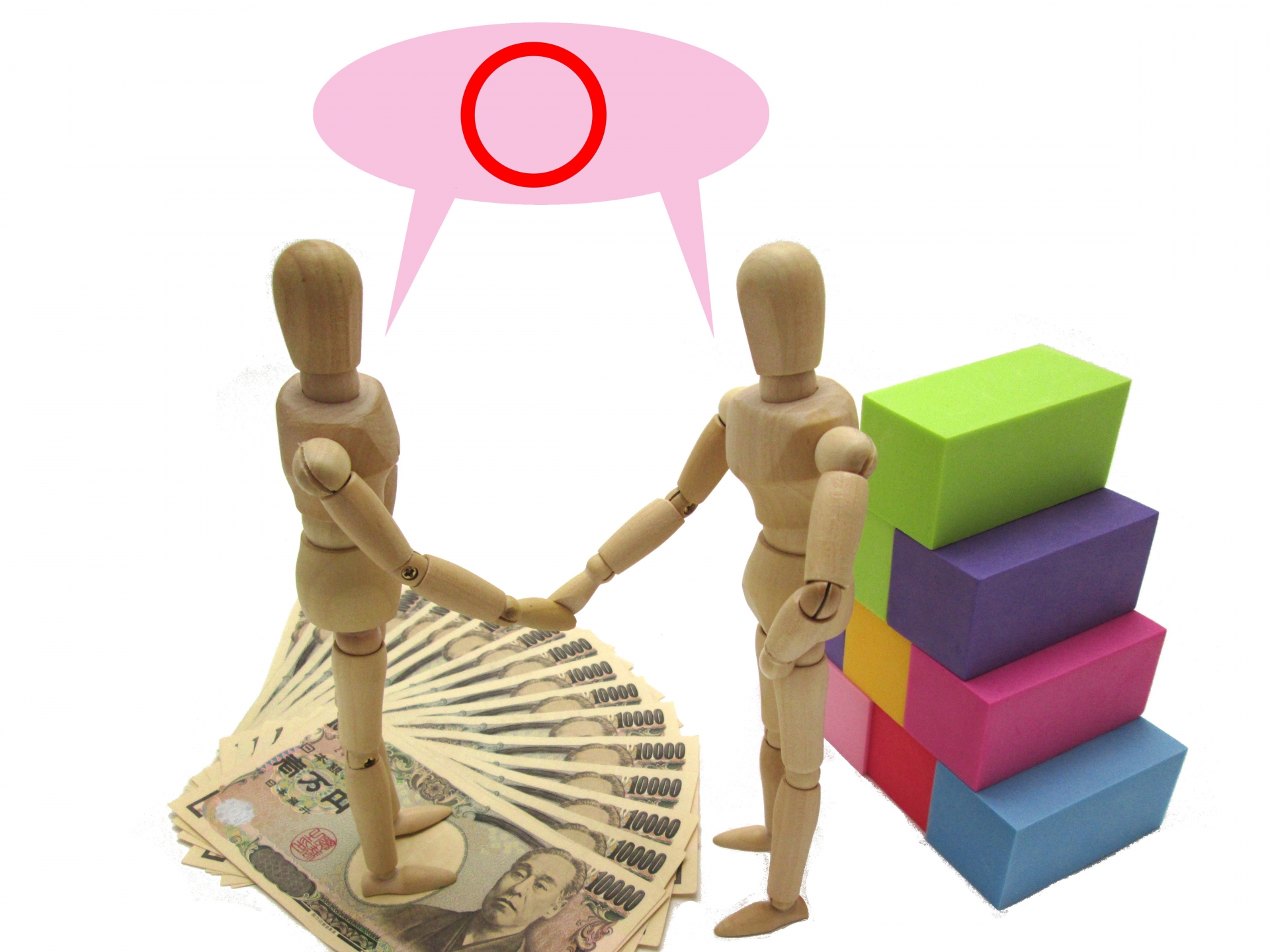個人事業主やフリーランスとして活動していると、スマートフォン(携帯電話)は、もはや欠かせない仕事道具のひとつです。
取引先との連絡、顧客対応、調べ物、スケジュール管理など、日々の業務の多くをスマホに頼っている方も多いでしょう。
しかし、「15万円のiPhoneを買ったとき、消耗品費にしていいのか?」「減価償却とは何か?」と迷う方は非常に多いです。
実は、スマホの端末代金は購入金額や申告方法(青色・白色)によって経理処理が全く異なります。
この記事では、個人事業主・フリーランス向けに、以下のポイントについて網羅的に解説します。
▼本記事のポイント
- スマホ代(通信費・端末代)を経費にする条件と家事按分
- 【重要】端末代の金額別ルール(10万・20万・30万の壁)
- 青色申告の特権「少額減価償却資産の特例」の必須要件(期限・除外規定あり)
- 減価償却の耐用年数(10年?4年?中古は?)
- 消費税(税込・税抜判定)とインボイス制度の基礎知識
PR
⚠️ 確定申告、まだ終わってない方へ
「何から手をつければいいか分からない…」という方は、安心プランの「丸投げ仕分け」を使うと、仕訳の着手ハードルが下がります。ただし、最終的な経費・プライベート判断は自分で確認が必要なので、まずは無料期間で動作確認してから判断するのが安心です。
3/16まで提出以外の機能は無料で試せます。
スマホ代(携帯電話)は経費にできる?
結論から言うと、事業で使用している分については、月々の利用料も端末代金も経費にできます。
ただし、個人事業主やフリーランスの場合、スマホを「完全に仕事専用」で使っているケースは少なく、多くの方が仕事とプライベートを兼用しているはずです。
そのため重要になるのが、家事按分(かじあんぶん)という考え方です。
経費として認められるための3つの条件
- 業務遂行上必要であること: 取引先との連絡、業務アプリの利用など。
- 区分が明確であること: 事業用と私用が混ざっている場合、その比率を合理的に説明できること。
- 記録があること: 領収書や請求明細書が保存されていること。
これらを満たしていれば、スマホ代のうち事業で使っている割合(按分率)のみを経費に計上できます。
毎月のインターネット代やスマホ代の請求額を見て、「これって少し高すぎるのではないか?」と不安に感じることはありませんか。 特に自宅で仕事をする個人事業主にとって、通信費は毎月必ず発生する固定費であり、同時に経費として計上できる重要な項[…]
経費処理とあわせて考えたい「スマホ代の最適化」
スマホ代を経費として処理することは大切ですが、実はそれ以上に重要なのが、毎月の料金そのものが適正かどうかという点です。
たとえ経費にできたとしても、月額料金が高ければ現金の流出(キャッシュアウト)は続き、手元の利益は減ってしまいます。
特にドコモユーザーの場合、「現在の料金プランが使い方に合っているか」「より安いプランの選択肢はないか」
これらを検討して見直すだけで、毎月数千円単位で固定費が下がるケースも珍しくありません。
通信費が高いと感じている場合は、ドコモ経済圏に特化した別サイトの「ドコモのeximoは高い?料金の仕組みと安くする解決策を徹底解説」などの記事もぜひ参考にしてください。
スマホ代は「経費にする」だけでなく、支出そのものを最適化する視点も非常に重要です。
【完全版】スマホ端末代(本体)の経理処理チャート
月々の通信費はシンプルですが、間違いやすいのが「スマホ端末(本体)を購入した時」の処理です。
スマホは金額によって「消耗品」になるか、「減価償却資産(数年かけて経費にする)」になるかが変わります。
ここでは、購入金額別の処理方法と、最も有利な選択肢を解説します。
金額別・処理方法の判定表(1台あたり)
| 購入金額 | 勘定科目 | 経費化のタイミング | 備考・対象者 |
|---|---|---|---|
| 10万円未満 | 消耗品費 | 全額、購入時に経費 | 青色・白色問わずOK |
| 10万円以上 30万円未満 |
消耗品費など | 全額、購入時に経費 | ※青色申告限定(特例) 期間:R8年3月31日まで等 |
| 10万円以上 20万円未満 |
一括償却資産 | 3年間で均等に経費化 | 白色もOK。 償却資産税がかからないメリットあり |
| 30万円以上 | 工具器具備品 | 耐用年数で減価償却 | 原則的な処理(通常10年などで計算) |
※金額の判定は、消費税の経理方式によって異なります(後述)。
① 10万円未満の場合(消耗品費)
最もシンプルなパターンです。
消耗品費として、全額を経費にできます。
- 対象: 全員(青色・白色)
- メリット: 手間がかからない。
② 10万円以上30万円未満の場合
ここが青色申告の最大のメリットの一つです。
通常、10万円以上の資産は数年かけて経費にしますが、青色申告者には「少額減価償却資産の特例」という強力なルールがあります。
これにより、1台30万円未満のスマホであれば、購入した年に全額を経費(即時償却)にできます。
最新のiPhone Proモデルなどは15万円~25万円ほどしますが、この特例を使えば一発で経費にでき、その年の税金を大きく抑えられます。
⚠️ 特例を利用するための必須要件(注意)
- 青色申告を行っていること。
- 従業員数が1,000人以下であること(一般的なフリーランスは該当します)。
- この特例を使う資産の合計が年間300万円以内であること。
- 適用期限:令和8年(2026年)3月31日までに取得したものであること(※税制改正により延長される場合もあります)。
- 確定申告時に「少額減価償却資産の取得価額の明細書」を添付すること(決算書等への記載)。
- 【除外規定】 レンタル事業など、「貸付け」の用に供した資産は対象外です(主要な事業として行っている場合を除く)。
③ 10万円以上20万円未満の場合(一括償却資産)
一括償却資産と言って、あえて一括で経費にせず、3年に分けて経費にするという方法も選べます。
これは青色・白色問わず利用可能です。
例えば、15万円のスマホを買った場合、5万円×3年間で経費にします。
- メリット: 償却資産税(固定資産税の一種)の対象外になること。
- 活用シーン: 今年は赤字だから経費を増やしたくない、または償却資産税の申告を避けたい場合。
④ 30万円以上の場合
30万円以上の超高性能スマホの場合、特例は使えません。
「工具器具備品」として資産計上し、法定耐用年数に応じて毎年少しずつ経費にします。
この記事では、工具器具備品の勘定科目で処理できる項目や、主な工具器具備品の耐用年数、償却方法や仕訳例をご説明しています。 工具器具備品とは 工具器具備品は、有形固定資産の勘定科目で、事務所で使用す[…]
スマホの耐用年数は10年?4年?
30万円以上のスマホや、白色申告で10万円以上のスマホを購入した場合、「何年で経費にするか(耐用年数)」が問題になります。
原則は「10年」(通信機器)
国税庁の耐用年数表において、スマホは「電話設備その他の通信機器」>「その他のもの」に該当すると解釈され、法定耐用年数は「10年」となります。
スマホの製品寿命からすると長く感じられますが、税務上の原則はここになります。
パソコン扱いで「4年」にできる?
実務上、「スマホは高性能な小型パソコンと同じだ」として、パソコンの耐用年数である「4年」を適用する考え方も一部にあります。
しかし、国税庁が「スマホ=4年」と明記しているわけではありません。
税務調査で否認されるリスク(主たる用途が通話・通信である等)を避けるため、安易な4年償却は推奨できません。
耐用年数の議論を回避するためにも、可能な限り「30万円未満の機種」を選んで青色申告の特例(即時償却)を使うのが、最も安全で節税効果の高い方法です。
中古スマホの耐用年数(最短2年)
仕事用に「中古」のスマホを購入した場合、新品よりも短い期間で償却できます。
法定耐用年数(10年)を過ぎた中古品の場合、「法定耐用年数 × 20%」の計算により、最短「2年」で償却可能です。
消費税とインボイスに関する注意点
経理処理において、消費税の取り扱いも非常に重要です。
10万円・30万円の判定は税込?税抜?
記事内の金額判定(10万円の壁など)は、あなたが採用している消費税の経理方式によって変わります。
- 免税事業者(消費税を納めていない人): 「税込金額」で判定します。
- 課税事業者(消費税を納めている人):
- 税込経理方式なら税込金額
- 税抜経理方式なら税抜金額
【例:本体98,000円(税込107,800円)のスマホ】
- 税抜経理の人 → 98,000円なので消耗品費(10万未満)
- 税込経理の人(免税事業者含む) → 107,800円なので固定資産(10万以上)
※免税事業者は税込で10万円を超えると消耗品費処理できないため注意が必要です。
クレカ明細はNG!インボイスの保存
2023年10月からインボイス制度が始まっています。
消費税の課税事業者が、スマホ代や端末代にかかった消費税を差し引く(仕入税額控除)ためには、原則として「適格請求書(インボイス)」の保存が必須です。
クレジットカードの「利用明細」だけでは、インボイスの記載要件(登録番号や税率ごとの消費税額など)を満たさないため、原則として仕入税額控除は認められません。
必ず、ドコモなどの通信キャリアや購入店(Apple Store、Amazon等)のマイページから、登録番号が記載された「領収書」や「請求書」をダウンロードして保存してください。
※なお、基準期間の課税売上高が1億円以下の事業者などについては、税込1万円未満の取引についてインボイス保存が不要となる「少額特例」がありますが、1万円を超えるスマホ端末の購入においては原則としてインボイスが必要です。
参考:国税庁 インボイス制度開始後において特にご留意いただきたい事項
スマホ代・端末代の仕訳・記帳ガイド
ここからは、具体的な仕訳例を紹介します。
ご自身の申告方法(青色・白色)に合わせて参考にしてください。
前提条件
- 月額利用料: 8,000円(事業割合50%)
- 端末購入代金: 150,000円(事業割合100%・青色申告の特例を使用)
青色申告の仕訳例(複式簿記)
青色申告(複式簿記)における、月々の支払いと端末購入(特例利用)の仕訳です。
① 月々のスマホ代(口座振替)
📘 仕訳伝票(通信費+家事按分)
| 日付 | 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 | 摘要(内容) |
|---|---|---|---|---|---|
| ◯月◯日 | 通信費 | 4,000 | 普通預金 | 8,000 | スマホ代(50%事業分) |
| 事業主貸 | 4,000 | スマホ代(50%私用分) |
② スマホ端末購入(15万円・青色申告特例)
15万円の端末を、青色申告の「少額減価償却資産の特例」を使って一括経費にする場合です。
📘 仕訳伝票(端末購入時)
| 日付 | 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 | 摘要(内容) |
|---|---|---|---|---|---|
| ◯月◯日 | 消耗品費 | 150,000 | 事業主借 | 150,000 | スマホ本体購入(少額特例) |
💡 仕訳のポイント
- 勘定科目:「消耗品費」または「工具器具備品」を使用します。
- 重要(適用要件):確定申告書の「少額減価償却資産の明細」への記載、または決算書への明記を忘れないでください。これが漏れると特例が否認されます。
- 貸方(右側):個人のクレジットカードや現金で買った場合は「事業主借」、事業用口座から振り込んだ場合は「普通預金」になります。
白色申告の記帳例(簡易帳簿)
白色申告(簡易帳簿)では、事業に使った分だけをシンプルに記録します。
📒 経費帳
| 日付 | 内容 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2025/◯/◯ | スマホ利用料 | 4,000円 | 事業利用50%(支払総額8,000円) |
| 2025/◯/◯ | スマホ本体代 | 50,000円 | 15万円の端末を一括償却(1/3ずつ経費化) |
💡 白色申告の注意点
白色申告には、30万円未満の特例(一括即時償却)がありません。
そのため、10万円以上のスマホを買った場合は、以下のいずれかで処理します。
- 一括償却資産(おすすめ):20万円未満なら、3年かけて均等に経費にする。
- 固定資産(原則):20万円以上なら、耐用年数(10年等)で少しずつ経費にする。
※白色申告の方が20万円以上の高額なスマホを買うと、経費になるペースが非常に遅くなる点に注意が必要です。
まとめ
スマホ代の経費計上や使用する勘定科目などの基本的な知識や経理処理などの注意点について解説しました。
▼重要ポイント
- 家事按分: 事業用と私用を分け、事業分だけを経費にする。
- 端末代金(~10万円): 「消耗品費」で即経費。
- 端末代金(~30万円): 青色申告なら「特例」を使って即経費にできる
- インボイス: 消費税の課税事業者は「適格請求書」の保存を忘れずに。
特に端末代金については、青色申告をしているかどうかで、その年の経費にできる金額や手間が大きく変わります。
高額なスマホへの買い替えを検討している場合は、この特例をうまく活用し、賢く節税につなげましょう。
🔧 当サイト独自の無料診断ツール(個人情報の登録不要)
- 一般家庭の平均と比較して「高い支出」を1分でチェック。勘定科目も表示!(個人事業主・フリーランス向け)
-
🧾 会計ソフト診断あなたの業種・規模に合う会計ソフトを最短で判定