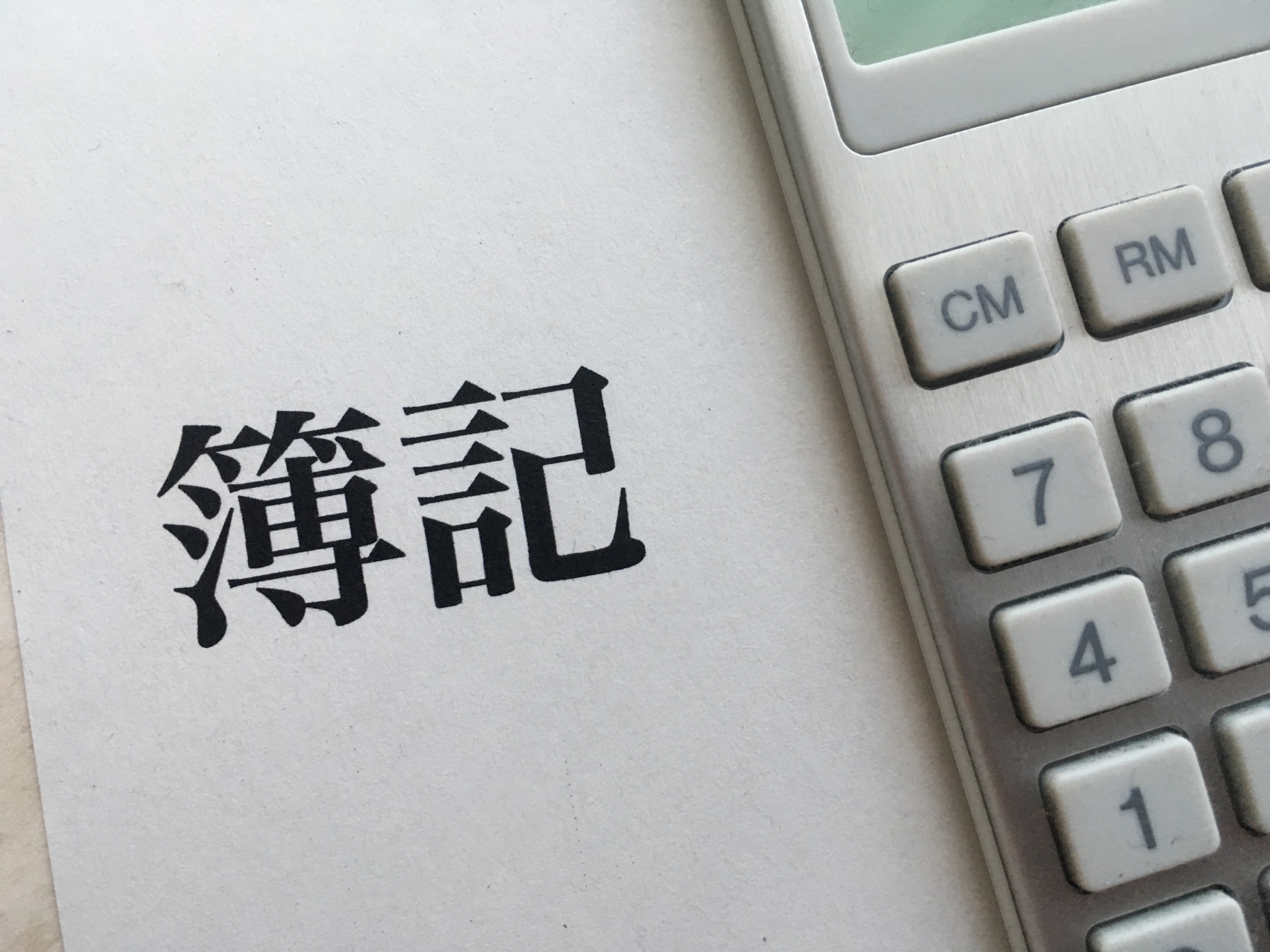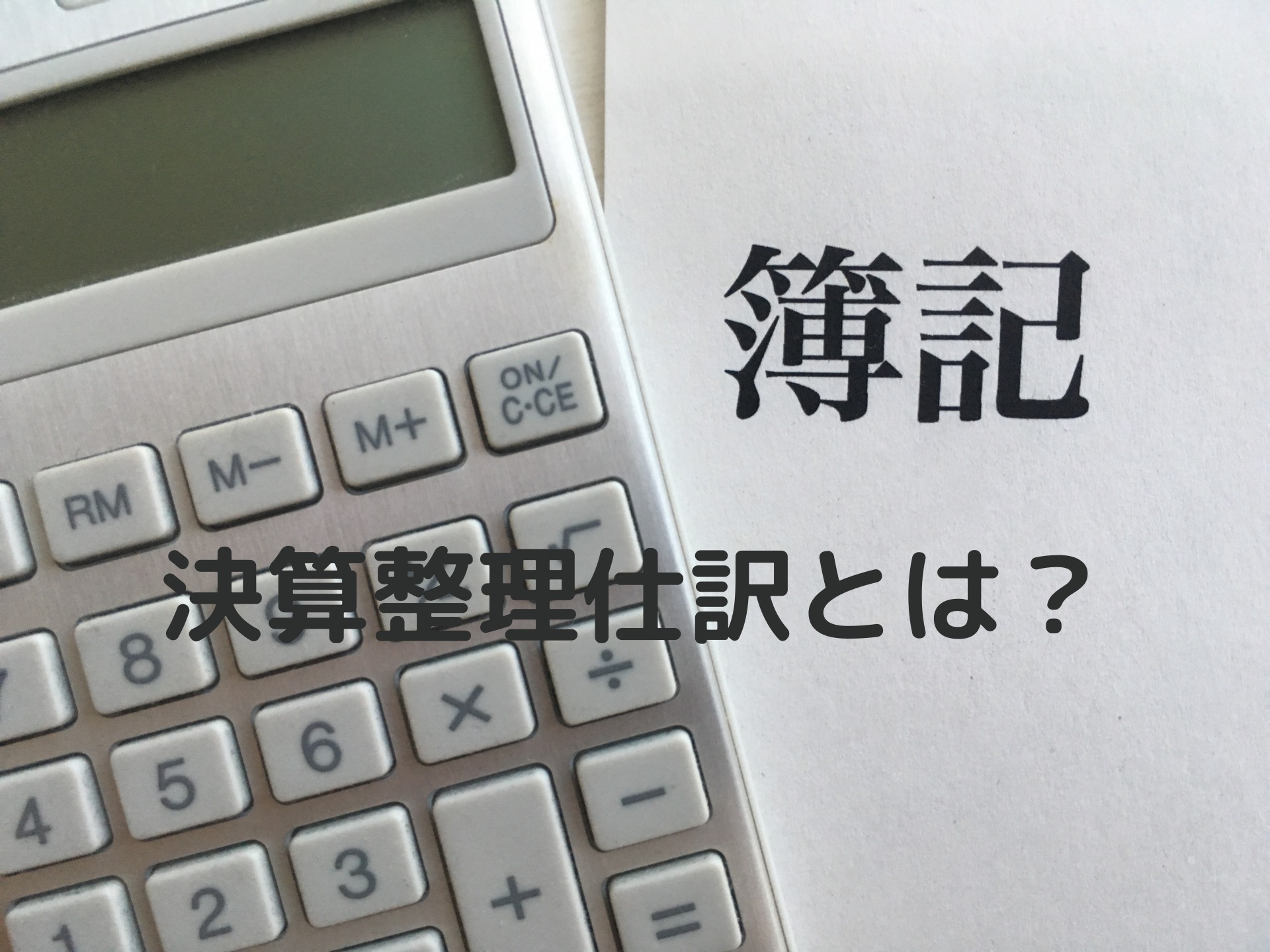簿記の学習を進めていると、商品売買の記録方法で必ず登場するのが三分法です。
しかし、専門用語が多く、分記法など他の方法との違いが分かりにくいため、つまずいてしまう方も少なくありません。
この記事では、簿記の初学者が抱える三分法とは何かという疑問に丁寧にお答えします。基本的な考え方から具体的な仕訳例、学習のポイントまでを網羅的に解説します。
- 三分法の基本的な意味と取引の流れ
- 分記法など他の記帳方法との明確な違い
- 具体的な仕訳例を通じた実践的な処理方法
- 簿記3級の試験で問われる重要なポイント
- 無料で効率的に簿記を学べる方法
ファイナンシャルプランナー2級・AFP、日商簿記2級、行政書士の資格保有者の個人事業主。詳細は運営者情報をご覧ください。
PR
⚠️ 確定申告、まだ終わってない方へ
「何から手をつければいいか分からない…」という方は、安心プランの「丸投げ仕分け」を使うと、仕訳の着手ハードルが下がります。ただし、最終的な経費・プライベート判断は自分で確認が必要なので、まずは無料期間で動作確認してから判断するのが安心です。
3/16まで提出以外の機能は無料で試せます。
簿記の基本!まず理解したい三分法とは?
このセクションでは、三分法の基本に焦点を当てて解説します。
多くの方が「わからない」と感じるポイントを整理し、仕訳例や例題を通じて、三分法がどのようなものかを具体的に明らかにしていきます。
まずは、この記帳方法の全体像を掴むことから始めましょう。
三分法をわかりやすく解説
三分法とは、商品売買に関する取引を「仕入」「売上」「繰越商品」という3つの勘定科目を使って記録する方法です。
この方法が多くの企業で採用されているのは、日々の記帳が非常にシンプルになるという大きな利点があるからです。
それぞれの勘定科目の役割は以下の通りです。
- 仕入(費用): 商品を仕入れた際に、その原価を記録します。期中はこの勘定科目に仕入れた商品の総額がどんどん蓄積されていきます。
- 売上(収益): 商品が売れた際に、その売価を記録します。どれだけの金額で商品を販売したかが、この勘定科目を見れば一目でわかります。
- 繰越商品(資産): 期末に残った在庫(売れ残り)の原価を記録します。これは来期に販売されるべき資産として扱われます。
このように、期中の取引では「仕入」と「売上」だけを使えばよく、商品の原価と売価を分けて管理する手間がかかりません。
そして、期末に一度だけ「繰越商品」を使って在庫の調整を行う、というのが三分法の大きな特徴です。
三分法の仕訳例
ここでは、三分法における具体的な仕訳の流れを「商品を仕入れたとき」「商品を販売したとき」「決算のとき」の3つの場面に分けて見ていきましょう。
商品を仕入れたとき
商品を現金12,000円で仕入れた場合の仕訳です。
| 借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 仕入 | 12,000 | 現金 | 12,000 |
商品を販売したとき
仕入れた商品を18,000円で販売し、代金を現金で受け取った場合の仕訳です。
| 借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金 | 18,000 | 売上 | 18,000 |
決算のとき
期末になり、期首の在庫が7,000円、期末の在庫が4,000円だった場合の決算整理仕訳です。
1. 期首在庫を仕入勘定へ振り替える仕訳
| 借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 仕入 | 7,000 | 繰越商品 | 7,000 |
2. 期末在庫を繰越商品勘定へ振り替える仕訳
| 借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 繰越商品 | 4,000 | 仕入 | 4,000 |
知っておきたい三分法の長所と短所
三分法は実務で広く使われている便利な方法ですが、長所と短所の両方を理解しておくことが大切です。
長所(メリット)
- 記帳が簡単で速い: 日々の取引では、仕入れた金額と販売した金額をそのまま記録するだけです。取引のたびに原価を計算する必要がないため、処理が非常にスピーディーです。
- 多くの取引に対応可能: 取り扱う商品の種類や数が多くても、全体の金額で管理するため、手間が増えにくいという利点があります。
短所(デメリット)
- 期中の利益が把握しにくい: 決算整理仕訳を行うまで、正確な売上原価が確定しません。そのため、日々の取引時点では、どれくらいの利益が出ているのかを帳簿上ですぐに確認することは困難です。
- 決算整理仕訳が必要: 期末には必ず棚卸(在庫確認)を行い、決算整理仕訳をする必要があります。この作業を忘れると、正しい利益計算ができません。
これらの特性から、三分法は日々の取引量が多い小売業や卸売業などで特に有効な記帳方法と考えられます。
三分法と他の記帳法を比較!
このセクションでは、三分法を他の記帳方法と比較することで、その特徴をさらに深く掘り下げていきます。
特に混同しやすい分記法との違いを明確にし、試験対策や無料で学べるツールについても触れていきます。
実務でなぜ三分法が選ばれるのか、その理由が見えてくるはずです。
三分法と分記法の違いを徹底比較
三分法としばしば比較されるのが「分記法」です。
分記法は、商品を資産として扱い、販売するたびに利益を計算する方法です。
両者の違いを理解することは、簿記の知識を深める上で欠かせません。
以下の表で、主な違いを比較してみましょう。
| 項目 | 三分法 | 分記法 |
|---|---|---|
| 主な勘定科目 | 仕入、売上、繰越商品 | 商品、商品売買益 |
| 利益の把握タイミング | 期末の決算時 | 商品を販売する都度 |
| 決算整理仕訳 | 必要 | 不要 |
| メリット | 日々の記帳が簡単 | リアルタイムで利益を把握できる |
| デメリット | 期中の利益がわかりにくい | 取引ごとの原価管理が煩雑 |
| 適した業種 | 小売業、卸売業など取引が多い業種 | 不動産業、宝石商など高価で取引が少ない業種 |
要するに、日々の処理の手軽さを取るか、利益把握のリアルタイム性を取るかで、どちらの方法が適しているかが変わってきます。
売上原価対立法と三分法の関係は?
簿記をさらに学ぶと「売上原価対立法」という言葉も出てきます。
これは分記法と考え方が似ており、商品を販売するたびに、その商品の原価を「売上原価」という費用勘定に振り替える方法です。
三分法が決算時にまとめて売上原価を計算するのに対し、売上原価対立法は販売の都度、売上と売上原価を対応させて記録します。
これにより、分記法と同様にリアルタイムでの利益管理が可能になります。
関係性を整理すると、三分法は「期末にまとめて原価計算」、分記法や売上原価対立法は「販売の都度、原価計算」を行う点で大きく異なります。
日商簿記検定では主に三分法が問われますが、他の方法との違いを理論的に理解しておくと、より深い知識が身につきます。
簿記3級で必須の三分法の知識
日商簿記3級の試験において、商品売買に関する問題はほぼ間違いなく三分法で出題されます。
そのため、三分法の理解は合格に不可欠です。
試験で特に重要となるのは、決算整理仕訳です。
期首の在庫を仕入勘定に加え、期末の在庫を仕入勘定から差し引く一連の処理を、正確かつ迅速に行えるかが問われます。
この仕訳ができないと、損益計算書の売上原価が正しく計算できず、大きな失点につながります。
対策としては、仕訳問題を繰り返し解くことが最も効果的です。
特に、決算整理の仕訳はパターンが決まっているので、何度も練習して身体で覚えるくらいの感覚で取り組むと良いでしょう。
私は、個人事業主として青色申告を始めるにあたり、簿記の基本的な知識の必要性を感じ独学で簿記の勉強を始め、日商簿記3級と日商簿記2級の資格を取得しました。 簿記については全く知識がなかったので、独学で学ぶのは[…]
簿記を無料で学ぶ方法
簿記の学習は、参考書や資格予備校を利用するのが一般的でしたが、現在は質の高い学習コンテンツを無料で利用できる時代です。
特に、簿記の学習が難しいと感じている方や、費用をかけずに学びたい方には「CPAラーニング」がおすすめです。
CPAラーニングは、公認会計士の資格スクールが提供する無料の学習プラットフォームです。
CPAラーニングの利用を検討しているものの、「完全無料」という言葉に、どこか怪しいと感じていませんか。 なぜ無料なのか、サービスの質は本当に信頼できるのか、といった疑問や不安を抱くのは自然なことです。多くの方が、お得な話の裏に[…]
その特徴は、単にテキストが読めるだけでなく、プロの講師による分かりやすい講義動画、ダウンロード可能なテキスト、そして豊富な問題集まで、学習に必要なものがすべて無料で提供されている点にあります。
スマホやPCがあれば、いつでもどこでも自分のペースで学習を進めることが可能です。
三分法のようなつまずきやすい論点も、動画講義で視覚的に学ぶことで、テキストだけでは得られない深い理解が得られます。
簿記の学習を始めたいけれど何から手をつけていいか分からない、という方は、まずはCPAラーニングに登録して、学習をスタートしてみてはいかがでしょうか。
メールアドレスを登録するだけで、無料で質の高い講義を視聴できるのでお勧めです。
\利用登録者数70万人以上!/
まとめ
この記事では、簿記における三分法とは何か、その基本的な考え方から具体的な仕訳例、そして分記法との違いまでを解説しました。
要点をまとめると、三分法は「仕入」「売上」「繰越商品」の3つの勘定科目を用いることで、日々の記帳を簡素化し、期末にまとめて正確な利益を計算する、非常に効率的な記帳方法です。
このシンプルさと実用性の高さから、多くの企業の実務で採用されています。
簿記の学習者がつまずきやすいのは、特に決算時に行う在庫の調整、つまり決算整理仕訳です。
もし独学で限界を感じたり、より効率的に学習を進めたい場合は、CPAラーニングのような無料の学習ツールを活用するのも一つの賢い選択です。
質の高い講義や問題集を通じて、三分法はもちろん、簿記全体の知識を体系的に身につけることができます。
三分法をマスターすることは、簿記の基礎を固め、実務や資格取得への大きな一歩となるはずです。
🔧 当サイト独自の無料診断ツール(個人情報の登録不要)
- 一般家庭の平均と比較して「高い支出」を1分でチェック。勘定科目も表示!(個人事業主・フリーランス向け)
-
🧾 会計ソフト診断あなたの業種・規模に合う会計ソフトを最短で判定