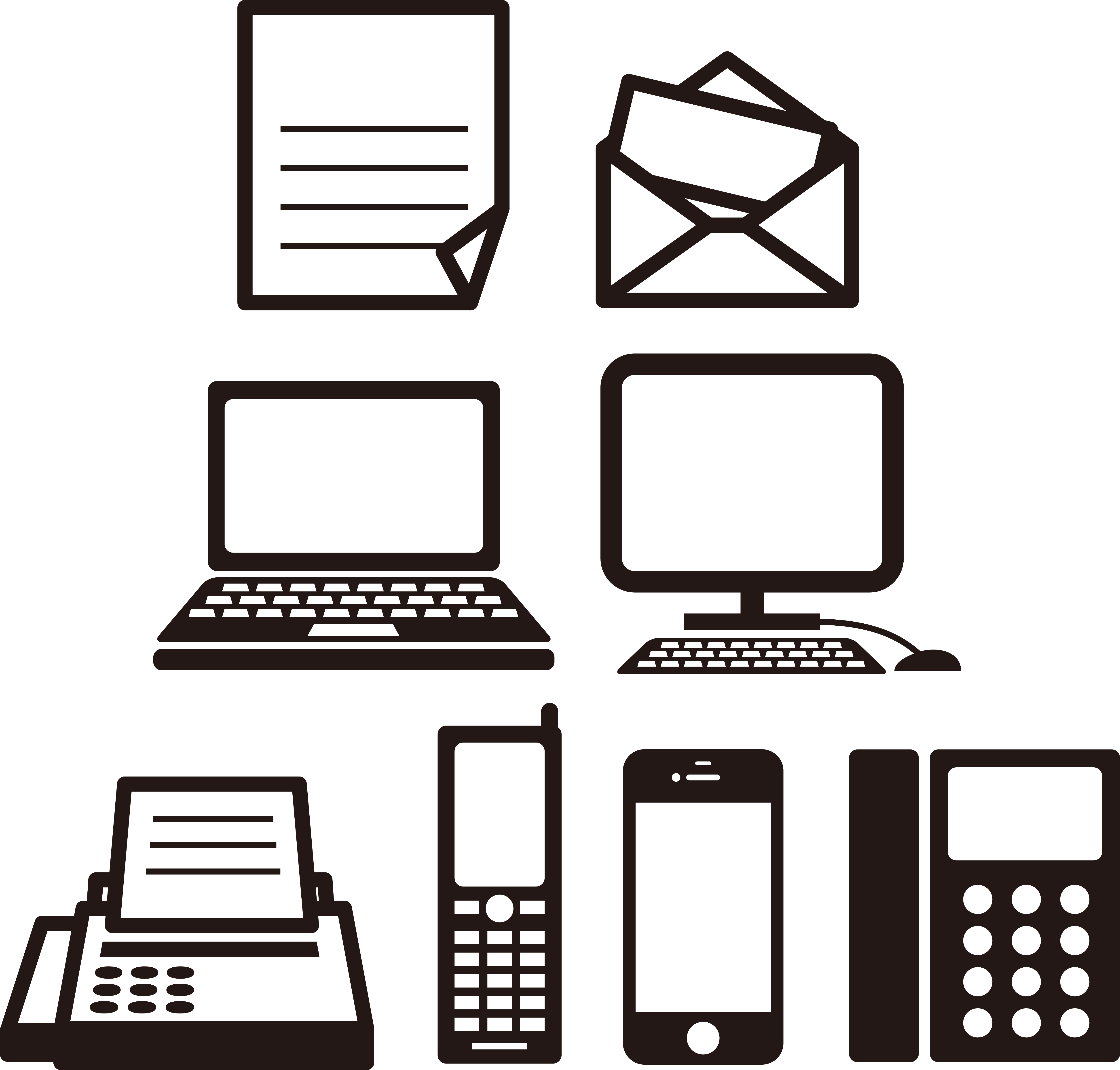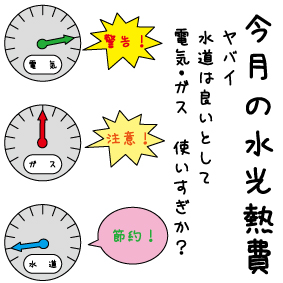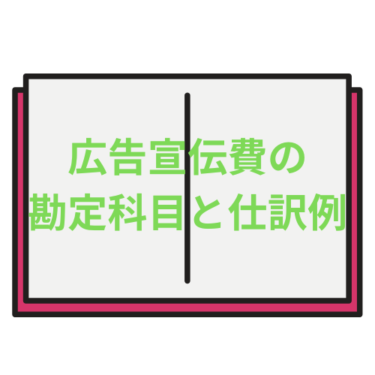個人事業主やフリーランスとして活動を始め、初めての確定申告に向けて準備を進めていると、多くの疑問に直面するかと思います。
特に、通信費とは具体的に何を指すのか、日々の業務で発生する携帯電話代やインターネット料金をどの勘定科目で処理すればよいのか、悩む方も少なくありません。
この記事では、通信費の勘定科目に関連して、以下の点を分かりやすく解説します。
本記事のポイント
- 通信費に該当する費用の具体例
- 個人事業主が行う「家事按分」の基本的な考え方
- 通信費の具体的な仕訳例
- 領収書がない場合の経費計上の対処法
PR
⚠️ 確定申告、まだ終わってない方へ
「何から手をつければいいか分からない…」という方は、タックスナップの「丸投げ仕分け」を使うと、仕訳作業が一気に進みます。私の場合は、未処理だった
667件の取引が約2秒
で仕訳されたので、正直かなりの衝撃でした。ただし、最終的な経費・プライベート判断は自分で確認が必要なので、まずは無料期間で動作確認してから継続利用を判断するのが安心です。
※3/16まで、提出以外の機能は無料で試せます。
通信費とは?勘定科目の基本を解説
ここでは、経理処理の第一歩として「通信費」とは何か、具体的にどのような費用が該当するのかを解説します。
インターネット代や携帯代など、日常業務で発生する費用がどの勘定科目に分類されるのか、基本的なルールを解説します。
通信費は経費になる?
事業を運営するために使用した通信費は、経費として計上できます。
例えば、取引先への電話、業務連絡用の携帯電話料金、事務所のインターネット回線利用料、仕事で送る郵便物の切手代などは、事業を行う上で不可欠な費用と考えられます。
これらの費用を売上から差し引くことで、課税対象となる所得金額を減らすことができます。
結果として、納めるべき所得税や住民税の節税につながります。
ただし、注意点があります。
個人事業主の場合、1台の携帯電話や自宅のインターネット回線を、仕事とプライベートの両方で使用しているケースが少なくありません。
この場合、プライベートで使用した分は経費として認められません。
そのため、後述する「家事按分」という方法で、業務に使用した分だけを正確に分けて計上する必要があります。
通信費に該当するもの
通信費は、名前の通り「通信」に関連する費用を処理するための勘定科目です。
ひと口に通信費といっても、その範囲は意外と広いです。
具体的には、以下のような費用が通信費として処理されます。
電話関係の費用
- 固定電話の基本料金、通話料
- 携帯電話(スマートフォン)の基本料金、通信料、通話料
- FAXの送信代
- 電報代(ただし、送る相手によって交際費や福利厚生費になる場合もあります)
郵便・宅配関係の費用
- 切手代
- 官製はがきの購入代
- 書類や郵便小包の郵送料
- 宅配便、メール便、バイク便の利用料
インターネット関係の費用
- インターネット回線の使用料
- プロバイダ料金
- レンタルサーバーの利用料
- 会計システムや顧客管理システムなどのクラウドサービス利用料
- 回線工事費(初期費用)
テレビ・放送関係の費用
- 事務所や店舗に設置したテレビのNHK受信料
- ケーブルテレビの利用料
- 店舗BGMなどに使う有線放送の利用料
このように、業務で使用する様々な連絡・通信手段が通信費に含まれます。
勘定科目の注意点
前述の通り、通信に関連する費用の多くは「通信費」という勘定科目で処理します。
しかし、経理処理では、通信費と間違えやすい他の勘定科目も存在します。
例えば、業務で使うパソコンや電話機本体を購入した場合、これは通信費ではありません。
また、宣伝目的でダイレクトメールを送った場合の送料も、通信費とは別の科目で処理するのが一般的です。
どの勘定科目で処理すべきか迷った際は、以下の表を参考にしてください。
これは、通信費と間違えやすい費用の一般的な分類例です。
| 費用の内容 | 推奨される勘定科目 | 補足 |
|---|---|---|
| 電話機、パソコン、コピー機の購入費用 | 消耗品費(または備品費) | 取得価額が10万円未満の場合は消耗品費で処理できます。 |
| コピー用紙、FAX用紙、私製はがき、封筒 | 消耗品費 | 切手代(通信費)とは区別されます。 |
| 宣伝目的のダイレクトメール送料 | 広告宣伝費 | 目的が宣伝・広告であるため、通信費とは区別します。 |
| 販売した商品の配送料 | 荷造運賃 | 書類の郵送(通信費)とは異なり、商品の発送にかかる費用です。 |
| 収入印紙代 | 租税公課 | 切手と似ていますが、税金の一種として扱われます。 |
| 取引先への祝電・電報代 | 交際費 | 従業員向けの場合は「福利厚生費」となることが多いです。 |
なお、NHK受信料や有線放送、レンタルサーバー代やクラウドサービス利用料などは、実務上「通信費」で処理されることが多いです。
しかし、事業の実態に応じて「支払手数料」「広告宣伝費」「雑費」などで処理するケースもあります。
どの勘定科目を選択しても、問題となることは稀ですが、一度決めたルールは継続して使用する「継続性の原則」を守ることが大切です。
通信費の仕訳を個人事業主向けに解説
基本を理解したところで、次は個人事業主の方が実際に行う経理処理に焦点を当てます。
プライベート利用分と分ける「家事按分」の具体的な方法や、簿記の仕訳例、確定申告での注意点など、実践的な内容を解説していきます。
家事按分とは
個人事業主が通信費を処理する上で最大のポイントは「家事按分」です。
家事按分とは、自宅兼事務所の家賃や光熱費、またはプライベートと共用している携帯電話代やインターネット代など、事業用と私用の両方にかかわる支出(家事関連費)を、合理的な基準で事業用と私用に分ける作業を指します。
通信費の場合、以下のような基準で按分比率を決めるのが一般的です。
- 使用時間で按分する
- 使用日数で按分する
重要なのは、税務調査などで尋ねられた際に「なぜその比率になるのか」を客観的に説明できることです。
例えば、スマートフォンの通話履歴や、業務日報に記録した作業時間などを根拠として残しておくと説得力が増します。
家事按分に関する詳細は、以下の記事を参考にしてください。
自宅で仕事をしていると、家賃や光熱費の一部を経費にできると聞くけれど、その具体的な方法がわからず不安に感じる方は少なくありません。 確定申告の時期が近づくにつれ、正しい仕訳や勘定科目の使い方を理解していないと、失敗や後悔につな[…]
通信費の経費計上の平均はいくら?
「通信費は経費にできるとして、平均はいくらくらいなのか」「経費はいくらまで認められるのか」と気になる方もいるかもしれません。
個人事業主の通信費の「平均額」については、業種や事業規模、働き方(在宅か事務所かなど)によって全く異なるため、明確な統計データはありません。
また、経費として計上できる金額に「いくらまで」という明確な上限はありません。
事業を行うために必要な支出であれば、その全額が経費として認められます。
ただし、売上に対して通信費の割合が不自然に高い場合、税務調査などでその必要性を詳しく問われる可能性はあります。
金額の平均を気にするよりも、前述の「家事按分」を適切に行うことが大切です。
仕訳の具体例
ここでは、通信費に関する具体的な仕訳例を見ていきましょう。
青色申告(複式簿記)と白色申告(単式簿記)の場合に分けて解説します。
青色申告(複式簿記)の仕訳例
複式簿記では、取引を借方(左側)と貸方(右側)に分けて記録します。
例1:仕事専用の携帯電話料金10,000円が、事業用の普通預金から引き落とされた。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 通信費 | 10,000円 | 普通預金 | 10,000円 | 携帯電話料金(X月分) |
例2:自宅兼事務所のインターネット料金10,000円が事業用口座から引き落とされた。家事按分の結果、事業割合は80%(8,000円)、プライベート割合は20%(2,000円)だった。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 通信費 | 8,000円 | 普通預金 | 10,000円 | インターネット料金(X月分) |
| 事業主貸 | 2,000円 | (プライベート分) |
「事業主貸」は、事業用の資金からプライベートな支出をした際に使う勘定科目です。
プライベート分の処理をする際に使用する、事業主貸や事業主借については、以下の記事を参考にしてください。
事業主貸と事業主借は、個人事業主特有の勘定科目です。 正しく会計処理をする上で、この2つの勘定科目の使い方を押さえておく必要があります。 この記事では、事業主貸と事業主借の勘定科目の仕訳例や決算時の相[…]
切手の仕訳(原則と例外)
切手は購入した時ではなく、使用した時に経費(通信費)として計上するのが原則です。
例1:840円分の切手を現金で購入した。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 貯蔵品 | 840円 | 現金 | 840円 | 切手購入 |
例2:購入した切手のうち84円分を使用した。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 通信費 | 84円 | 貯蔵品 | 84円 | 切手使用 |
例3:ただし、切手を継続的に購入し、すぐに使用する場合は、購入時に「通信費」として処理することも認められています。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 通信費 | 840円 | 現金 | 840円 | 切手購入 |
※この方法を採用した場合、期末(12月31日)時点で未使用の切手が残っていれば、その分を「貯蔵品」に振り替える仕訳が必要です。
白色申告(単式簿記)の仕訳
白色申告の単式簿記は、複式簿記よりも簡易的な記帳方法です。家計簿のようにお金の出入りを記録します。
例えば、上記(例2)のインターネット料金の場合、以下のように記帳します。
| 日付 | 勘定科目 | 摘要 | 金額(支出) |
|---|---|---|---|
| X月X日 | 通信費 | インターネット料金(X月分) ※事業割合80% | 8,000円 |
単式簿記では、このように家計簿をつける感覚で、事業で使った経費(8,000円)のみを日付順に記録します。
支払った総額(10,000円)やプライベート分(2,000円)は、この帳簿上には記載しません。
確定申告の方法
日々の帳簿付けが終わったら、年に一度の確定申告を行います。
通信費の確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間に経費として計上した「通信費」の合計額を、所定の書類に記入する作業です。
青色申告の場合:「青色申告決算書」の「損益計算書」にある「通信費」の欄に、1年間の合計金額を転記します。
白色申告の場合:「収支内訳書」の「経費」欄にある「通信費」の欄に、1年間の合計金額を転記します。
日々の仕訳データを会計ソフトに入力していれば、これらの合計額は自動で集計されます。
確定申告の手間を大幅に削減できるため、会計ソフトの導入は非常に有効な手段です。
個人事業主として事業を運営する上で、正確な会計処理やスムーズな税務申告は欠かせません。 しかし、日々の記帳や青色申告の準備は大変な作業となりがちです。 そこで、本記事では、初心者の方でも扱いやすい会計ソフトや無料で利用できる会計[…]
領収書なしの対処法
経費を計上する際は、原則として領収書(レシート)が必要です。
しかし、通信費の中には領収書が発行されにくいものもあります。
もし領収書がない場合でも、諦める必要はありません。
以下の書類が領収書の代わりとして認められることが一般的です。
- クレジットカードの利用明細
- 銀行口座の通帳(引き落としの記録)
- 通信会社などが発行する「請求書」や「ご利用料金のお知らせ」
大切なのは、「いつ(日付)」「どこに(支払先)」「いくら(金額)」「何のために(内容)」支払ったかを客観的に証明できることです。
これらの書類も手元にない場合は、「出金伝票」を作成するという方法もあります。
出金伝票は、領収書がもらえなかった場合に自分で作成する書類ですが、証拠能力としては上記のものより劣ります。
あくまで最終手段と考え、できるだけ請求書や利用明細を保存する習慣をつけましょう。
ただし、インボイス制度(適格請求書等保存方式)の開始後は、消費税の仕入税額控除を受けるために、原則として適格請求書(インボイス)の保存が求められます。
クレジットカード明細だけでは要件を満たさないケースが多いため、インボイスの要件を満たす請求書や領収書を別途保存するよう注意が必要です。
まとめ
この記事では、個人事業主やフリーランスの方に向けて、通信費の基本的な考え方から実践的な仕訳方法までを解説しました。
通信費とは、電話、郵便、インターネットなど、業務上の通信手段にかかる費用を処理するための勘定科目です。
特に個人事業主の方にとって最大のポイントは「家事按分」です。
プライベートと共用している支出は、必ず業務で使用した割合を合理的に算出し、事業用の部分だけを経費として計上しなくてはなりません。
会計ソフトを導入すれば、銀行口座やクレジットカードと連携して多くの作業を自動化でき、確定申告のプロセスも簡素化されます。
正しい知識を身につけ、便利なツールも活用しながら、本業に集中できる環境を整えていきましょう。
🔧 当サイト独自の無料診断ツール(個人情報の登録不要)
- 一般家庭の平均と比較して「高い支出」を1分でチェック。勘定科目も表示!(個人事業主・フリーランス向け)
-
🧾 会計ソフト診断あなたの業種・規模に合う会計ソフトを最短で判定