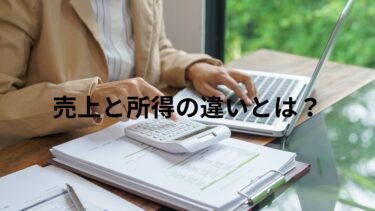個人事業主として確定申告の準備を進める中で、様々な税金の支払いに直面し、どれが経費になるのか分からず立ち止まってしまった経験はありませんか?
その経費になる・ならないを判断する鍵を握るのが「租税公課(そぜいこうか)」という勘定科目です。
この記事を読めば、あなたが支払っている税金や会費のうち、どれが経費として計上できる「租税公課」で、どれが経費にできないものなのか、区別できるようになります。
具体的な仕訳例から、インボイス制度との関連、よくある質問まで、分かりやすく解説します。
PR
⚠️ 確定申告、まだ終わってない方へ
「何から手をつければいいか分からない…」という方は、安心プランの「丸投げ仕分け」を使うと、仕訳の着手ハードルが下がります。ただし、最終的な経費・プライベート判断は自分で確認が必要なので、まずは無料期間で動作確認してから判断するのが安心です。
3/16まで提出以外の機能は無料で試せます。
租税公課とは?経費にできる税金・できない税金
「租税公課」とは、「租税(国や地方に納める税金)」と「公課(国や公共団体などから課される会費や罰金など)」を合わせた会計上の勘定科目です。
しかし、支払った税金のすべてが経費になるわけではありません。
個人事業主の場合、経費として認められるのは、原則として「事業を運営する上で直接的に必要となる税金や負担金」に限られます。
まずは結論として、経費に「できるもの」と「できないもの」を一覧で見てみましょう。
| 経費にできる租税公課 | 経費にできない主な税金・負担金 |
| ✅ 個人事業税 | ❌ 所得税 |
| ✅ 固定資産税(事業用部分) | ❌ 住民税 |
| ✅ 自動車税(事業用部分) | ❌ 国民健康保険料(税) |
| ✅ 不動産取得税(事業用資産) | ❌ 国民年金保険料 |
| ✅ 登録免許税 | ❌ 相続税・贈与税 |
| ✅ 印紙税 | ❌ 各種の加算税・延滞税・罰金 |
| ✅ 消費税(税込経理の場合) | |
| ✅ 商工会議所などの会費 |
※商工会議所等の会費は“対価性”しだいで課税/不課税が分かれる場合があるようです。判断が難しい場合は税務署や税理士などへ確認してください。
ここで最も重要なポイントは、所得税・住民税・国民健康保険などは経費にできない、ということです。
これらは事業で得た利益(所得)をもとに計算され、個人として負担すべきもの、と位置づけられているため、事業の経費とは明確に区別されます。
経費になる租税公課の詳しい解説
経費にできる租税公課には、具体的にどのようなものがあるか、もう少し詳しく見ていきましょう。
- 個人事業税:事業所得が290万円を超えた場合に課される税金です。8月と11月に納付し、その年の経費にできます。
- 固定資産税・自動車税:事業で使っている事務所、店舗、社用車などにかかる税金です。自宅兼事務所のようにプライベートと兼用している場合は、事業での使用割合に応じて「家事按分」し、事業分のみを経費にします。
- 不動産取得税・登録免許税:事業用の土地や建物を購入した際にかかる税金や、不動産登記にかかる税金です。
- 印紙税:5万円以上の領収書や契約書に貼り付ける収入印紙代です。
- 消費税:「税込経理方式」を採用している場合、確定申告で納付する消費税額を「租税公課」として経費に計上できます。(「税抜経理方式」の場合は経費になりません。)
- 商工会議所や同業者組合の会費:事業運営のために加入している団体の会費も、公課として経費にすることができます。
【状況別】租税公課の仕訳例
実際に租税公課を支払った際の仕訳(帳簿の付け方)を、状況別に見ていきましょう。
青色申告者の場合(複式簿記)
例:固定資産税 80,000円を普通預金から納付した。なお、この固定資産は100%事業用である。
(借方)租税公課 80,000円 /(貸方)普通預金 80,000円
例:自宅兼事務所の自動車税 45,000円を現金で支払った。(事業使用割合 50%)
- 事業経費分:45,000円 × 50% = 22,500円
- 個人負担分:45,000円 × 50% = 22,500円
この場合、個人負担分は「事業主貸」として処理します。
(借方)租税公課 22,500円 /(貸方)現金 45,000円 (借方)事業主貸 22,500円 /
事業主貸と事業主借は、個人事業主特有の勘定科目です。 正しく会計処理をする上で、この2つの勘定科目の使い方を押さえておく必要があります。 この記事では、事業主貸と事業主借の勘定科目の仕訳例や決算時の相[…]
白色申告者の場合(簡易帳簿)
白色申告の簡易帳簿では、複式簿記よりシンプルな形で記録します。家計簿のようなイメージで、以下の項目を記録しておけば問題ありません。
| 日付 | 勘定科目 | 取引内容 | 金額 |
| 8月31日 | 租税公課 | 個人事業税 第1期分 | 150,000円 |
| 5月30日 | 租税公課 | 固定資産税(事業分) | 40,000円 |
白色申告と青色申告を比べると、青色申告の方が税金が安くなったり、他にもオトクな特典があると見聞きしたことがあるかも知れません。 ただ、青色申告は会計処理が白色申告よりも大変みたいだし、面倒だから[…]
インボイス対応事業者の場合
インボイス制度は消費税の制度ですが、「租税公課」にはどう影響するのでしょうか。
原則として、ほとんどの税金(租税)の支払いは、インボイス制度に影響されません。
個人事業税や固定資産税などの税金は、サービスの対価ではないため消費税の課税対象外(不課税)です。そのため、消費税がかからず、インボイスのやり取りも発生しません。
ただし、公課の一部、例えば「商工会議所の会費」などがサービスの対価とみなされ、消費税の課税対象となる場合があります。その場合はインボイス制度のルールが適用されます。
例:商工会議所(適格請求書発行事業者)に会費11,000円(うち消費税1,000円)を支払った場合
適格請求書を保存することで、消費税1,000円分の仕入税額控除が可能です。
(借方)租税公課 10,000円 /(貸方)普通預金 11,000円 (借方)仮払消費税等 1,000円 /
見落としがち?消費税の「税区分」
会計ソフトで入力する際は「税区分」の選択が重要です。
- 個人事業税、固定資産税など、ほとんどの「租税」に関する税区分は「対象外」または「不課税」を選択します。これらは資産の譲渡やサービスの対価ではないため、消費税の課税対象外です。
- 商工会議所の会費など、一部の「公課」請求書に消費税の記載があれば「課税仕入10%」を選択します。対価性のある会費などが該当します。
参考情報として、国税庁のウェブサイトでも課税対象とならないものの例が示されています。
参考:国税庁タックスアンサー No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
租税公課に関連したよくある質問(Q&A)
Q. なぜ所得税や住民税は経費にならないのですか?
A. 所得税や住民税は、事業で得た「所得(儲け)」に対して個人として課される税金だからです。事業を行うためのコストとは見なされず、経費にはなりません。
Q. 延滞税や交通違反の罰金は経費にできますか?
A. いいえ、できません。延滞税、加算税、罰金、科料といったペナルティは、懲罰的な意味合いがあるため、経費として計上することは認められていません。
この点に関しては、以下の記事で詳しく取り上げていますので参考にしてください。
交通違反をしてしまった場合、反則金や罰金を支払う必要があります。 私は過去に駐車禁止違反や一時停止違反で反則金を支払った経験があります。 この記事では、仕事中に交通違反[…]
Q. 国民健康保険料や国民年金は経費になりますか?
A. いいえ、「経費」にはなりません。
これらは「租税公課」ではなく、確定申告の際に所得から差し引くことができる「社会保険料控除」の対象となります。
経費とは別の形で、税金の負担を軽くする効果があります。
まとめ
最後に、租税公課に関する重要な点をまとめます。
- 「租税公課」は、事業運営に直接必要な税金や公的な負担金を処理する勘定科目です。
- 個人事業税や固定資産税(事業分)、印紙税などは経費になります。
- 所得税、住民税、国民健康保険、年金、罰金などは経費になりません。
- 経費にできない税金・保険料も、所得控除の対象になるものがあります。
- ほとんどの税金は消費税の対象外(不課税)です。
どれが経費になるか・ならないかを正しく理解することが、適切な申告と節税への第一歩です。この一覧表を参考に、日々の経理処理に役立ててください。
【免責事項】
この記事は、2025年6月時点の情報に基づき、一般的な情報提供を目的として作成したものです。
税務に関するアドバイスを提供するものではありません。
個別具体的な税務判断については、必ず管轄の税務署や税理士などの専門家にご相談いただきますようお願い致します。
🔧 当サイト独自の無料診断ツール(個人情報の登録不要)
- 一般家庭の平均と比較して「高い支出」を1分でチェック。勘定科目も表示!(個人事業主・フリーランス向け)
-
🧾 会計ソフト診断あなたの業種・規模に合う会計ソフトを最短で判定