本記事では、年金収入の特性を踏まえた確定申告の基本条件や、医療費控除や生命保険料控除など各種節税対策の具体例、そしてよくある質問への解説を行っています。
年金生活者ならではの納税のポイントや、申告が不要なケースと必要なケースの見極め方を詳しく説明していますので、ぜひ参考にして下さい。
本記事のポイント
- 年金生活者が確定申告不要な条件と、申告が必要なケースを理解できる
- 年金以外の所得が確定申告に与える影響を把握できる
- 医療費控除、生命保険料控除などの節税対策の具体例を学べる
- 確定申告をしない場合のリスクと還付金受領のメリットが分かる
※本記事の情報は2025年2月時点のものです。税制改正等により内容が変更される可能性があるため、最新情報は国税庁の公式サイト等でご確認ください。国税庁の公式サイトへのリンクは、記事の最後に掲載しています。
PR
⚠️ 確定申告、まだ終わってない方へ
「何から手をつければいいか分からない…」という方は、安心プランの「丸投げ仕分け」を使うと、仕訳の着手ハードルが下がります。ただし、最終的な経費・プライベート判断は自分で確認が必要なので、まずは無料期間で動作確認してから判断するのが安心です。
3/16まで提出以外の機能は無料で試せます。
年金生活者:確定申告の基本条件

本題に入る前に重要なことなので、最初にご説明しておきたい点があります。
2025年の確定申告(2024年分)を行う場合に、注意が必要な点は、定額減税に関する記入です。
確定申告しなくても定額減税が受けられる方でも、医療費控除や生命保険料控除など、他の控除を受けるために確定申告をする場合は、定額減税の記入が必要です。
もし、確定申告を行った際に、定額減税に関する記入を忘れてしまうと、その分税金が多く取られてしまいます。
その点をぜひ注意して申告を行って、損をしないようにして下さい。
定額減税に関する注意点や書き方については、以下の記事で詳しくご説明していますので、この記事をご覧になった後からでも確認していただくことをお勧めします。
記事のタイトルが「個人事業主の場合の定額減税~」となっていますが、書き方は同じですので参考にして下さい。
参考:【2024年分】個人事業主の場合の定額減税|基本情報と確定申告書の書き方を分かりやすく解説
必要な場合と不要な場合
年金受給者の場合、通常は年金から所得税が天引き(源泉徴収)されているため、確定申告をしなくても問題ないケースが多いです。
しかしながら、以下の場合は確定申告が必要となります。
- 複数の公的年金の合計収入が年間400万円を超える場合
- 年金以外の所得(アルバイト、配当所得など)が年間20万円を超える場合
- 外国の公的年金を受給している場合
- 医療費控除、生命保険料控除、ふるさと納税などを利用して、払い過ぎた税金の還付を受けたい場合
一方、確定申告が不要とされる条件も存在します。
一般的には、以下の2つの条件が整えば、年金受給者は確定申告を省略することができます。
- 公的年金等の年間収入が400万円以下であること。
- 年金以外の所得が年間20万円以下であること。
ただし、上記の条件を満たしていても、控除を受ける目的で申告を行ったほうが有利になる場合があります。
例えば、医療費が多くかかった翌年に確定申告をすることで、源泉徴収されていた税金が還付される可能性があります。
このように、年金受給者が確定申告をするかどうかは、ご自身の年金収入だけでなく、他の収入や支出、そして利用できる各種控除の内容によって大きく異なります。
毎年送付される「公的年金等の源泉徴収票」や、給与明細、各種支出の証明書類をもとに、正確な収入状況を把握することが大切です。
公的年金等に含まれる収入の種類
公的年金等とは、国や地方公共団体が運営する公的な年金制度に基づいて支給される年金のことで、主に国民年金、厚生年金、共済年金などが該当します。
これらの年金は、老後の生活資金の基盤となる一方で、税制上の取り扱いが異なるため、確定申告の必要性にも大きく影響します。
ここでは、公的年金等の収入の種類について、課税対象となるものと非課税となるものに分け、さらに確定申告不要制度の適用条件とその考え方について具体的に解説いたします。
まず、公的年金等に含まれる収入は大きく分けて以下の種類があります。
- 老齢年金
主に国民年金、厚生年金、共済年金が含まれます。これらは、受給者が老後に受け取る年金で、原則として課税対象となります。 - 障害年金・遺族年金
これらは、被保険者が障害状態になった場合や、亡くなった場合に支給される年金ですが、法律により非課税とされています。
下記に、年金の種類に関する比較表を示します。
| 年金の種類 | 課税対象かどうか | 確定申告不要の条件の対象となるか |
|---|---|---|
| 老齢年金 | 課税対象 | 年間収入400万円以下かつ、他の所得が20万円以下の場合、確定申告は不要です。 |
| 障害年金・遺族年金 | 非課税 | もともと非課税なので、確定申告の必要はありません。 |
| 私的年金(個人年金) | 制度により異なる | 公的年金等には含まれません。 |
このように、年金受給者が確定申告を行うかどうかは、自分が受給している年金の種類や金額などによって判断されます。
年金以外の収入と確定申告の判断基準
年金受給者の場合、基本的には公的年金から源泉徴収されるため、単独の年金収入だけであれば確定申告を省略できるケースが大半です。
しかし、年金以外の収入があると、その所得額が確定申告の必要性を左右する重要なポイントとなります。
ここでは、年金以外の収入の種類や、実際に確定申告が必要になるかどうかの判断基準について説明いたします。
まず、年金以外の収入とは、以下のようなものを指します。
- 給与収入:パートやアルバイトで得た収入です。
- 配当収入:株式や投資信託などから得られる配当金など、金融収入が含まれます。
- 事業収入:フリーランスとして働く場合や個人で何らかの事業を行っている場合の収入です。
確定申告が必要になる基準は、年金以外の「所得」が年間20万円を超えるかどうかで判断されます。
年金以外の収入については、実際の「収入額」と「所得額」との違いを理解することが重要です。
ここでの「所得」とは、収入から給与所得控除や必要経費などの各種控除を差し引いた後の金額のことを指します。
給与所得の場合であれば、一定の控除があるため、実際に受け取った収入金額よりも低い所得額となります。
給与所得の場合、収入金額に応じて、給与所得控除額が決められています。
例えば、年金収入以外にアルバイト収入があり、その金額が年間70万円だったのであれば給与所得控除額は55万円です。
結果として、所得金額は15万円となるため、確定申告は不要となります。
ただし、年金収入以外の所得が20万円以上になっても、確定申告が不要になるケースがあります。
それは、以下の条件を満たしている場合です。
- 公的年金等の収入が60万円(65歳未満)もしくは110万円(65歳以上)以下
- 給与収入が1社のみで年末調整済み
このケースでは、公的年金等の所得が0円となるため、確定申告するものがない状態だからです。

ただし、このようなケースでも、例えば多くの医療費がかかった年の翌年に確定申告をすることで、給与収入から差し引かれている所得税の還付を受けられる可能性があります。
こうした場合は、確定申告をすることで損を避けることができるため、申告手続きをすることを検討してみて下さい。
まずは、毎年送付される公的年金等の源泉徴収票や給与明細、その他の収入に関する書類をもとに、控除後の所得額を確認し、全体の所得を合算して判断することが重要です。
年金生活者の確定申告:所得控除の具体例
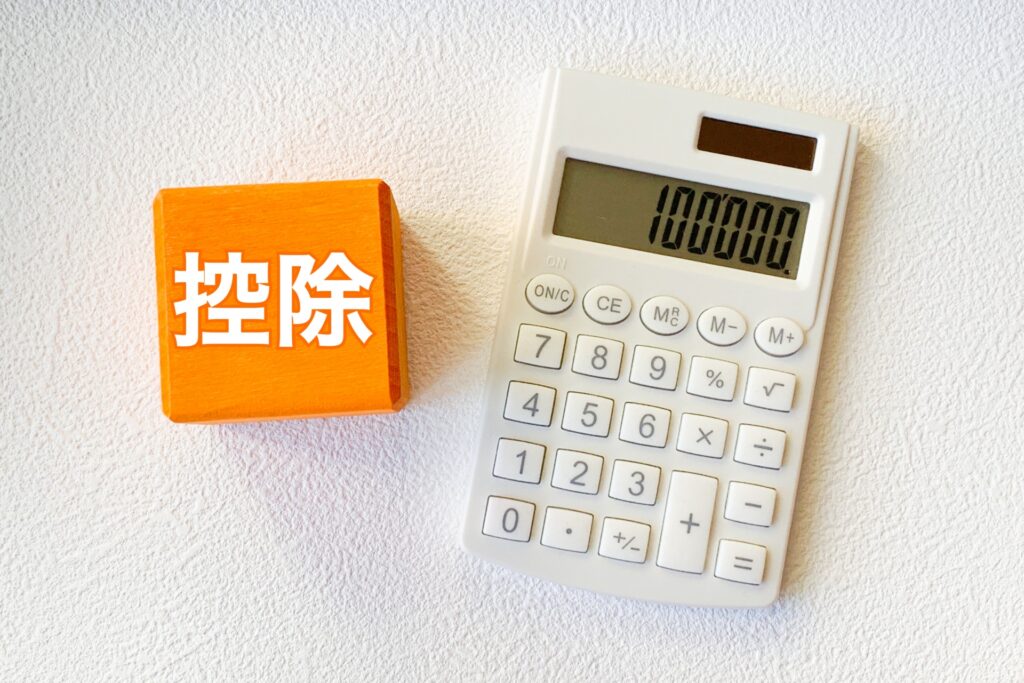
年金生活者の方が、確定申告をする場合、控除できる支出として、以下のような項目があります。
- 医療費控除
- 生命保険料控除
- 雑損控除
- 寄付金控除(ふるさと納税など)
この記事では、特に関係する方が多いと思われる、医療費控除と生命保険料控除について詳しく解説します。
医療費控除
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定の基準を超えた場合、その超過分を所得から差し引くことができる制度です。
年金受給者は、年齢とともに医療費の支出が増える傾向にあるため、確定申告を行うことで税金の負担を軽減できる可能性があります。
医療費控除の金額は、総所得金額によって次のように異なります。
- 200万円以上・・1年間の医療費の合計金額ー補てんされる金額(保険金など)ー10万円
- 200万円未満・・1年間の医療費の合計金額ー補てんされる金額(保険金など)ー総所得金額✕5%
控除を受けるためには、医療費の領収書や診療明細書などの証拠書類を整理し、確定申告書に正確に記入することが重要です。
以下に医療費控除のポイントを整理します。
- 支払った医療費が、総所得金額等の5%または10万円を超えた場合、その超過分が控除対象となる。
- 領収書や診療明細書などの証拠書類をしっかり保管する必要がある。
- 「生計を一にする」親族の医療費は合算してまとめて申告できる。
- 確定申告により、源泉徴収された仮納税と正確な税額との差額が清算され、納めすぎた税金が還付される可能性がある。
このように、医療費控除を活用することで、年金受給者の方も医療費負担に応じた節税効果が期待できるため、医療費が多い場合は必ず確認し、必要に応じて確定申告を行うことをおすすめします。
医療費控除の更に詳しい情報は、関連記事を参考にして下さい。
関連記事:確定申告で医療費控除の対象となる医療費や節税の方法について
生命保険料控除
生命保険料控除とは、契約している生命保険の保険料の一部を、所得から差し引くことができる制度です。
年金受給者は、長期にわたり生命保険料を支払っていることが多いため、この控除を活用することで、所得税や住民税の負担を軽減できるメリットがあります。
具体的には、支払った保険料の金額が控除対象となり、控除額には契約内容に応じた上限が設定されています。
生命保険料控除の控除額は、最大12万円となっています。
控除を受けるためには、保険会社から発行される「控除証明書」が必要です。
この証明書には、1年間に支払った保険料の合計金額が記載されており、確定申告書に添付することで控除の適用が認められます。
保険の種類や契約内容によって控除額は異なりますので、最新の国税庁の情報を確認することが重要です。
以下に生命保険料控除のポイントを整理します。
- 保険会社から発行される控除証明書が必要。
- 控除額は契約内容や支払い方法により異なり、一定の上限がある。
- 正確に申告することで、実際に納めた税金と正確な納税額の差額が調整され、場合によっては還付金が発生する。
このように、生命保険料控除を適切に利用することで、年金受給者の方も納税額を効果的に軽減することが可能です。
控除対象となる保険料については、毎年送付される証明書をもとに、正確な情報を確認し、確定申告書に漏れなく記入することを心がけましょう。
関連記事:【確定申告】生命保険料控除の書き方と計算方法を分かりやすく解説
これらの支出以外にも、災害や盗難による被害にあった場合に控除できる「雑損控除」や、ふるさと納税などの寄付を行った場合に利用することができる「寄付金控除」などについても、基本的な内容を記事にしていますので、参考にして下さい。
ふるさと納税については、「ワンストップ特例制度」を利用していれば確定申告は不要です。
年金受給者の確定申告でよくある質問

夫婦で年金生活をしている場合、確定申告はどうなりますか?
夫婦で年金生活を送っている場合、確定申告の必要性は各自の収入状況によって判断されます。
基本的には、年金受給者は年間の公的年金等収入が一定の基準内であれば、確定申告が不要となる制度があります。
しかし、夫婦のうちどちらか一方が年金以外の収入を得ており、所得金額が基準を超える場合は、確定申告を行う必要があります。
たとえば、妻が年金のみで基準内であっても、夫がアルバイトやその他の副収入を得ている場合は、その方のみ確定申告を行う必要が生じることがあります。
さらに、医療費控除や生命保険料控除、ふるさと納税など、各種控除を受けることで本来納めた税金の還付が受けられる可能性もありますので、各自の状況を正確に把握して申告することが大切です。
年金以外に収入がない場合は確定申告の必要はない?
年金受給者の場合、年金からはすでに所得税が天引きされていますが、実際の納税額は1年間の所得全体を正確に計算することで決まります。
確定申告を行わないと、以下のような不都合や損失が生じる可能性があります。
まず、源泉徴収は仮納税として天引きされているだけで、年間の正確な所得に基づいて税額を再計算する必要があります。
確定申告を行うことで、源泉徴収された税金と実際の税額との差額が清算され還付されるチャンスがあります。
しかし、申告をしない場合、払いすぎた税金がそのままとなり、結果として損をしてしまいます。
具体的には、以下の点が問題となります。
- 還付金の受領機会の喪失
仮に天引きされた税金が、実際の税額より多かった場合、その差額が還付されるはずですが、申告しなければその還付金を受け取ることができません。 - 控除の適用漏れ
医療費、保険料、ふるさと納税などの控除対象となる支出があっても、確定申告を行わなければ、これらの控除が適用されず、本来軽減できるはずの税負担がそのまま残ります。 - 未申告による将来の不利益
過去数年分の未申告がある場合、最大5年分まで遡って還付請求が可能です。しかし、申告を行わないとその権利を失い、結果として払いすぎた税金の還付の機会を逃してしまいます。
このように、年金以外に収入がなくても、確定申告を行うことで源泉徴収されたお金が還付される可能性もあるため、場合によっては申告を怠ることは損失につながります。
毎年送付される「公的年金等の源泉徴収票」や、その他の収入に関する書類をもとに、自分の収入状況と控除対象となる支出を正確に把握し、必要に応じて税務署などで相談しながら、確定申告を行うことを検討しましょう。
まとめ
本記事では、年金生活者の方向けに確定申告の基本条件や注意点、節税対策などについて解説しました。
基本的に、以下の2つのケースに該当すれば確定申告は不要です。
- 公的年金等の年間収入が400万円以下であること。
- 年金以外の所得が年間20万円以下であること。
ただし、確定申告が不要であっても、医療費控除や生命保険料控除など各種控除を活用することで、払い過ぎた税金の還付を受けられる可能性があります。
その場合は、確定申告をすることを検討してみて下さい。
税制は改正される可能性があるため、最新の情報を確認することが重要です。
以下の、国税庁のサイトも参考にして下さい。
🔧 当サイト独自の無料診断ツール(個人情報の登録不要)
- 一般家庭の平均と比較して「高い支出」を1分でチェック。勘定科目も表示!(個人事業主・フリーランス向け)
-
🧾 会計ソフト診断あなたの業種・規模に合う会計ソフトを最短で判定







