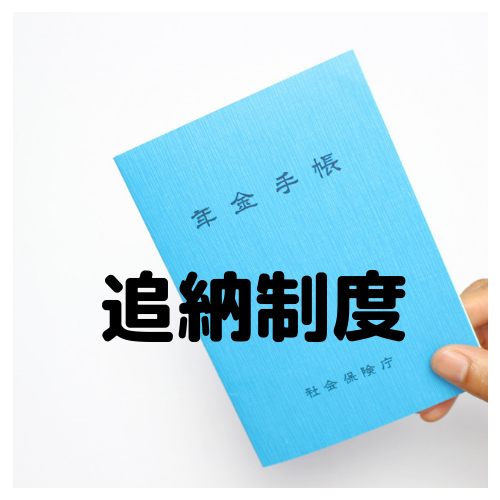「老後の資金、国民年金だけだと少し不安…」「何か手軽に始められる対策はないだろうか」と感じていませんか。
自営業やフリーランスとして働く方々にとって、将来の年金額は切実な問題です。
そんな中で、付加年金という言葉を耳にしたことがあるかもしれません。
この記事では、付加年金とはどのような制度なのか、その仕組みからメリット、注意点まで、あなたの疑問に一つひとつ丁寧にお答えします。
この記事を読むことで、以下の点が明確になります。
- 付加年金の基本的な仕組みや対象者
- 国民年金基金との違いやメリット・デメリット
- 具体的な申し込み方法や注意点
- 確定申告など税金に関する知識
PR
⚠️ 確定申告、まだ終わってない方へ
確定申告がまだ終わっていない方は、まず仕訳を片付けると一気に気持ちがラクになります。特にタックスナップの「丸投げ仕分け」は、迷いがちな仕訳作業を一気に進められる機能です。
私の場合は、 667件の取引が約2秒 で仕訳されました。ただし端末や通信状況などにより、処理の時間は異なる可能性があります。
3/16までは提出・印刷以外を無料で試せます。無料のうちに使ってみて、合うかどうかを確認してみてください。
※仕訳後に、勘定科目や金額は念のため確認しておくと安心です。
※3/16まで、提出以外の機能は無料で試せます。
クーポンは、初回登録時に入力しておくとスムーズです。合わなければ無料期間中に解約できます。
▶ 無料でタックスナップを試してみる(3/16まで) ※「丸投げ仕分け」の詳細や体験談を確認できる記事はこちら付加年金とはどんな制度?
このセクションでは、付加年金の基本的な仕組みから、どのような方が加入できるのか、将来受け取れる年金額はいくらになるのかを解説します。
また、よく比較される国民年金基金との違いや、加入する上でのメリット・デメリットにも触れ、制度の全体像をわかりやすく解き明かしていきます。
老後資金の準備を考え始めた方が、まず知っておくべき基礎知識を提供します。
付加年金とはわかりやすく解説
付加年金とは、毎月の国民年金保険料に加えて、月額400円の「付加保険料」を納めることで、将来受け取る老齢基礎年金を増額できる公的な年金制度です。
この制度は、国民年金の第1号被保険者や任意加入被保険者の方々が、比較的少額の負担で将来の備えを手厚くするために設けられています。
厚生年金のような上乗せ部分がない自営業者やフリーランスの方にとって、老後の所得を確保するための一つの選択肢となります。
具体的に将来受け取れる付加年金額は「200円×付加保険料を納付した月数」という非常にシンプルな計算式で決まります。
つまり、長く納めれば納めるほど、将来受け取る年金額が増えていく仕組みです。
このように、付加年金は手軽に始められ、かつ成果が分かりやすい年金の上乗せ制度と考えることができます。
付加年金の対象者
付加年金に加入できるのは、国民年金の「第1号被保険者」と「任意加入被保険者」に限られています。
具体的には、以下のような方が対象となります。
- 自営業者
- フリーランス
- 農業者
- 学生(20歳以上)
- 無職の方
一方で、会社員や公務員などの「第2号被保険者」や、その方に扶養されている配偶者である「第3号被保険者」は、付加年金に加入することはできません。
これは、第2号被保険者には国民年金に上乗せされる厚生年金制度が既にあるためです。
したがって、一般的なサラリーマンの方は対象外となります。
また、国民年金保険料の納付を免除または猶予されている期間は、付加保険料を納めることができない点にも注意が必要です。
(参考:日本年金機構「付加保険料の納付」)
年金はいくら増えるか
付加年金に加入した場合に将来受け取れる年金額は、前述の通り「200円×付加保険料を納付した月数」で計算されます。
この金額が、65歳から生涯にわたって老齢基礎年金に上乗せされます。
では、加入期間によって年金額がいくら増えるのか、具体的な例を見てみましょう。
| 付加保険料の納付期間 | 納付月数 | 支払う保険料の総額 | 増える年金額(年額) |
|---|---|---|---|
| 10年間 | 120ヶ月 | 48,000円 | 24,000円 |
| 20年間 | 240ヶ月 | 96,000円 | 48,000円 |
| 30年間 | 360ヶ月 | 144,000円 | 72,000円 |
| 40年間(20歳~60歳) | 480ヶ月 | 192,000円 | 96,000円 |
この表からわかるように、支払った付加保険料の総額は、年金の受給を2年間続ければ元が取れる計算になります。
例えば、20年間保険料を納めた場合、総額96,000円を支払いますが、年額48,000円が上乗せされるため、65歳から67歳になるまでの2年間で元が取れることになります。
これは非常に効率の良い制度と言えます。
付加年金と国民年金基金どっちを選ぶ?違いを徹底比較
自営業者やフリーランス(国民年金第1号被保険者)の方が、将来の老齢基礎年金に上乗せして備えるための公的な制度として、「付加年金」と「国民年金基金」という2つの選択肢があります。
「どちらの制度がよりお得なのだろう?」「自分にはどちらが合っているのだろう?」と迷う方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、どちらが「得」か、あるいは「良い」かは、個人のライフプラン、現在の収入状況、そして将来の資産形成に対する考え方によって異なります。
両者は年金を増やすという目的は同じですが、その仕組みや特徴は大きく異なります。
まずは、両者の主な違いを一覧で比較してみましょう。
| 項目 | 付加年金 | 国民年金基金 |
|---|---|---|
| 掛金 | 月額400円(定額) | 加入口数やプランにより変動(上限 月額68,000円) |
| 給付額 | 200円×納付月数(確定) | 加入時の年齢・性別・プランにより変動(確定給付) |
| 柔軟性 | いつでも脱退・再加入が可能 | 原則として自己都合での脱退は不可 |
| 税制優遇 | 掛金全額が社会保険料控除の対象 | 掛金全額が社会保険料控除の対象 |
| 併用関係 | 国民年金基金との併用は不可 | 付加年金との併用は不可(基金の1口目が付加年金を代行) |
この比較表からわかるように、両制度の最も大きな違いは「掛金の自由度」と「制度の柔軟性」にあります。
これを踏まえて、どのような方にどちらの制度が向いているのか、さらに詳しく見ていきましょう。
付加年金が向いている方
付加年金は、月々わずか400円という定額の掛金で始められる手軽さが最大の魅力です。
将来受け取る年金額も「200円×納付月数」とシンプルで、受給開始から2年で元が取れるという高いコストパフォーマンスを誇ります。
また、いつでも自分の意思で脱退したり、再加入したりできるため、収入がまだ不安定な方や、まずはお試しで年金の上乗せを始めてみたいという方に最適です。
<こんな方におすすめ>
- まずは少額から手軽に年金の上乗せを始めたい方
- 収入が不安定で、将来的に掛金の支払いを止める可能性がある方
- 手続きの簡単さや制度のシンプルさを重視する方
- iDeCo(個人型確定拠出年金)をメインに考えつつ、少額の上乗せをしたい方
国民年金基金が向いている方
国民年金基金は、自分で給付の型や口数を選ぶことで、掛金を月額68,000円を上限に自由に設定できます。
これにより、将来受け取る年金額を計画的に大きく増やすことが可能です。
また、支払った掛金は付加年金と同様に全額が社会保険料控除の対象となるため、掛金が多いほど高い節税効果が期待できます。
ただし、一度加入すると自己都合で任意に脱退することは原則としてできません。
長期的な視点で、計画的に老後資金を準備したいという強い意志のある方に適した制度です。
<こんな方におすすめ>
- より手厚い老後の保障を計画的に準備したい方
- 毎月、一定額を確実に積み立てられる安定した収入がある方
- 所得控除の上限額を大きく活用して、節税効果を高めたい方
注意点
ここまで両制度を比較してきましたが、付加年金と国民年金基金は同時に加入することができないという点を必ず覚えておいてください。
これは、国民年金基金の1口目の給付に、付加年金に相当する部分が含まれているためです。
したがって、国民年金基金に加入した場合は、付加保険料を納める必要がなくなり、自動的に付加年金からは脱退扱いとなります。
ご自身の現在の状況と将来の目標を照らし合わせ、どちらか一方を選択する必要があります。
自営業者(個人事業主やフリーランス)の方が、将来貰える年金を増やす方法の一つとして「国民年金基金」を活用することができます。 この記事では、国民年金基金の基本的な内容についてご説明しています。 […]
デメリットや注意点はある?
非常にメリットの大きい付加年金ですが、加入を検討する際にはいくつかのデメリットや注意点を理解しておく必要があります。
物価変動に対応していない付加年金は将来受け取る金額が固定されている「定額年金」です。
このため、将来インフレが進み物価が上昇した場合、年金の実質的な価値が目減りしてしまう可能性があります。
早期に亡くなった場合は元本割れの可能性
年金の受給開始から2年で支払った保険料の元が取れますが、例えば65歳から受給を開始して67歳になる前に亡くなってしまうと、支払った保険料総額よりも受け取る年金額が下回ることになります。
また、年金を受け取る前に亡くなった場合、原則として支払った保険料は返金されません。
ただし、付加保険料を36ヶ月以上納めていた方が死亡一時金の支給対象となる場合には、一律8,500円が死亡一時金に加算される制度があります。
繰り上げ・繰り下げ受給に連動する
老齢基礎年金を65歳より前に受け取る「繰り上げ受給」を選択すると、付加年金も同様に減額されます。
逆に、66歳以降に受け取る「繰り下げ受給」を選択すれば、付加年金も同様に増額されます。
減額・増額率は生涯変わらないため、慎重な判断が求められます。
iDeCoの掛金上限額に影響がある
付加年金とiDeCoは併用可能です。
ただし、国民年金の第1号被保険者がiDeCoに拠出できる上限額は、国民年金基金の掛金または付加保険料と合算して月額68,000円です。
付加保険料(月額400円)を納める場合、iDeCoで拠出できる理論上の上限は67,600円になりますが、iDeCoの掛金は1,000円単位で設定するため、実務的な上限額は月額67,000円となる点に注意が必要です。
これらの点を踏まえた上で、ご自身の状況に合っているかどうかを総合的に判断することが大切です。
手続きや税金まで解説!付加年金とはどう付き合う?
このセクションでは、付加年金の具体的な申し込み方法から、加入後の状況変化(就職など)への対応、そして確定申告といった税金面での扱いまで、実践的な知識を詳しく解説します。
制度を実際に利用する上で必要な手続きや注意点がわかります。
申し込み方法とさかのぼっての加入
付加年金の申し込み手続きは、お住まいの市区町村の役所窓口(国民年金担当課)または、お近くの年金事務所で行います。
手続きに必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)
- (代理人が手続きする場合)委任状
窓口で「国民年金付加保険料納付申出書」を提出することで、手続きは完了します。
マイナンバーカードがあれば、マイナポータルからの電子申請も可能です。
ここで大切な注意点があります。
付加保険料の納付は、申し込みをした日の属する月から開始となり、過去にさかのぼって加入することはできません。
将来の年金を少しでも増やしたいと考えるなら、思い立った時に早めに手続きをすることが鍵となります。
厚生年金加入者は付加年金に加入できる?
厚生年金に加入している会社員や公務員の方が、付加年金に加入する方法は基本的にありません。
その理由は、付加年金制度が、国民年金の第1号被保険者のための上乗せ制度として設計されているからです。
厚生年金加入者は国民年金の第2号被保険者にあたり、既に給与から天引きされる厚生年金保険料の中に、国民年金保険料相当分と、上乗せ部分である厚生年金分が含まれています。
このため、制度の対象外となっており、加入手続きを行うことはできません。
もし、会社を退職して自営業者(第1号被保険者)になった場合には、その時点から付加年金に加入することが可能になります。
就職した場合
自営業やフリーランスとして付加年金に加入していた方が、その後、会社などに就職して厚生年金の被保険者(第2号被保険者)になった場合、付加年金の加入資格は自動的に失われます。
就職先の会社で行う厚生年金の加入手続きによって被保険者の種別が切り替わるため、基本的にはご自身で付加年金の「辞退(脱退)」の手続きを行う必要はありません。
ただし、資格変更の情報が反映され、口座振替が停止するまでには時間差が生じる可能性があります。
意図しない引き落としを防ぐためにも、特に口座振替で納付していた方は、念のため「国民年金付加保険料納付辞退申出書」を提出しておくことをお勧めします。
確定申告での勘定科目と仕訳
個人事業主やフリーランスの方にとって、支払った付加保険料の税務上の扱いは気になるところです。
支払った付加保険料(年間最大4,800円)は、国民年金保険料と同じく、全額が「社会保険料控除」の対象となります。
これにより、所得税や住民税の負担を軽減する効果が期待できます。
(参考:国税庁「No.1130 社会保険料控除」)
勘定科目と仕訳例
会計処理を行う際の勘定科目は「事業主貸」として処理します。
付加保険料は、事業運営に必要な経費ではなく、あくまで個人として支払う社会保険料です。
このため、「租税公課」などの経費の科目では処理できない点に注意が必要です。
(例)普通預金から付加保険料400円が引き落とされた場合
事業主貸 400円 /普通預金 400円
確定申告の際には、確定申告書の「社会保険料控除」の欄に、その年に支払った国民年金保険料と付加保険料の合計額を記入します。
日本年金機構から送付される「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」に記載された金額を忘れずに転記しましょう。
この記事では、個人事業主に関係する社会保険料控除の種類や書き方、お得な節税の方法についてご説明しています。 本来差し引くことができるものを知らずにいるなら、税金を余計に支払うことになり損をしてしまいます。 ぜひ最後までご覧下さい[…]
付加年金はいつから廃止になりますか?
時折、年金制度の改正に関するニュースが報じられる中で、「付加年金は将来なくなってしまうのではないか」と心配される方もいらっしゃるかもしれません。
現在のところ、付加年金制度が廃止されるという具体的な予定や公式な発表はありません。
この制度は国民年金法に定められた公的な制度の一部であり、国民年金の第1号被保険者のための重要な選択肢として機能し続けています。
もちろん、将来的に年金制度全体の見直しが行われる可能性は常にありますが、現時点では廃止を心配する必要はなく、安心して利用を検討できる制度と考えられます。
制度に関する最新の情報は、日本年金機構の公式サイトなどで確認することが大切です。
まとめ
ここまで、付加年金とはどのような制度か、多角的に解説してきました。
月々400円という少額の負担で始められ、年金受給開始から2年で元が取れるという高い費用対効果は、この制度の最大の魅力です。
特に、厚生年金のない自営業者やフリーランスの方々にとって、将来の年金を少しでも増やすための確実で手軽な第一歩となります。
ただし、物価変動に弱い定額年金である点や、国民年金基金との併用ができないといった注意点も理解しておく必要があります。
これらの点を踏まえると、付加年金とは「老後のために何か始めたいけれど、大きな負担は避けたい」と考える方に最適な制度と言えます。
ご自身の収入状況や、iDeCoなど他の資産形成とのバランスを考えながら、賢く活用していくことがおすすめです。
まずは役所の窓口で相談してみるなど、具体的な行動を起こしてみてはいかがでしょうか。