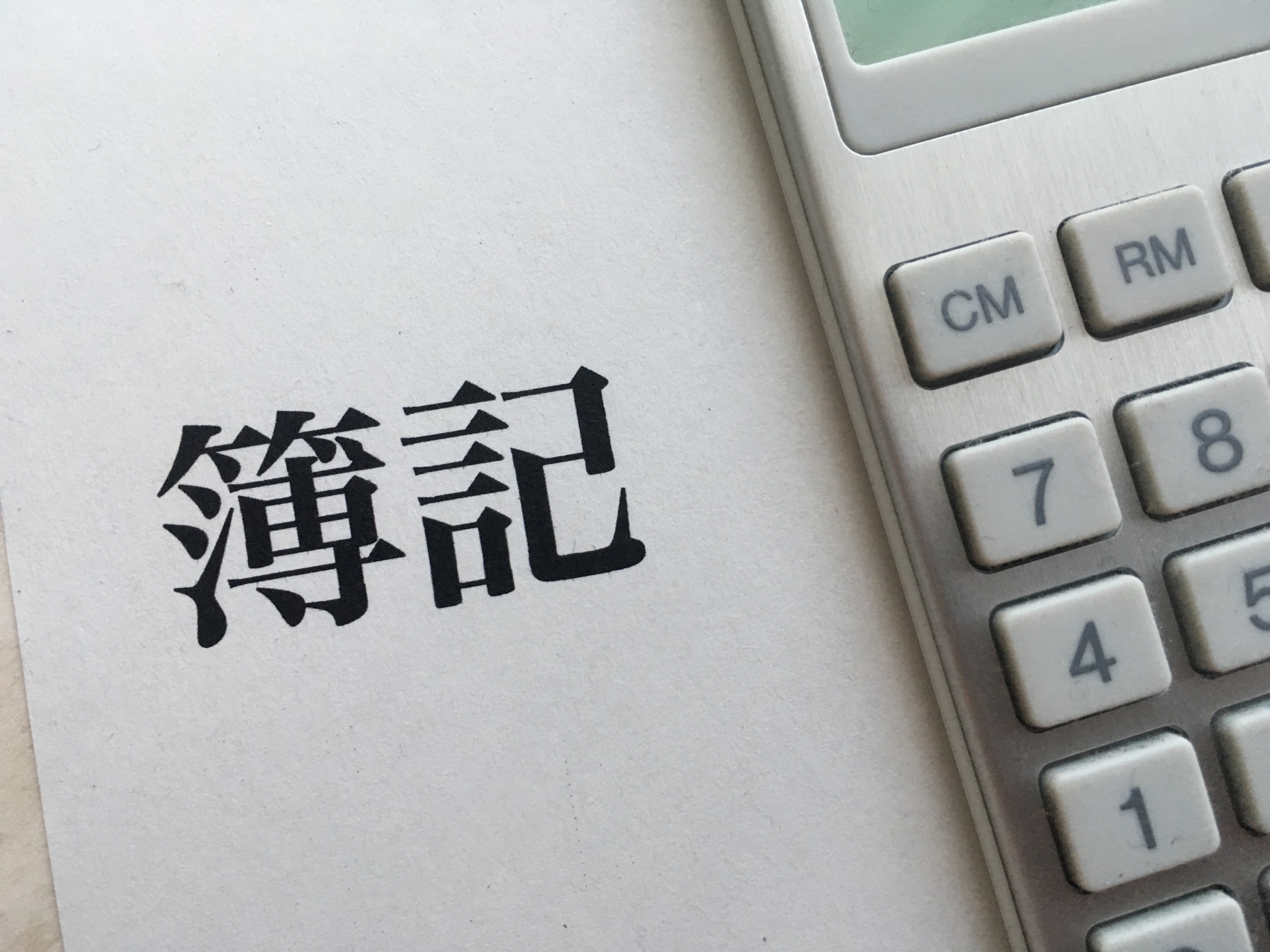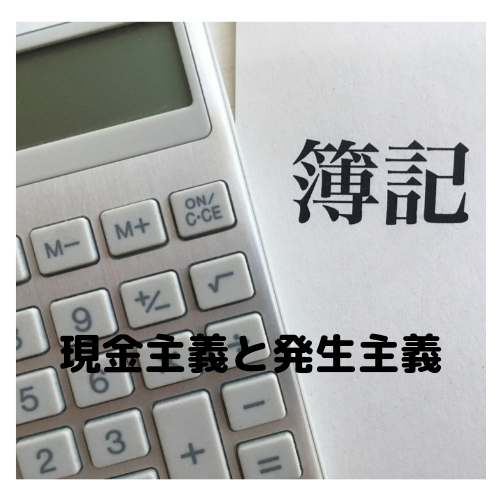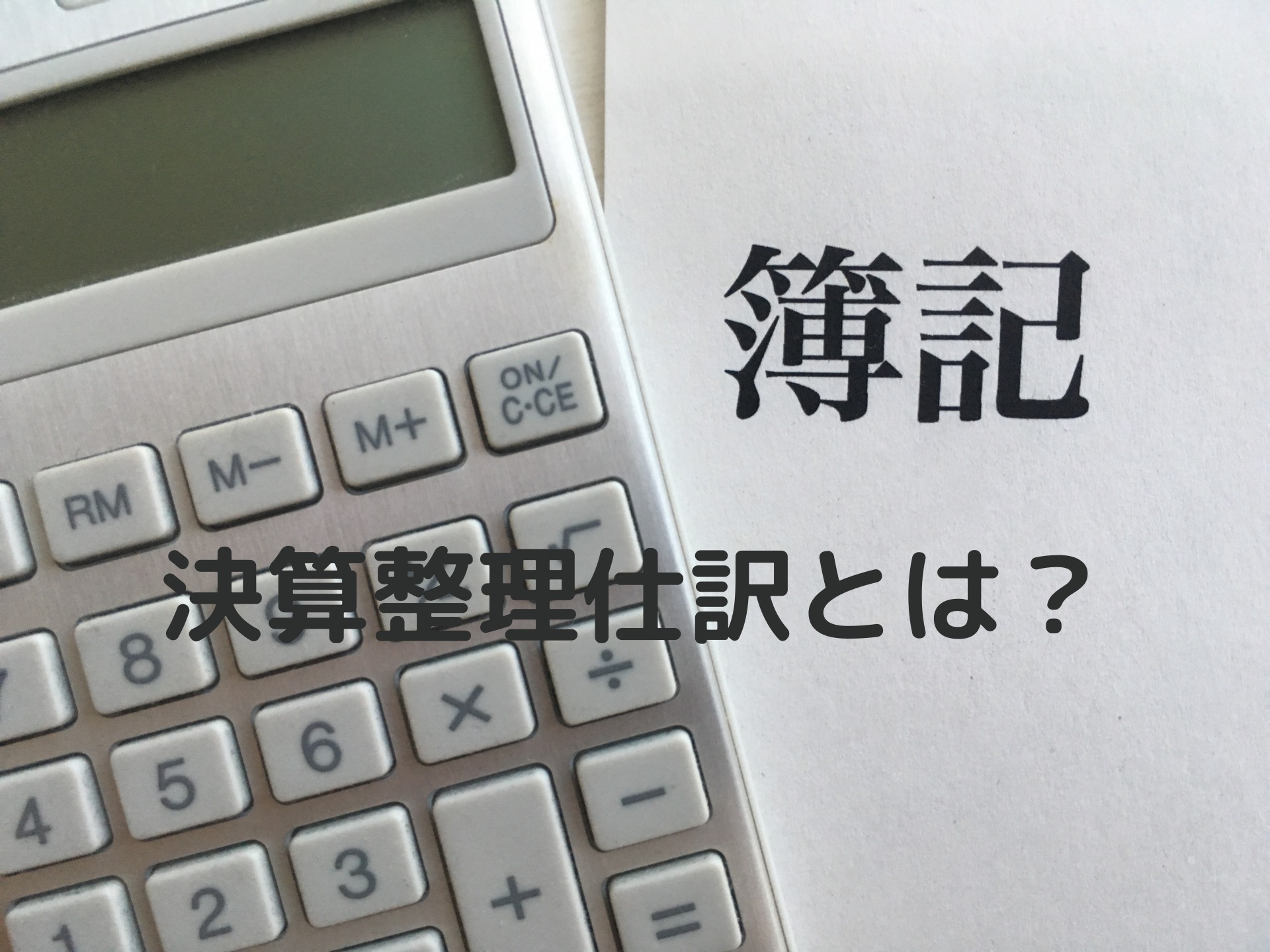簿記の学習を始めると「三分法」や「総記法」など、様々な専門用語が出てきます。
中でも、分記法とは何か、他の方法とどう違うのかが分からず、混乱してしまう方も少なくありません。
簿記の仕組みを正しく理解するためには、それぞれの記帳方法の特徴を掴むことが大切です。
この記事では、分記法とは何かという基本的な疑問から、具体的な仕訳方法、そして実務での使われ方まで、初心者にも分かりやすく解説します。
本記事のポイント
- 分記法の基本的な意味と処理の流れ
- 三分法や総記法との違いと比較
- 具体的な取引に基づいた仕訳例
- 実務で分記法が使われるケース
PR
⚠️ 確定申告、まだ終わってない方へ
「何から手をつければいいか分からない…」という方は、安心プランの「丸投げ仕分け」を使うと、仕訳の着手ハードルが下がります。ただし、最終的な経費・プライベート判断は自分で確認が必要なので、まずは無料期間で動作確認してから判断するのが安心です。
3/16まで提出以外の機能は無料で試せます。
簿記の基本!まず理解したい分記法とは?
このセクションでは、分記法の核心となる基本的な考え方について解説します。
多くの方が疑問に思う「分記法とは何か」という問いに答え、商品売買益の考え方や具体的な仕訳例を通して、その仕組みを明らかにしていきます。
また、簿記検定試験でどのように扱われるかについても触れていきます。
分記法とは
分記法とは、商品売買の取引を記録する記帳方法の一つです。
その最大の特徴は、商品を販売するたびに、その取引で得られた利益を計算して記録する点にあります。
具体的には、商品を仕入れたときは資産である「商品」勘定で記録し、販売したときには、仕入れた価格(原価)分の「商品」勘定を減少させると同時に、原価と売価の差額を「商品売買益」という収益の勘定科目で計上します。
このように、取引ごとに利益を「分けて記録する」ことから「分記法」と呼ばれています。
この方法により、帳簿を見ればいつでも個別の取引や期間中の利益の状況をリアルタイムで把握することが可能です。
特徴は商品と商品売買益の勘定科目
分記法を理解する上で鍵となるのが、「商品」と「商品売買益」という2つの勘定科目です。
- 商品(資産): この勘定科目は、仕入れた商品の原価を記録するために使います。商品を仕入れると借方(左側)に金額が記録され、資産が増加したことを示します。逆に、商品が売れると、その商品の原価分だけ貸方(右側)に記録され、資産が減少したことを表します。
- 商品売買益(収益): この勘定科目は、商品を販売した際に得られた利益(儲け)を記録します。金額は「売価 − 原価」で計算され、収益の発生として貸方(右側)に記録されます。
分記法では、この2つの勘定科目をセットで使うことで、在庫(商品)の増減と、それによって生じた利益(商品売買益)を取引の都度、正確に管理していくのです。
分記法の仕訳例
文章だけでは分かりにくい部分も、具体的な仕訳例を見ると理解が深まります。
ここでは、「原価8,000円の商品を仕入れ、それを10,000円で販売した」という取引を例に見ていきましょう。
商品を仕入れたときの仕訳
まず、原価8,000円の商品を現金で仕入れた場合の仕訳です。
資産である「商品」が増え、資産である「現金」が減ります。
| 借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 商品 | 8,000 | 現金 | 8,000 |
商品を販売したときの仕訳
次に、原価8,000円の商品を10,000円で販売し、代金を現金で受け取った場合の仕訳です。
この取引では、3つの要素が同時に動きます。
- 現金が10,000円増える(借方)
- 在庫の商品(原価8,000円)がなくなる(貸方)
- 差額の2,000円が利益として発生する(貸方)
これを一つの仕訳にまとめると、以下のようになります。
| 借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金 | 10,000 | 商品 | 8,000 |
| 商品売買益 | 2,000 |
分記法と他の記帳法を比較
このセクションでは、分記法を「三分法」や「総記法」といった他の記帳方法と比較し、それぞれのメリット・デメリットを明らかにします。
また、実務において分記法がどのような場面で使われるのか、あるいは使われないのか、その理由についても掘り下げていきます。
三分法・総記法との違いと覚え方
簿記には分記法の他に、主に「三分法」と「総記法」という商品売買の記帳方法があります。
それぞれの違いを理解することが、分記法の特徴をより深く掴むための鍵となります。
| 記帳方法 | 主な勘定科目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 分記法 | 商品、商品売買益 | ・リアルタイムで利益を把握
・決算整理が不要 |
・仕訳が煩雑になる
・取引ごとの原価管理が必要 |
| 三分法 | 仕入、売上、繰越商品 | ・日々の記帳が簡単で速い | ・期中の利益が不明
・決算整理仕訳が必須 |
| 総記法 | 商品 | ・使う勘定科目が最も少ない | ・帳簿が原価と売価で混在
・決算整理が複雑 |
覚え方としては、三分法は「仕入・売上・繰越商品の3つに分ける」、分記法は「利益を分けて記録する」と、名前と特徴を結びつけると覚えやすくなります。
三分法が日々の手軽さを重視しているのに対し、分記法は利益管理の正確性を重視している、という対比で理解するとよいでしょう。
簿記の学習を進めていると、商品売買の記録方法で必ず登場するのが三分法です。 しかし、専門用語が多く、分記法など他の方法との違いが分かりにくいため、つまずいてしまう方も少なくありません。 この記事では、簿記の初学者が抱える[…]
売上原価対立法との違いも解説
さらに発展的な論点として「売上原価対立法」という方法も存在します。
これは分記法と考え方が似ており、商品を販売した際に利益だけでなく「売上原価」を費用として計上する方法です。
分記法では「商品売買益」という収益のみを計上しますが、売上原価対立法では「売上」という収益と「売上原価」という費用を両方計上します。
結果的に利益額は同じになりますが、売上原価対立法の方が、損益計算書の形式(売上高 − 売上原価 = 売上総利益)とより直接的に連動するため、実務ではこちらが好まれる場合があります。
つまり、分記法と売上原価対立法は、どちらも「販売の都度、原価を把握する」という点で共通していますが、勘定科目の使い方が異なると理解しておきましょう。
分記法は使わない?廃止される?
「分記法は実務では使わない」「もう古い方法で廃止されるのでは?」といった声を聞くことがあります。
これは、半分正解で半分誤解です。
確かに、一般的な小売業や卸売業のように、多品種・大量の商品を扱うビジネスでは、取引のたびに原価を計算する分記法は手間がかかりすぎるため、ほとんど使われません。
このような業種では、圧倒的に三分法が主流です。
しかし、分記法が完全に使われなくなったわけではありません。
例えば、宝石、美術品、不動産、特注の機械など、単価が非常に高く、取引の回数が少ない商品を扱うビジネスでは、今でも分記法の考え方が有効です。
一つひとつの取引の利益を正確に管理することが経営上きわめて大切だからです。
したがって、分記法は「廃止される」のではなく、「用途が限定的な、専門性の高い記帳方法」として存在していると考えるのが正確です。
個人事業主の会計処理での活用法
前述の通り、分記法は特定の業種で有効です。これは法人だけでなく、個人事業主にも当てはまります。
例えば、フリーランスのデザイナーが制作したグラフィックを1点ずつ販売する場合や、ハンドメイド作家が高価なアクセサリーを販売する場合などが考えられます。
このようなビジネスでは、取引件数が限られている一方で、一つひとつの作品の原価(材料費など)と利益をしっかり管理したいというニーズがあります。
このようなケースで分記法を採用すれば、確定申告の際に必要な売上や利益の計算がスムーズになりますし、日々の経営状況も把握しやすくなります。
自分の事業が「高単価・低頻度」の取引を特徴としているなら、分記法は会計処理の有力な選択肢の一つになり得ます。
CPAラーニングで簿記を無料で学ぼう
簿記の学習には、分記法や三分法のように、一人で理解するのが難しい概念がいくつかあります。
もし独学に限界を感じたり、費用をかけずに効率よく学びたいと考えているなら、「CPAラーニング」の活用が非常におすすめです。
CPAラーニングは、公認会計士の資格予備校が運営しているeラーニングプラットフォームで、驚くことに簿記3級から1級までの講座を完全無料で受講できます。
プロの講師による分かりやすい講義動画はもちろん、テキストや問題集もすべて無料で利用可能です。
CPAラーニングの利用を検討しているものの、「完全無料」という言葉に、どこか怪しいと感じていませんか。 なぜ無料なのか、サービスの質は本当に信頼できるのか、といった疑問や不安を抱くのは自然なことです。多くの方が、お得な話の裏に[…]
分記法と三分法の違いのような混同しやすいポイントも、動画で視覚的に解説してもらうことで、スムーズに理解が進みます。
通勤時間や休憩中などのスキマ時間を活用してスマホで手軽に学べるのも大きな魅力です。
簿記の学習を始めたい方、または途中で挫折してしまった方も、この機会にぜひCPAラーニングに登録してみてはいかがでしょうか。
メールアドレスだけで、登録することができます。
\利用登録者数70万人以上!/
まとめ
この記事では、分記法とは何かというテーマについて、その基本から他の記帳方法との比較、実務での使われ方まで幅広く解説しました。
分記法の本質は、「商品を販売する都度、原価と利益を分けて記録することで、リアルタイムに経営成績を把握する」という点にあります。
この特性から、決算整理が不要になるというメリットがある一方で、日々の記帳が煩雑になるというデメリットも併せ持っています。
実務においては、取引量が多い一般的な小売業などでは三分法が主流ですが、不動産や美術品のように高単価で取引回数が少ない業種では、分記法の考え方が今なお重要です。
🔧 当サイト独自の無料診断ツール(個人情報の登録不要)
- 一般家庭の平均と比較して「高い支出」を1分でチェック。勘定科目も表示!(個人事業主・フリーランス向け)
-
🧾 会計ソフト診断あなたの業種・規模に合う会計ソフトを最短で判定