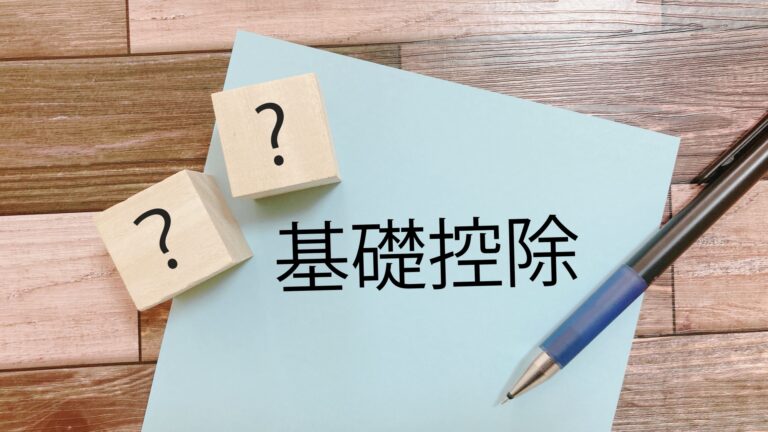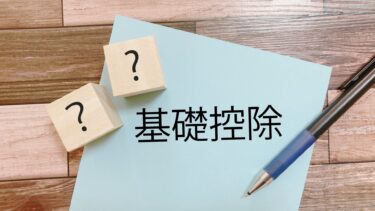2025年から、私たちの所得税や住民税の計算の土台となる基礎控除が大きく変わることをご存知でしょうか。
これまでとは金額や仕組みが変わるため、働き方や家計に大きく影響する可能性があります。
この記事では、2025年に適用される新しい基礎控除の制度について、分かりやすく丁寧に解説していきます。
ファイナンシャルプランナー2級・AFP、行政書士、日商簿記2級の資格保有者の個人事業主。詳細は運営者情報をご覧ください。
本記事の主なポイント
- 2025年から基礎控除がどう変わるかの全体像
- 新しい所得税の非課税ライン「160万円の壁」
- 所得税と住民税における控除額の違い
- 年収や家族構成ごとの注意点
| 【PR】おすすめの会計ソフト | 詳細 |
| やよいの白色申告オンライン |
個人事業主向けクラウド白色申告ソフト。インボイス制度や電子帳簿保存法にも対応。全ての機能がずっと無料で使えます。 |
| やよいの青色申告オンライン |
個人事業主向けクラウド青色申告ソフト。インボイス制度や電子帳簿保存法にも対応。全ての機能が1年間無料で使えます。 |
| 弥生会計オンライン |
法人向けクラウド会計ソフト。インボイス制度や電子帳簿保存法にも対応。全ての機能が1年間無料で使えます。 |
| タックスナップ | 記帳作業がスワイプで簡単、確定申告もスマホで完結、アプリストア4.6高評価の会計アプリ。2025年3月17日まで、「安心プラン」が1万円割引キャンペーン中です。2週間無料お試しができます。 |

ここでは2025年から始まる基礎控除の大きな変更点について、全体像から具体的な金額までを解説します。
特に、多くの方に関係する「160万円の壁」がどのようにして生まれたのか、給与所得控除との関係性も踏まえて分かりやすく紐解いていきます。
ご自身の税金がどう変わるのか、まずは基本をしっかり押さえましょう。
基礎控除引き上げ!令和7年改正の見直し点
2025年(令和7年)分の所得税から、私たち納税者の税負担を軽くするための重要な見直しが行われます。
具体的には、すべての納税者に適用される「基礎控除」と、給与所得者に関係する「給与所得控除」の金額が、そろって引き上げられることになりました。
この改正の背景には、近年の物価上昇があります。物価が上がっても給料が同じだと、実質的な生活は苦しくなってしまいます。そこで、税金の計算で差し引ける控除額を増やすことで、手元に残るお金が少しでも増えるように配慮されたわけです。
また、アルバイトやパートで働く人が年収を一定額に抑えようとする、いわゆる「103万円の壁」を意識した働き方を緩和する狙いもあります。
今回の基礎控除引き上げは、税金の仕組みを通じて、私たちの生活を支え、より柔軟な働き方を後押しする重要な一歩と言えます。
2025年1月から基礎控除額はいくらになりますか?
2025年1月以降の所得に適用される所得税の基礎控除額は、納税者本人の合計所得金額に応じて、これまで以上に細かく設定されることになります。
最大のポイントは、所得が比較的低い層に対して、控除額が大幅に増額される点です。
これまで、基礎控除は合計所得金額が2,400万円以下であれば一律で48万円でした。
しかし改正後は、合計所得金額が132万円以下(給与収入のみの場合、年収200万円に相当)の方については、基礎控除額が95万円へと大幅にアップします。
所得が増えるにつれて控除額は段階的に変わります。
ご自身の所得がどの区分に該当するのかを把握することが、税額を正しく計算する上で最初のステップとなります。
詳しい金額については、以下の表で確認してみましょう。
| 合計所得金額 | 2025年・2026年の基礎控除額 | 2027年以降の基礎控除額 |
|---|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 | 95万円 |
| 132万円超 336万円以下 | 88万円 | 58万円 |
| 336万円超 489万円以下 | 68万円 | 58万円 |
| 489万円超 655万円以下 | 63万円 | 58万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 58万円 | 58万円 |
| 2,350万円超 2,500万円以下 | 2,350万超~2,400万以下:48万円 2,400万超~2,450万以下:32万円 2,450万超~2,500万以下:16万円 |
2,350万超~2,400万以下:48万円 2,400万超~2,450万以下:32万円 2,450万超~2,500万以下:16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 | 0円 |
このように、特に合計所得金額が655万円以下の方については、2年間限定の特例措置が設けられている点も大きな特徴です。
参考:国税庁 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
基礎控除95万はいつから適用される?
新しい基礎控除額である95万円が適用されるのは、2025年(令和7年)1月1日から12月31日までの1年間の所得に対してです。
会社員の方であれば、この改正が給与に直接反映されるのは、2025年の12月に行われる年末調整のタイミングとなります。
毎月の給与から天引きされている源泉徴収税額は、年の初めにはまだ古い税額表で計算されているため、改正後の金額は反映されていません。
そのため、1年間の所得が確定する年末調整の際に、新しい基礎控除額(95万円など)を使って正しい税額を再計算し、多く払いすぎていた税金が還付される、という流れになります。
個人事業主やフリーランスの方は、2026年の2月から3月にかけて行う確定申告で、この新しい基礎控除額を適用して所得税を計算します。したがって、すぐに毎月の手取りが増えるわけではない点を理解しておくことが大切です。
新しい税金がかからないラインは160万円に
今回の改正で最も注目される変化の一つが、所得税がかからなくなる年収の上限、いわゆる「〇〇円の壁」が大きく変わることです。
これまでは「103万円の壁」として知られていましたが、2025年からは「160万円の壁」となります。
この160万円という金額は、先ほど説明した基礎控除の最低額と、給与所得控除の2つを足し合わせることで算出されます。
- 給与所得控除の最低額:65万円
- 基礎控除の最高額:95万円
今回、基礎控除だけでなく、給与所得控除も55万円⇒65万円に改正されるため、この2つを合計すると、65万円 + 95万円 = 160万円 となります。
つまり、アルバイトやパートの給与収入が年間160万円以下であれば、そこから控除額を差し引くと所得がゼロになり、結果として所得税がかからなくなるのです。
これにより、これまで103万円を超えないように勤務時間を調整していた方も、より多くの時間働くことが可能になります。ただし、これはあくまで所得税の話であり、社会保険の壁とは別問題であるため、その点には注意が必要です。
旧制度の基礎控除をおさらい
旧制度の基礎控除48万円が適用されるのは、2024年(令和6年)12月31日までの所得が最後となります。
会社員の方であれば2024年の年末調整、個人事業主の方であれば2025年春の確定申告までは、この48万円という金額で税金が計算されます。
この48万円という金額は、2020年(令和2年)の税制改正で、それまでの38万円から10万円引き上げられて設定されたものでした。
そして今回、2025年からの改正によって、この48万円という基準は、より所得の高い層(合計所得金額655万円超)に適用される58万円へと、さらに引き上げられることになります。
このように、時代の変化とともに、基礎控除の額も見直されてきました。
2025年以降の基礎控除|所得税と住民税の違いと2年間の特別ルール
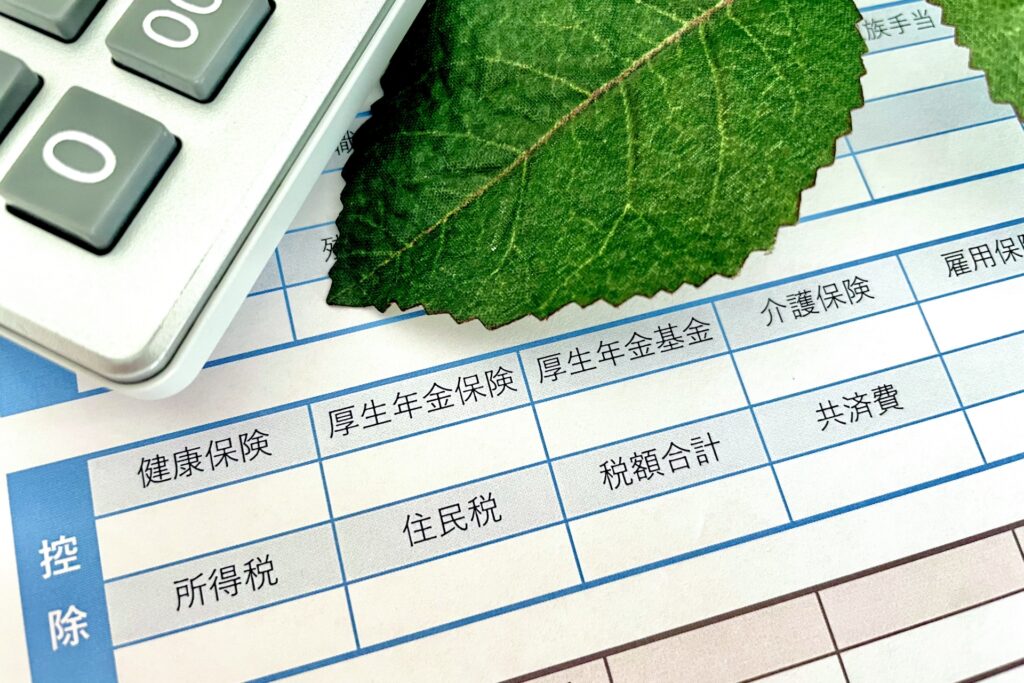
このセクションでは、所得税と住民税では基礎控除の扱いがどのように違うのか、また特定の所得層に適用される控除額や、2年間だけの特別なルールについて詳しく解説します。
ご自身の状況に合わせた、より正確な知識を身につけるために役立つ情報です。
所得税と住民税で控除額が違うので注意
今回の税制改正を理解する上で、非常に大切なポイントがあります。
それは、所得税と住民税では基礎控除の金額が異なる、という点です。
2025年から所得税の基礎控除は大幅に引き上げられますが、住民税の基礎控除については、基本的にこれまでの金額から据え置かれます。
なぜなら、住民税は私たちが住む市区町村の教育や福祉、インフラ整備といった行政サービスを支える貴重な財源であり、大幅な減収を避ける必要があるためです。
具体的な控除額の違い
- 所得税の基礎控除: 合計所得2,400万円以下で58万円~95万円(所得により変動)
- 住民税の基礎控除: 合計所得2,400万円以下で43万円
この違いにより、「所得税はかからないけれど、住民税は課税される」というケースがこれまで以上に増える可能性があります。
例えば、給与収入が100万円の場合、所得税は非課税ですが、住民税は課税対象となります。この点をしっかり認識しておくことが、家計管理の上でとても大切です。
年収いくらから?基礎控除58万円の対象
2025年からの新しい制度では、基礎控除額が58万円となる所得層が設定されます。
これは、比較的高めの所得がある方が対象となります。
具体的には、合計所得金額が655万円を超え、2,350万円以下の方が、この58万円の基礎控除の適用対象です。
給与収入のみの方で、他に所得控除がないと仮定した場合、おおむね年収850万円あたりからがこの区分に該当してきます。
これまでの制度では、所得が2,400万円以下であれば一律で48万円の控除でした。
今回の改正では、この層に対しても10万円の控除額引き上げが行われ、幅広い層に減税の恩恵が及ぶように設計されています。ご自身の年収がこの範囲にある方は、年間で所得税が数万円程度軽減される効果が期待できます。
2年限定!見逃せない基礎控除の特例
今回の基礎控除の見直しには、恒久的な変更だけでなく、2025年(令和7年)と2026年(令和8年)の2年間だけに適用される特別な措置が含まれています。
これは、物価高の影響が特に大きい中間所得層の負担を時限的に緩和するための特例です。
この特例の対象となるのは、合計所得金額が132万円を超え、655万円以下の方々です。この所得層は、所得に応じて基礎控除額が「88万円」「68万円」「63万円」の3段階に設定されます。
2027年以降はこれらの区分は一律で58万円の控除額に統一される予定です。しかし、この2年間に限っては、恒久措置である58万円にさらに上乗せする形で控除額が加算されます。
この特例は自動的に適用されるため、特別な手続きは必要ありません。
しかし、2年後には控除額が減る(=税負担が増える)可能性があることを念頭に置き、将来の家計計画を立てることが賢明と言えるでしょう。
まとめ
この記事では、2025年から大きく変わる基礎控除の制度について解説してきました。
最後に、重要なポイントを改めて整理します。今回の改正の核心は、所得税の「基礎控除」が大幅に引き上げられ、特に所得が低い層の税負担が軽くなる点にあります。
これにより、所得税の非課税ラインは、これまでの103万円から「160万円の壁」へと引き上げられます。
しかし、注意すべき点もあります。
まず、この変更は所得税に関するものであり、住民税の基礎控除は基本的に据え置かれるため、両者の違いを理解しておく必要があります。
また、税金の壁は変わっても、社会保険の扶養に関する「130万円の壁」などは依然として残ります。働き方を考える際には、税金と社会保険の両面から総合的に判断することが大切です。
2025年 基礎控除の改正は、私たちの手取りに直結する重要な変更です。
年末調整や確定申告の時期に慌てないよう、今のうちから正しい知識を身につけ、ご自身のライフプランにどう影響するかを考えておきましょう。
関連記事