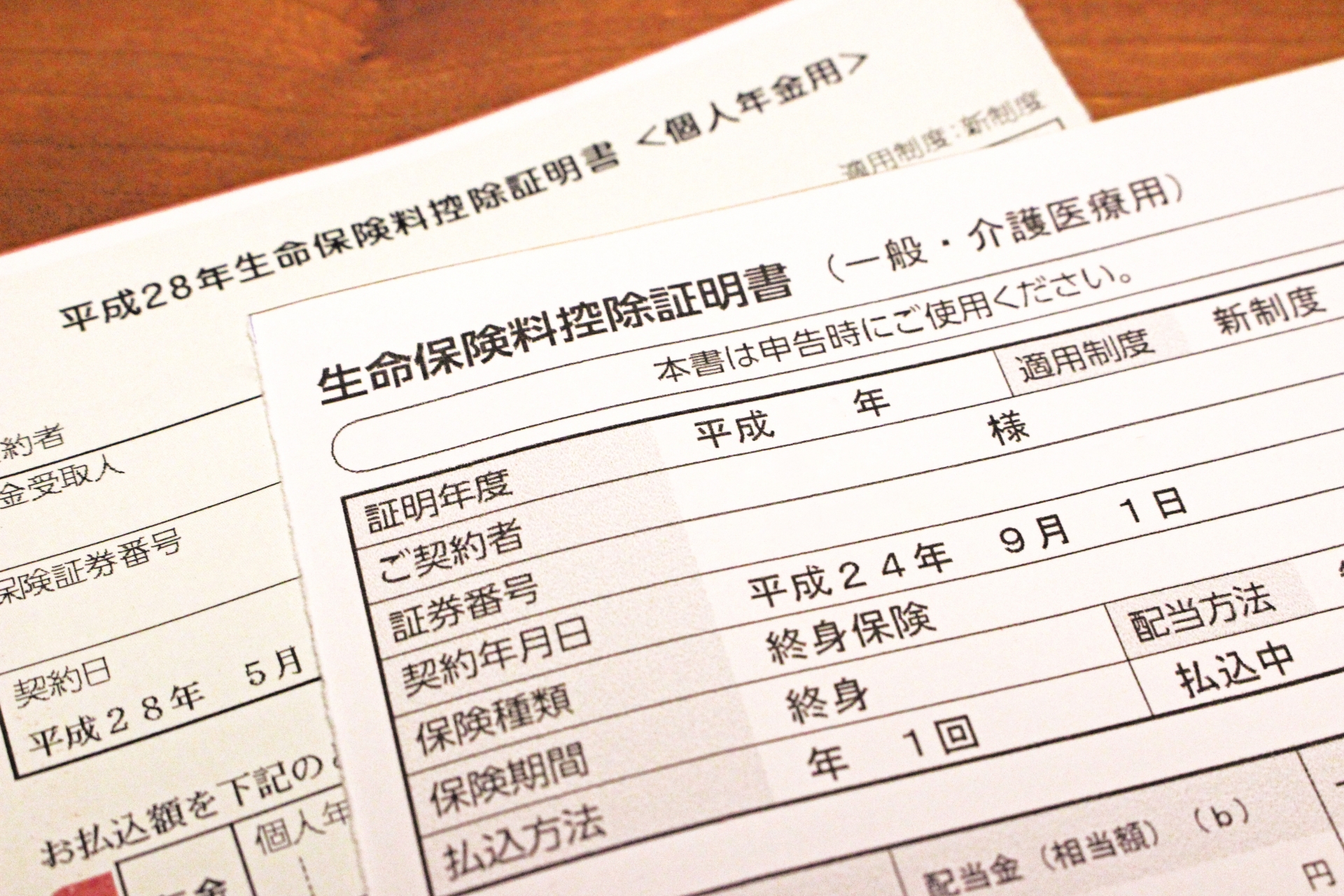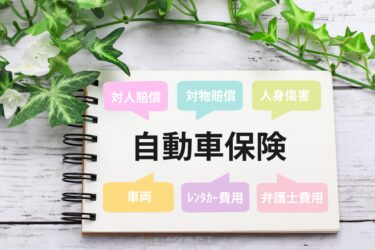個人事業主やフリーランスとして活動する中で、「もし自分が病気やケガで働けなくなったら、収入が完全に途絶えてしまうのではないか」という不安を感じたことはありませんか。
自営業の方は、ご自身の頑張りが直接収入に結びつく一方で、会社員のような手厚い公的保障がないのが実情です。
このような万が一の事態に備え、生活と事業を守るための選択肢として注目されるのが所得補償保険です。
この記事では、働けなくなったときのリスクに備えたいと考える全ての個人事業主の方へ向けて、所得補償保険の必要性から選び方、そして税金に関する疑問まで、分かりやすく解説していきます。
本記事のポイント
- 個人事業主と会社員で異なる公的保障の内容
- 所得補償保険に加入するメリットと注意点
- 自分に合った保険を選ぶための比較ポイント
- 保険料が経費になるかなど確定申告に関する知識
PR
⚠️ 確定申告、まだ終わってない方へ
確定申告がまだ終わっていない方は、まず仕訳を片付けると一気に気持ちがラクになります。特にタックスナップの「丸投げ仕分け」は、迷いがちな仕訳作業を一気に進められる機能です。
私の場合は、 667件の取引が約2秒 で仕訳されました。ただし端末や通信状況などにより、処理の時間は異なる可能性があります。
3/16までは提出・印刷以外を無料で試せます。無料のうちに使ってみて、合うかどうかを確認してみてください。
※仕訳後に、勘定科目や金額は念のため確認しておくと安心です。
※3/16まで、提出以外の機能は無料で試せます。
クーポンは、初回登録時に入力しておくとスムーズです。合わなければ無料期間中に解約できます。
▶ 無料でタックスナップを試してみる(3/16まで) ※「丸投げ仕分け」の詳細や体験談を確認できる記事はこちらなぜ所得補償保険は個人事業主の味方なのか

個人事業主は、会社員と比べて働けなくなったときのリスクが非常に大きいと言えます。
会社員であれば健康保険の傷病手当金や労災保険といった公的なセーフティーネットがありますが、個人事業主には同様の制度がありません。
このセクションでは、まず個人事業主が直面する具体的なリスクと、会社員との公的保障の違いを明らかにします。
その上で、所得補償保険がなぜ個人事業主にとって心強い備えとなるのか、保険の基本的な仕組みからメリット・デメリットまでを一つひとつ丁寧に紐解いていきます。
怪我で働けないときのリスク
個人事業主が病気やケガで働けなくなると、その瞬間から収入が途絶える直接的なリスクに直面します。
会社員であれば有給休暇を使ったり、傷病手当金を受け取ったりできますが、個人事業主にはそうした制度がありません。
例えば、フリーランスのデザイナーが腕を骨折してしまった場合、デザイン作業ができなくなり、進行中の案件はストップし、新規の受注も不可能になります。
収入がゼロになる一方で、家賃や光熱費、国民健康保険料といった生活費の支払いは待ってくれません。
事業を続けている場合、オフィスの賃料やツールの利用料などの固定費も発生し続けます。
このように、収入が途絶えることと、支出が続くことの二重の負担が、個人事業主の生活と事業基盤を大きく揺るがすリスクとなります。
貯蓄で一時的にしのぐことはできても、療養が長引けば、それも底をついてしまう可能性があります。
会社員とは違う?個人事業主の休業補償は?
個人事業主の休業補償を考える上で、会社員の公的保障との違いを理解しておくことが大切です。
両者の間には、働けなくなった際の経済的支援に大きな差があります。
主な違いは「労災保険」と「傷病手当金」の有無です。
以下の表で具体的な違いを確認してみましょう。
| 補償の種類 | 会社員 | 個人事業主 |
|---|---|---|
| 業務中・通勤中のケガ | 労災保険から休業補償給付(給与の約8割)が支給される | 原則として対象外(特別加入制度あり) |
| 業務外の病気・ケガ | 健康保険から傷病手当金(給与の約2/3)が最長1年6ヶ月支給される | 国民健康保険には傷病手当金制度がない※ |
※ただし、新型コロナウイルス感染症の流行時には、一部の自治体や国民健康保険組合で臨時的な給付措置が取られた例もあります(なお、この臨時措置はすでに終了した自治体が大半です)。
このように、会社員は業務中・業務外を問わず、働けなくなった際の所得を補う公的制度が整っています。
一方で、個人事業主が加入する国民健康保険には、基本的に傷病手当金の制度は含まれていません。
この公的保障の薄さこそが、個人事業主が自ら収入減に備える必要性を示しています。
参考:全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」
就業不能保険は本当に必要か
前述の通り、公的保障が限定的である個人事業主にとって、働けなくなった際の収入減は深刻な問題です。
このリスクをカバーするために、民間の就業不能保険(所得補償保険)の必要性が高まります。
「貯蓄があるから大丈夫」と考える方もいるかもしれませんが、治療が長期化するケースも想定しなければなりません。
例えば、大きな病気で半年間の療養が必要になった場合、その間の生活費と事業の固定費をすべて貯蓄で賄うのは簡単なことではないでしょう。
治療に専念すべき時期に、お金の心配をしなくてはならない状況は避けたいものです。
就業不能保険は、このような「もしも」のときに、毎月の生活費の支えとなる保険です。
公的保障でカバーできない部分を民間の保険で補うという考え方は、個人事業主が安心して事業を続けるための合理的なリスク管理と言えます。
所得補償保険のメリット・デメリットを解説
所得補償保険への加入を検討する際には、メリットだけでなくデメリットや注意点も把握し、総合的に判断することが鍵となります。
メリット
- 収入減少を直接カバーできる:働けない期間中、月々の収入のように給付金を受け取れるため、生活費や事業の固定費に充てることができます。
- 精神的な安心につながる:万が一への備えがあることで、日々の業務に安心して集中できます。お金の心配をせずに治療に専念できる環境は、早期の回復にもつながります。
- 幅広い状況に対応:業務中だけでなく、日常生活での病気やケガも補償の対象となります。国内外を問わず24時間補償される商品が一般的です。
- 簡単な手続きで加入できる商品が多い:多くの所得補償保険では、医師の診査が不要で、健康状態に関する告知のみで加入手続きが完了します。
デメリット
- 保険料の負担が発生する:当然ながら、保障を得るためには毎月の保険料を支払い続ける必要があります。家計や事業の収支とのバランスを考えることが求められます。
- 補償対象外となるケースがある:特にうつ病などの精神疾患の扱いは保険商品による差が大きく、補償対象外の場合や、補償期間に上限が設けられている場合など様々です。加入前に必ずご自身の契約内容を確認することが不可欠です。
- 免責期間(待機期間)がある:働けなくなってからすぐに給付金が支払われるわけではありません。例えば代表的なプランでは7日間程度の「免責期間」が設定されていますが、この日数は商品によって異なり、30日、60日、90日といったプランも存在します。この期間は自己資金で対応する必要があります。
個人事業主向け休業補償の保険には何がある?
個人事業主が働けなくなったときの収入を補う保険には、主に損害保険会社が扱うものと、生命保険会社が扱うものの2種類があります。一般的に、以下のように区別されます。
- 所得補償保険(損害保険会社):保険期間が1年更新など短期のものが多く、給付金の支払期間も最長1~2年程度の商品が中心です。骨折など、比較的短期の療養による収入減に備えるのに適しています。
- 就業不能保険(生命保険会社):保険期間が60歳まで、65歳までといった長期にわたる商品が主流です。がんや脳卒中など、長期療養や後遺症により、何年も働けない状態が続くリスクに備えます。
この記事では、短期補償タイプを「所得補償保険」、長期補償タイプを「就業不能保険」として解説します。
ご自身の職業のリスクや、どのくらいの期間の保障を重視するかによって、適切な選択は変わります。
所得補償保険を個人事業主が選ぶ際のポイント

所得補償保険の必要性を理解したところで、次は具体的に「自分に合った保険をどう選ぶか」というステップに進みます。
数ある商品の中から最適なものを見つけるためには、いくつかの比較ポイントを押さえることが不可欠です。
このセクションでは、具体的な選択肢やお得な加入方法を紹介します。
さらに、個人事業主にとって最も関心の高いテーマの一つである、保険料の経費計上や確定申告といった税金面の疑問についても、分かりやすく解説していきます。
比較ポイント
特定の保険商品をランキング形式で紹介するのではなく、ここでは個人事業主が保険を選ぶ際の基準となるポイントを解説します。
以下の点を参考に、ご自身の状況に合った保険を比較検討してください。
- 保険料と補償額のバランス:月々の保険料が手頃であることはもちろんですが、受け取れる給付金額がご自身の生活費をきちんとカバーできるかどうかが大切です。毎月の最低限必要な生活費や固定費を算出し、それを基に必要な補償額を設定しましょう。
- 免責期間の長さ:免責期間は代表的な7日のほか、30日・60日・90日・180日など様々なプランがあります。期間が長いほど保険料は安くなる傾向にあるため、ご自身の貯蓄で対応できる期間と、毎月の保険料負担のバランスを考えて選ぶことが重要です。
- 補償対象の広さ:繰り返しになりますが、精神疾患の補償は特に商品差が大きいため、ご自身のニーズと照らし合わせて、契約内容を細かく確認することが重要です。
FREENANCE:休業と賠償の備えを一つに
フリーナンスとは
近年、フリーランスや個人事業主向けの総合的な支援サービスが登場しており、その中で所得補償の選択肢も提供されています。
代表的な例が、freeeグループが運営する「FREENANCE(フリーナンス)」です。
このサービスの特徴は、所得補償と仕事上の賠償責任保険をワンセットで備えられる点にあります。
無料の会員登録だけで、業務中の事故や納品物の欠陥に対応する賠償責任保険(あんしん補償Basic、引受:東京海上日動)が自動付帯します。
情報漏えい・著作権侵害・偶然な事故による納期遅延など、いわゆる“業務過誤”まで補償範囲を広げたい場合は、有料の『あんしん補償』(引受:損保ジャパン)を選択します。
そして、この記事のテーマである所得補償については、オプションの「あんしん補償プラス」(引受:あいおいニッセイ同和損保)で備えることができます。
休業への備えと事業上の賠償リスクへの備えをまとめて検討したい方にとって、合理的な選択肢となり得ます。
詳細は、公式サイトで確認することをお勧めします。
公式サイト:あんしん補償プランはこちら
加入時の注意点
補償開始日
無料付帯の賠償保険(あんしん補償Basic)の開始日は、承認日に応じて翌月1日または15日からと定められています。
所得補償(あんしん補償プラス)の開始日は別途申し込みと承認、保険始期の設定によりますのでご注意ください。
給付上限・対象外
所得補償の給付額は平均所得の50%〜70%の範囲内で、精神障害や妊娠・出産などは対象外です。
これはFREENANCEのプランの条件であり、他の保険商品では給付上限や対象外となる条件が異なりますので、必ず個別に確認が必要です。
フリーランスとして活動している方々にとって、収入の管理やキャッシュフローの確保は重要な課題です。 フリーナンスは、そんなフリーランスを支援するための多彩なサービスを提供していますが、中にはフリー[…]
その他の選択肢(団体保険・専門家への相談)
所得補償保険に割安で加入する方法として、商工会議所が提供する「休業補償プラン」のような団体保険を活用する方法もあります。
団体のスケールメリットを活かしているため、個人で加入するよりも保険料を抑えられる場合があります。
また、どの保険が自分に合っているか判断が難しい場合は、保険の専門家であるファイナンシャルプランナー(FP)に相談するのも有効です。
多くの保険商品を比較し、中立的な立場からあなたに最適な保険を提案してくれます。
所得補償保険は経費にできる?
個人事業主の方にとって、支払う保険料が経費として認められるかは非常に気になる点です。
結論から言うと、個人事業主自身のために支払った所得補償保険の保険料は、事業の「必要経費」として計上することはできません。
ただし、経費にはなりませんが、税金の負担を軽減する「生命保険料控除」の対象となる可能性があります。
しかし、保険の種類によって扱いが異なるため注意が必要です。
生命保険料控除は、所得税や住民税の負担を軽減できる所得控除の1つです。 しかし、確定申告書の書き方や計算方法について、初めて確定申告をする方や慣れていない方にとっては大きなハードルになることもあります。 本記事では、確定申告で生[…]
確定申告の方法
生命保険会社が扱う「就業不能保険」や、損害保険会社が扱う「所得補償保険」の保険料は、契約が疾病を保障するなど一定の要件を満たす場合、生命保険料控除(多くは介護医療保険料控除)の対象になり得ます。
近年では、損害保険会社の商品でも控除対象となるものが増えています。ご自身の契約が対象になるかどうかの最も確実な確認方法は、毎年秋ごろに保険会社から送付される「生命保険料控除証明書」を見ることです。
この証明書に記載されている控除区分に従って、確定申告を行ってください。対
象となる場合、所得税では最大4万円、住民税では最大2.8万円の所得控除が受けられます。
参考:国税庁 タックスアンサー「No.1140 生命保険料控除」
勘定科目について
個人事業主が自分自身のために支払った所得補償保険料は、経費にはならないため、事業用の帳簿に勘定科目を立てて記帳する必要はありません。
もし事業用口座から支払った場合は、「事業主貸」という勘定科目で処理します。
一方で、従業員を雇用している個人事業主が、その従業員のために所得補償保険に加入し、保険料を負担した場合は経費として計上できます。
この場合の勘定科目は、保険金の受取人や契約形態によって異なります。
- 受取人が従業員(またはその家族)の場合:全従業員が対象なら「福利厚生費」、特定従業員のみが対象なら「給料手当」として扱われます。
- 受取人が事業主の場合:実務上は、保険の種類によって資産計上(前払保険料など)し、期間の経過に応じて費用化する処理や、福利厚生費と給与課税の判断が伴うため、契約内容の確認が不可欠です。
このように、対象が誰かによって会計処理が大きく変わるため注意が必要です。
自分で判断がつかない場合は、税務署や税理士などの専門家に相談することを検討してください。
事業主貸と事業主借は、個人事業主特有の勘定科目です。 正しく会計処理をする上で、この2つの勘定科目の使い方を押さえておく必要があります。 この記事では、事業主貸と事業主借の勘定科目の仕訳例や決算時の相[…]
まとめ:所得補償保険でリスクに備えよう
この記事では、個人事業主が所得補償保険を検討する上で知っておくべきポイントを解説しました。
会社員と異なり、傷病手当金などの公的保障が手薄な個人事業主にとって、病気やケガで働けなくなった際の収入減少は事業の存続にも関わる深刻なリスクです。
所得補償保険は、この万が一の事態に備え、ご自身の生活と大切な家族を守るための有効な手段となります。
ただし、この記事で解説した免責日数や補償範囲などの内容はあくまで一般的な例であり、実際の補償内容や保険料は個別の商品や契約によって大きく異なります。
保険を選ぶ際は、単に保険料の安さだけで決めるのではなく、ご自身の職業やライフスタイルに合った補償額、免責期間、そして補償範囲を慎重に比較検討することが何よりも大切です。
加入を検討する際は、必ず複数の保険商品を比較し、ご自身の契約内容を詳細に確認してください。
まずはご自身にとって毎月いくらの生活費が必要かを把握し、それを基に保険商品の資料請求や専門家への相談といった具体的な一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。