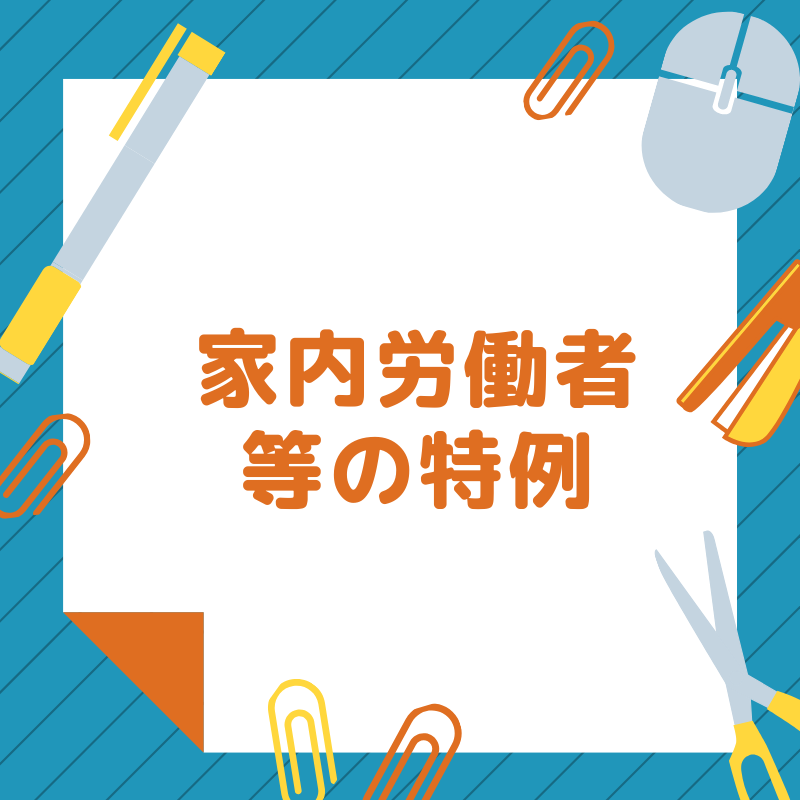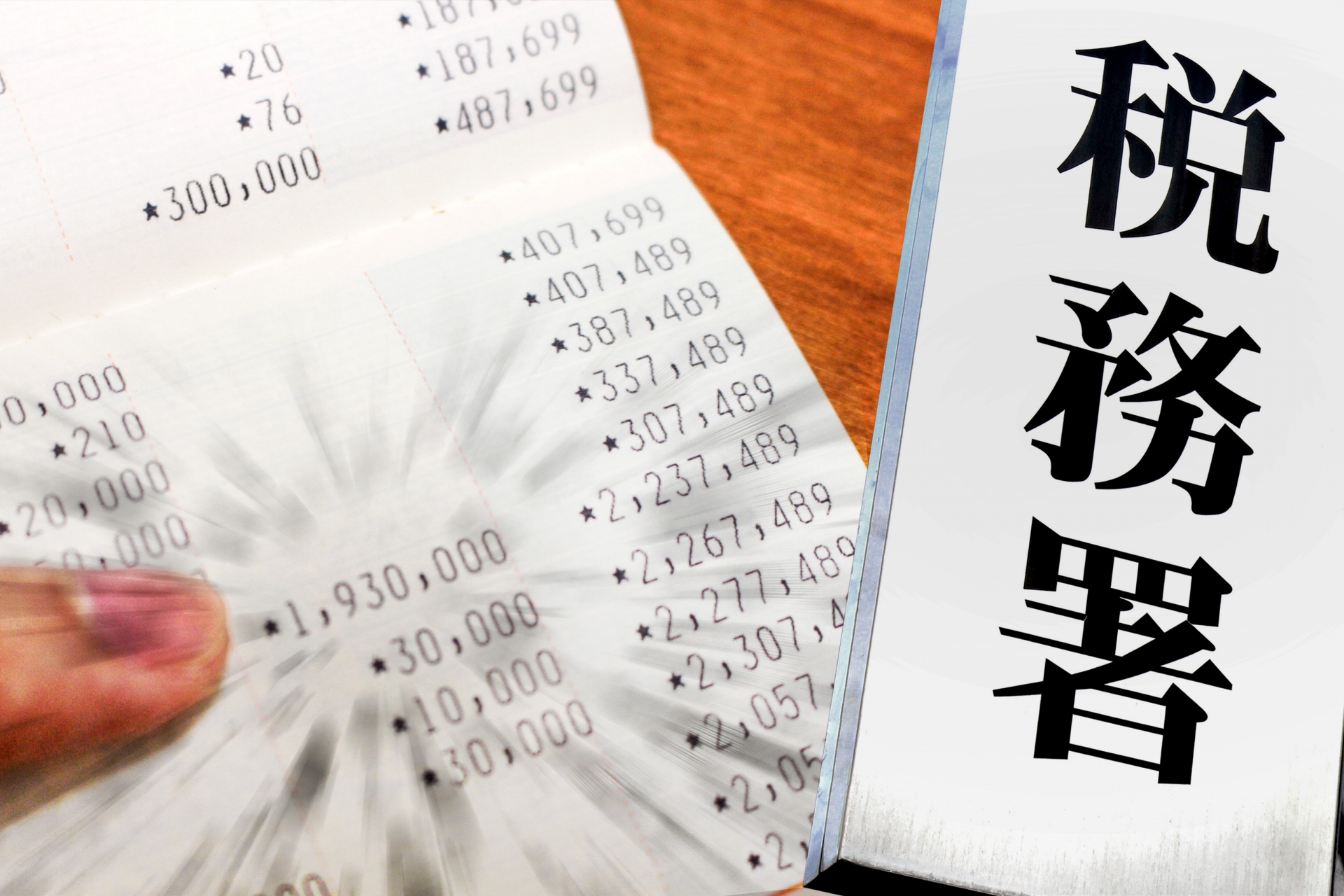一定の条件を満たす事業主が利用できるのが、「家内労働者等の必要経費の特例」です。
この特例を利用できれば、最大65万円まで経費の計上ができるため、その分所得金額を減らすことができ節税につながります。
この記事では「家内労働者等の必要経費の特例」がどんな制度か、そして、その特例を受けることのできる家内労働者等についてご説明しています。
広告・PR
⚠️ 確定申告の準備はお済みですか?
2月、3月になってから領収書を整理するのはもう終わり!
スマホでスワイプするだけの次世代アプリ「Taxnap」なら、今からでも間に合います。
※副業・フリーランス・個人事業主向け
年払い契約で招待コード【 SC5RJEQK 】
を入力すると1,500円割引で利用できます。
家内労働者等の必要経費の特例とは
家内労働者等の必要経費の特例とは、確定申告の際に経費が65万円まで認められる経費の特例です。
通常、事業所得や雑所得については、収入から必要経費を差し引いて所得金額を計算します。
ですから節税のためには、必要経費を漏れなく計上することが重要です。
しかし事業内容によっては、それほど必要経費がかからないかも知れません。
仮に必要経費が30万円しか計上できないとしても、この特例を利用すれば65万円まで経費として認められるので、その差は大きいです。
この特例を利用できるかどうかは、「家内労働者等」に該当するかどうかで決まります。
参考:国税庁 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
特例の申告要件
最初に、国税庁のホームページで家内労働者等について説明されている内容をご覧ください。
家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
この中で説明されている家内労働者等に該当すれば、特例を利用することができます。
国税庁のサイトの説明だけでは、わかりにくい部分もありますので、これから詳しく見ていきたいと思います。
家内労働法に規定する家内労働者
この説明に該当するのは、いわゆる内職(家の中で働く人)をしている人です。
業務委託を受けて商品の製造や加工などを行っていて、同居の親族以外に人を雇ったりせずに仕事をしている人のことです。
家内労働者に該当するかどうかは、下記のサイトで詳しく説明されていますので参考にして下さい。
参照:厚生労働省 埼玉労働局 委託者、家内労働者と家内労働法
外交員、集金人、電力量計の検針人
この表現は、わかりやすいですね。
保険の外交員、新聞やNHKの集金人、電気や水道の検針人などは家内労働者等に該当しますので、必要経費の特例を利用することができます。
特定の人に、継続的に、人的役務の提供を行う人
「特定の人に、継続的に、人的役務の提供を行う人」として考えられる、仕事の一例としては次の通りです。
- ライターやwebデザイナー
- シルバー人材センターの作業員
- ヤクルトの配達員
- 特定の会社に所属する英会話やピアノの講師
注意が必要な点としては、上記の業種の方でも家内労働者の対象とならない場合があることです。
例えば、英会話やピアノを教えている講師の方でも、特定の会社に所属しておらず自宅で教えているといった場合は、家内労働者の特例を適用することはできません。
理由としては、自宅で教えている場合は不特定の人を対象としているとみなされるからです。
あくまでも、考え方としては「特定の人に」、「継続的に」、「人的役務の提供を行う人」が対象となることを抑えておきましょう。
また、ライターとして、特定の事業者に継続して記事を作成して納品している場合、この特例の対象となる可能性があります。
ただし、注意点もあります。
これは当メディアの管理人の実例ですが、複数のWEBサイトを運営して広告収入を得ており、それ以外にも、特定の事業者に継続して記事を作成して納品していた時期がありました。
それで、事業収入の一部が、家内労働者としての働き方に該当する場合でも、経費の特例を使えるか税務署に確認したことがあります。
結果としては、必要経費の特例を利用することができないということでした。
これは、あくまでも私の例です。
ご自身の仕事が、家内労働者等に該当するかどうか判断がつかない場合は、一度税務署や税理士などに確認されるようお勧め致します。
家内労働者等に該当する場合
家内労働者等に該当する業種の方で、年間の経費の金額が毎年65万円を超えるようなケースは多くないと思います。
この特例を適用できれば、毎年65万円まで経費として認められますので節税効果が大きくなります。
ただし、給与所得など他の収入があると、差し引き調整が必要となるため注意が必要です。
例えば、給与所得にかかる給与所得控除65万円に加えて、事業所得にかかる必要経費は、実際には30万円しか掛かっていないのに、必要経費の特例の65万円を加えて130万円の経費計上はできません。
このケースでは、実際にかかった必要経費の30万円分のみを経費計上する必要があります。
下記の記事では、特例を利用することによる節税効果や、確定申告の際の書き方についてご説明していますので参考にして下さい。
関連記事:【確定申告】家内労働者等の特例で税金はどのくらい変わる?
関連記事:「家内労働者等の必要経費の特例」の書き方|計算書・決算書・確定申告書
もし家内労働者等に該当するのに、これまでの確定申告で特例を使っていなかった場合は、更正の請求を行うことで払いすぎた税金を取り戻すことができます。
過去5年間に遡って請求することができますので、詳しくは国税庁のサイトでご確認下さい。
公式サイト:国税庁 No.2026 確定申告を間違えたとき
まとめ
家内労働者等の特例を利用すれば、必要経費が65万円まで認められます。
家内労働者等に該当するのは次の通りです。
- 家内労働法に規定する家内労働者
- 外交員、集金人、電力量計の検針人
- 特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人
家内労働者等に該当するかどうか判断がつかない場合は、一度税務署や税理士に確認しましょう。