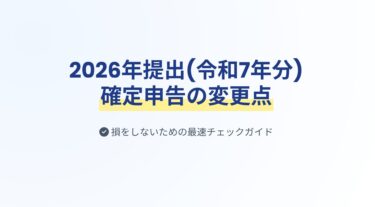この記事では、減価償却費の仕訳や、定額法と定率法の違いについてご説明しています。
また、減価償却の特例についてもご紹介していますので、ぜひ参考にして下さい。
PR
⚠️ 確定申告、まだ終わってない方へ
確定申告がまだ終わっていない方は、まず仕訳を片付けると一気に気持ちがラクになります。特にタックスナップの「丸投げ仕分け」は、迷いがちな仕訳作業を一気に進められる機能です。
私の場合は、
667件の取引が約2秒
で仕訳されました。ただし端末や通信状況などにより、処理の時間は異なる可能性があります。
3/16までは提出・印刷以外を無料で試せます。無料のうちに使ってみて、合うかどうかを確認してみてください。
※仕訳後に、勘定科目や金額は念のため確認しておくと安心です。
🎁 紹介コードで5,000円OFF
招待コード:SC5RJEQK
(↑長押しでコピーできます)
※安心プラン(年払い)限定。
※3/16まで、提出以外の機能は無料で試せます。
減価償却費とは
減価償却費とは、固定資産を購入したのち、それぞれの固定資産の耐用年数に応じて経費にする際に使用する勘定科目です。
固定資産は、基本的に一度には経費計上しません。
固定資産を一度に経費にしない理由は、費用収益対応の原則と関係があります。
当期の収益を得るために要した費用分のみを、計上する必要があるということです。
基本的に購入した固定資産は、何年にもわたって使用しますよね。
その間に、固定資産を事業で使用することで、毎年収益が発生します。
それなのに、固定資産を購入した年に、全額を経費にしてしまうと毎年の収益に対応しなくなります。
ですから、固定資産の種類に応じて定められている、法定耐用年数に合わせて各年に応じた経費計上が必要となります。
ただし、減価償却費として経費計上しない固定資産もあります。
例えば、下記の通りです。
少額の資産とは、1年以内に消費するか10万円未満のものを言います。
この場合は、複数年に渡って減価償却するのではなく、消耗品費として当期に全額を経費にします。
また、目減りしない資産(土地など)や販売目的の資産についても、減価償却の対象ではありませんので注意が必要です。
定額法と定率法
減価償却費の計算方法については、主に定額法と定率法の2種類に分けることができます。
個人事業主の場合、原則は定額法で会計処理をします。
定額法とは
定額法とは、資産の耐用年数にわたって、毎年一定の金額を必要経費として計上していく計算方法です。
定額法の計算方法は、資産を取得した日によって異なります。
平成19年3月31日以前に取得した場合
※残存価額は取得価額の10%で計算します。
平成19年4月1日以後に取得した場合
個人事業主の場合は原則、定額法が適用されます。
定率法とは
定率法は耐用年数の期間に渡って、一定の率で計算した金額を費用として計上する方法です。
定率法の計算方法も、資産を取得した日によって異なります。
平成19年3月31日以前に取得した場合
平成19年4月1日以後に取得した場合
※上記の方法で計算した金額が、償却保証額(取得価額×保証率)より下回った場合は、その年から次のように計算します。
定率法の特徴は、初年度が最も必要経費を多く計上できることになり、年の経過とともにその金額が減っていきます。
個人事業主の場合は、届出書を提出することによって定率法を選択することもできます。
ただし、定額法でしか減価償却できない資産がありますので、注意が必要です。
例えば、建物や建物附属設備、構築物などの資産を取得した日が次の条件に該当すれば、定額法での処理になります。
- 建物・・平成10年4月1日以後
- 建物附属設備・構築物・・平成28年4月1日以後
減価償却費の仕訳例
定額法による減価償却の仕訳例をご紹介したいと思いますが、減価償却の処理方法には「直接法」と「間接法」とがあり、使用する勘定科目が異なります。
それぞれの仕訳を確認してみましょう。
●1月に事業で使用する目的で軽自動車を新車で購入し、代金の120万円を銀行口座から支払った。
●期末に償却率0.25をかけて減価償却費を計算した。(直接法)
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 減価償却費 | 300,000 | 車両運搬具 | 300,000 |
直接法では、車両運搬具の勘定科目の減少として仕訳を切ります。
●期末に償却率0.25をかけて減価償却費を計算した。(間接法)
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 減価償却費 | 300,000 | 減価償却累計額 | 300,000 |
間接法の場合は、減価償却累計額という勘定科目を使って会計処理を行います。
もし、車を事業だけでなくプライベートでも使用している場合、プライベート分は経費計上できません。仮に車を事業6、プライベート4の割合で使用している場合には、下記のような仕訳を切る必要があります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 減価償却費 | 180,000 | 車両運搬具 | 300,000 |
| 事業主貸 | 120,000 | | |
プライベート分の40%は、上記のように事業主貸の勘定科目を使って仕訳をして、減価償却費とプライベート分を区別する必要があります。
加えて、上記の例は車を購入したのが1月でしたが、年の途中に購入したときは、初年度については使用月の割合に応じて減価償却費を計上します。
例えば、個人事業主が仕事の為に車を購入して、使用を開始したのが10月だった場合、初年度には10月~12月の3か月分しか費用計上することができません。
このように、初年度については月数に応じた按分計算により、減価償却費を計上する必要があることには注意が必要です。
減価償却費の耐用年数
減価償却費を計上する際に使用する耐用年数は、固定資産の種類に応じて決められています。
例えば、主な固定資産の耐用年数は以下の通りです。
- 軽自動車・・4年
- 乗用車・・6年
- 複合機(コピー機)・・5年
- パソコン・・4年
- 机や椅子・・金属製15年、その他8年
このように固定資産の種類によって、耐用年数は定められていますから、その期間に応じて減価償却費を計上することになります。
ちなみに、耐用年数以降は経費計上できませんが、継続して固定資産を使用することは問題ありません。
国税庁のサイトで、固定資産の種類に応じた耐用年数を確認することが出来ます。
参照:国税庁 耐用年数表
中古の資産を購入した場合
中古で固定資産を購入した場合は、最初に耐用年数の計算をする必要があります。
さきほどご説明したように、固定資産にはその種類に応じた耐用年数が定められています。
しかし、中古で固定資産を購入した場合は、法定耐用年数を当てはめるのではなく、下記のように計算します。
- 中古の耐用年数=(法定耐用年数ー中古の固定資産の経過年数)+(中古の固定資産の経過年数×20%)
例えば、中古の複合機(2年落ち)を購入したとします。
複合機の法定耐用年数は5年ですが、中古で購入していますので耐用年数の計算が必要です。
上記の式に当てはめて計算すると、下記のようになります。
小数点以下については、すべて切り捨てになります。
よって、この複合機の償却期間は3年です。
ちなみに、中古で購入した固定資産が、法定耐用年数を過ぎている場合の計算は次の通りです。
仮に、中古の軽自動車(5年落ち)を購入した場合の計算は次の通りです。
軽自動車の法定耐用年数は4年です。
その年数よりも古い中古の軽自動車を購入していますので、上記の計算式を使います。
注意点としては、0.8という数字です。
複合機の例のように、小数点以下を切り捨てると0になって、償却期間がなくなってしまい減価償却出来ません。
今回の例のように、計算した数字が小数点以下を切り捨てた結果、2年に満たない時は償却期間を2年とすることができます。
ですから、中古の軽自動車(5年落ち)を事業で使うために購入しても、2年は減価償却して経費計上することが可能です。
特例や他の計算方法
基本的には、固定資産の取得価額が10万円以上であれば、固定資産として計上して耐用年数に応じて減価償却を行う必要があります。
ただし、耐用年数を考慮しなくてもいい特例や償却方法があります。
少額減価償却資産の特例
少額減価償却資産の特例とは、購入した30万円未満の固定資産の全額を当期に必要経費として計上できる特例です。
少額減価償却資産の特例は、青色申告者が利用できます。
当期の売上などにもよりますが、固定資産を購入したその年に全額経費にできるので節税効果が期待できます。
一括償却資産
一括償却資産とは、取得した資産の価格が10万円以上~20万円未満のものであれば、耐用年数に関係なく3年間にわたり、毎年3分の1の金額を減価償却していく方法です。
この方法は、白色申告・青色申告のどちらでも用いることができます。