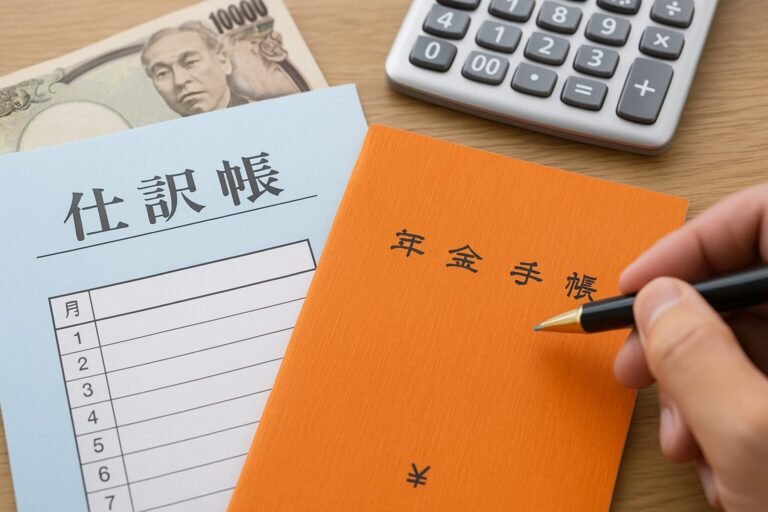「国民年金を支払ったとき、勘定科目は何を使えばよいのか?」「年金を受け取った時の会計処理は?」と悩んでしまうことはありませんか。
この記事では、特に個人事業主やフリーランスの方が知っておくべき年金に関する正しい仕訳の方法を、具体的なケースごとに分かりやすく解説します。
本記事のポイント
- 個人事業主が支払う国民年金の正しい勘定科目
- 年金保険料が経費になるか、または所得控除になるか
- 法人や従業員を雇用した場合の厚生年金の仕訳方法
- 個人事業主が将来、年金を受け取った際の会計処理
PR
⚠️ 確定申告、まだ終わってない方へ
「何から手をつければいいか分からない…」という方は、タックスナップの「丸投げ仕分け」を使うと、仕訳作業が一気に進みます。
私の場合は、 667件の取引が約2秒 で仕訳されました。
ただし、使用しているスマホや通信状況などにも左右されるため、まずは無料期間で動作確認してから継続利用を判断するのが安心です。
※自動仕訳後は「勘定科目の最終確認」だけは行うのがおすすめです。
※3/16まで、提出以外の機能は無料で試せます。
個人事業主の年金に関する勘定科目の基礎知識
このセクションでは、個人事業主やフリーランスの方が直面する年金の会計処理に焦点を当てます。
国民年金や国民年金基金を支払った際の正しい勘定科目、経費にできるのか、といった基本的な疑問から解説します。
さらに、青色申告や白色申告での具体的な仕訳方法、会計ソフトでの設定例、年金収入を得た場合の処理まで、個人事業主が知っておくべき年金の仕訳について網羅的に解説します。
年金の勘定科目の基本
個人事業主が支払う国民年金は、事業を運営するために直接かかった費用とはみなされません。
そのため、会計上は必要経費として扱うことができません。
これは、国民年金が事業主個人の将来の生活保障のための支出、つまりプライベートな支出と位置付けられているためです。
ただし、プライベートな支出であっても、どの口座から支払ったかによって会計処理の必要性が変わってきます。
- プライベート用の口座:帳簿に仕訳を記載する必要はありません。
- 事業用の口座:帳簿に記載する必要があります。
事業用の口座から国民年金の保険料を支払った場合、使用する勘定科目は「事業主貸(じぎょうぬしかし)」です。
「事業主貸」とは、事業用の資金を、事業とは関係のない事業主個人の生活費やプライベートな支払いのために使った場合に用いる勘定科目です。
例えば、事業用の普通預金口座から国民年金保険料(令和7年度の月額)17,510円が引き落とされた場合の仕訳は以下のようになります。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 事業主貸 17,510円 | 普通預金 17,510円 |
この仕訳は、事業用の普通預金が17,510円減少し、その分を事業主個人に貸した(事業主個人の支払いに充てた)という資金の動きを示しています。
「租税公課」や「社会保険料」といった勘定科目と混同しやすいですが、これらは事業に関連する税金や、従業員を雇用した際の社会保険料を経費として計上する場合に使うものです。
個人事業主自身の国民年金は、経費ではないため「事業主貸」で処理すると覚えておきましょう。
国民年金は所得控除扱い
前述の通り、国民年金の保険料は事業の経費にはなりません。
しかし、経費にならなくても、税制上の非常に大きなメリットが存在します。
それは、支払った保険料の全額が「社会保険料控除」の対象となる点です。
「社会保険料控除」は所得控除の一種です。
確定申告の際に、その年に支払った国民年金保険料の全額を所得から差し引くことができます。
これにより、課税対象となる所得金額が減るため、結果として所得税や翌年の住民税の負担が軽減されます。
この記事では、個人事業主に関係する社会保険料控除の種類や書き方、お得な節税の方法についてご説明しています。 本来差し引くことができるものを知らずにいるなら、税金を余計に支払うことになり損をしてしまいます。 ぜひ最後までご覧下さい[…]
確定申告書を作成する際、第一表および第二表の社会保険料控除の欄に、支払った国民年金保険料の合計額を忘れずに記入する必要があります。
この金額を証明する書類として、毎年10月下旬から11月上旬頃に日本年金機構から社会保険料(国民年金保険料)控除証明書というハガキが送付されます。
確定申告の際には、この証明書を申告書に添付することが原則として求められます。
なお、e-Tax(電子申告)で確定申告を行う場合、この控除証明書の添付を省略することができます。
ただし、添付を省略した場合であっても、税務署から提示を求められた場合に備えて、法定申告期限から5年間は自宅などで保管する義務がありますので注意が必要です。
ちなみに、生計を一つにしている配偶者や子どもの国民年金保険料をあなたが支払った場合も、その全額があなたの社会保険料控除の対象に含められます。
国民年金基金の仕訳方法
国民年金基金は、個人事業主やフリーランスなどが、老齢基礎年金に上乗せして加入できる公的な年金制度です。
この国民年金基金の掛金も、国民年金保険料と全く同じ扱いになります。
- 経費について: 事業の経費にはなりません。
- 仕訳について: 事業用口座から支払った場合は、勘定科目「事業主貸」で処理します。
- 控除について: 支払った掛金の全額が「社会保険料控除」の対象となります。
国民年金基金に加入している場合、国民年金とは別に「社会保険料控除証明書」が送付されますので、確定申告時には国民年金の分と合算して申告します。
freeeなどの会計ソフトでの仕訳
freeeや弥生などの会計ソフトを利用している場合、国民年金の処理は簡単になります。
これらの会計ソフトを銀行口座やクレジットカードと連携させていれば、国民年金の支払いの明細が自動で取り込まれます。
例えばfreeeでは、取り込まれた明細に対して、国民年金の支払いであることを一度登録するだけで、AIが学習します。
その結果、勘定科目を「事業主貸」として自動で推測してくれるようになります。
このような会計ソフトを導入すれば、毎月数時間かかっていたかもしれない手作業での明細入力や、勘定科目で悩む時間から解放され、営業活動に集中したり、本業のスキルアップのための学習に充てたりすることができるようになります。
今では、会計処理だけでなく確定申告までスマホで完結できる、タックスナップやFinFinなどのアプリも利用者が増加しています。
会計ソフトの利用を検討している場合は、以下の記事も参考にしてください。
個人事業主として事業を運営する上で、正確な会計処理やスムーズな税務申告は欠かせません。 しかし、日々の記帳や青色申告の準備は大変な作業となりがちです。 そこで、本記事では、初心者の方でも扱いやすい会計ソフトや無料で利用できる会計[…]
年金収入の仕訳
これまで支払う側の処理を見てきましたが、年金を「受け取る」場合の処理も確認しておきましょう。
個人事業主が受け取る公的年金は、雑所得(公的年金等)という別の所得区分で扱われ、事業所得とは分けて税金計算が行われます。
そのため、もし年金が事業用口座に振り込まれた場合、その仕訳には勘定科目の事業主借(じぎょうぬしかり)を使用します。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 普通預金 100,000円 | 事業主借 100,000円 |
事業主借は、事業主貸の逆で、事業主個人の資金を事業用口座に入れた場合などに使う勘定科目です。
ここで絶対に避けたい間違いは、「雑収入」という勘定科目を使ってしまうことです。
「雑収入」として処理すると、年金収入が事業所得の一部とみなされ、本来よりも事業所得が過大に計算されてしまいます。
その結果、納めるべき所得税や住民税、国民健康保険料などが不必要に高額になってしまう恐れがあるため、年金の入金は必ず「事業主借」で処理してください。
この記事では、雑収入の勘定科目についてご説明しています。 雑収入の勘定科目を使う際の注意点や仕訳例、決算書や確定申告書の書き方を確認することができます。 雑収入とは 雑収[…]
法人・従業員雇用の年金の勘定科目
ここでは、法人や、従業員を雇用している個人事業主の年金処理について解説します。
個人事業主自身の国民年金とは異なり、法人が負担する従業員の厚生年金保険料などは「経費」として扱われます。
従業員の給与から天引きする際の「預り金」や、会社負担分である「法定福利費」といった、法人特有の勘定科目と仕訳方法を紹介します。
法人の勘定科目
法人は、役員や加入要件を満たす従業員を厚生年金保険に加入させる義務があります。
厚生年金保険料は、従業員と会社が半分ずつ負担します。
この会計処理は、個人事業主自身の国民年金とは全く異なり、以下の2つの勘定科目が中心となります。
- 預り金(あずかりきん):従業員が負担する分の保険料です。会社は、従業員の給与からこの金額を天引き(源泉徴収)します。この天引きしたお金は、一時的に会社が預かっているだけのお金(負債)であるため、「預り金」として処理します。
- 法定福利費(ほうていふくりひ):会社が負担する分の保険料です。これは、法律で定められた福利厚生費用であり、会社の「経費」として計上できます。
具体的な仕訳の流れは以下の表のようになります。
仕訳例:厚生年金保険料(従業員負担分5万円、会社負担分5万円の場合)
| 日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 給与支払時 (給与30万円と仮定) |
給与手当 300,000 | 普通預金 250,000 預り金 50,000 |
従業員負担分の厚生年金を天引き |
| 保険料納付時 (合計10万円を納付) |
預り金 50,000 法定福利費 50,000 |
普通預金 100,000 | 会社負担分を経費計上し合算して納付 |
個人事業主の場合
個人事業主であっても、常時5人以上の従業員を雇用する事業所や、任意で適用を受けた事業所は、社会保険の強制適用事業所となります。
その場合、個人事業主は従業員を厚生年金に加入させる義務が生じ、その会計処理は前述の法人と全く同じになります。
- 従業員負担分: 給与から天引きし、「預り金」として処理します。
- 事業主負担分: 納付時に「法定福利費」として処理し、事業の必要経費に計上します。
注意が必要なのは、この「法定福利費」として経費にできるのは、あくまで従業員のために事業主が負担した分だけである、という点です。
個人事業主自身の国民年金保険料は、従業員がいたとしても「事業主貸」であり、経費にはならない原則は変わりません。
まとめ
この記事では、個人事業主と法人における年金の勘定科目について詳しく解説してきました。
要点を整理すると、最も重要な分岐点は「誰の」「どの年金か」ということです。
個人事業主自身の国民年金や国民年金基金は、事業の経費にはならず、事業用口座から支払った場合は「事業主貸」で処理します。
これは個人の支出であるためですが、確定申告で「社会保険料控除」として所得から全額控除できるため、節税効果は非常に大きいです。
この際、e-Taxで申告しても控除証明書の5年間保管義務がある点に注意しましょう。
一方で、法人や、従業員を雇用する個人事業主が支払う従業員の厚生年金保険料は異なります。
事業主が負担する半分は「法定福利費」という経費になり、従業員から預かった半分は「預り金」で処理します。
また、年金を受け取る際の勘定科目も、間違いの多いポイントです。
事業用口座に年金が振り込まれた場合、それは事業の売上(雑収入)ではなく、個人の資金であるため、「事業主借」として処理します。
この処理を誤ると事業所得が過大になり、税負担が増える恐れがあるため、厳格に区別してください。
これらのルールを正しく理解し、適切に仕訳を行うことが、正確な帳簿作成と、適切な節税につながります。
🔧 当サイト独自の無料診断ツール(個人情報の登録不要)
- 一般家庭の平均と比較して「高い支出」を1分でチェック。勘定科目も表示!(個人事業主・フリーランス向け)
-
🧾 会計ソフト診断あなたの業種・規模に合う会計ソフトを最短で判定