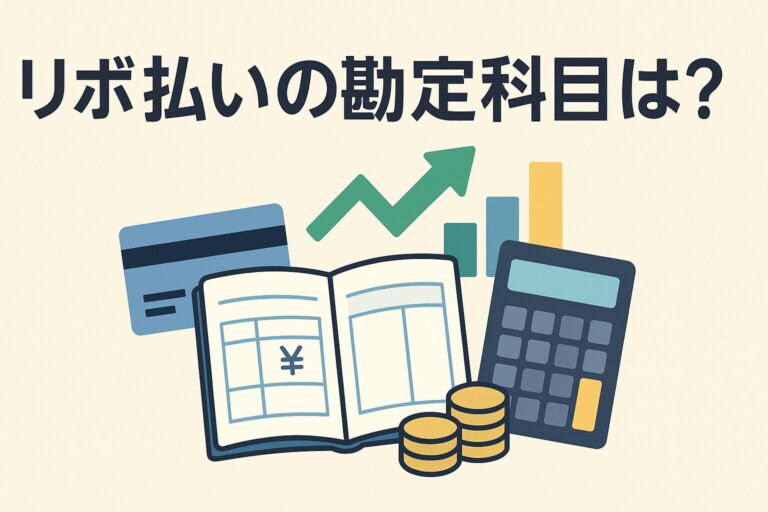個人事業主として事業用の備品などを購入した際、手元の資金繰りを考えてリボ払いを選択する場面もあるかと思います。
しかし、その後の経理処理で、このリボ払いの勘定科目をどうすれば良いのか、また仕訳はどのように行うべきかと手が止まってしまうことはありませんか。
複雑に感じるかもしれませんが、正しい処理方法を一度理解すれば、決して難しいものではありません。
この記事では、リボ払いの会計処理で迷いがちな勘定科目や、具体的な仕訳の方法について、初心者の方にも分かりやすく解説します。
本記事のポイント
- リボ払いの購入時と支払時に使う基本的な勘定科目がわかる
- リボ払いの一連の仕訳方法が理解できる
- リボ払いと分割払いの違いについて確認できる
広告・PR
⚠️ 確定申告の準備はお済みですか?
2月、3月になってから領収書を整理するのはもう終わり!
スマホでスワイプするだけの次世代アプリ「Taxnap」なら、今からでも間に合います。
※副業・フリーランス・個人事業主向け
年払い契約で招待コード【 SC5RJEQK 】
を入力すると1,500円割引で利用できます。
リボ払いの勘定科目
事業を行うために支払った費用であれば、経費として計上することが可能です。
リボ払いで商品やサービスを購入した場合、購入代金の勘定科目は「未払金」を使用して処理するのが基本です。
なぜなら、クレジットカードでの支払いは、購入した時点ではまだ口座からお金が引き落とされていない後払いの取引だからです。
商品やサービスは受け取っているものの、支払いは後日となるため、一時的に「支払う義務」、つまり負債として帳簿に記録しておく必要があります。
これは、一括払いや分割払いでクレジットカードを利用した際と考え方は同じです。
この記事では、青色申告をしている個人事業主やフリーランスの方が、クレジットカードを使用した場合の仕訳例や、仕訳の際に注意すべき内容をまとめています。 青色申告(10万円の特別控除)の仕訳例 &nb[…]
リボ払いの際に毎月発生する手数料は、「支払利息」という勘定科目で処理するのが一般的です。
リボ払いの手数料は、実質的にクレジットカード会社からお金を借りて分割で返済している際の利息と同じ性質を持っています。
そのため、会計上は金融取引における利息と同様に扱い、「支払利息」として費用計上するのが最も適切と考えられています。
「支払手数料」という勘定科目で処理するケースも見られますが、どちらを使用しても税務上の扱いに大きな違いは生じません。
ただし、会計には「継続性の原則」というルールがあるため、一度採用した勘定科目は特別な理由がない限り、その後も継続して使用することが求められます。
どちらにするか迷った場合は、より実態に近い「支払利息」を選択しておくことをお勧めします。
リボ払いの仕訳例
ここでは、リボ払いの一連の流れを具体的な仕訳例でご説明します。
20万円のパソコン(資産計上)をリボ払いで購入し、初回の支払いで元本10,000円と利息1,000円の合計11,000円が口座から引き落とされたケースを想定します。
| タイミング | 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| ① 購入時 | 工具器具備品 200,000 | 未払金 200,000 | パソコン購入 |
| ② 支払時 | 未払金 10,000
支払利息 1,000 |
普通預金 11,000円 | カード代金引き落とし |
① 購入時の処理
まず、パソコンを購入した日に、資産として「工具器具備品」を計上し、同額を負債である「未払金」として貸方に計上します。
② 支払時の処理
次に、口座から代金が引き落とされた日に、カード会社の明細で確認した内訳に基づき仕訳します。
支払った元本分だけ「未払金」を借方に計上して減額し、利息分を「支払利息」として費用計上します。
そして支払った合計額を「普通預金」の減少として貸方に記録します。
この②の処理を、支払いが完了するまで毎月繰り返すことになります。
個人事業主やフリーランスの方が、仕事で使うためにパソコンを購入した場合、経費計上することができます。 ただし、パソコンは購入した年に、全額を経費にできる場合とできない場合とがあります。 &[…]
リボ払い手数料の消費税
リボ払いの手数料(支払利息)には、消費税はかかりません。
利子や保証料、保険料といった金融取引に関する手数料は「非課税取引」と定められています。
参考: 国税庁「No.6201 非課税となる取引」
帳簿付けの際には、リボ払いの手数料を「非課税仕入れ」として処理する必要があります。
会計ソフトを使用している場合は、税区分を選択する項目で「非課税」や「対象外」といった選択肢の中から、自社の運用ルールに沿ったものを継続して使用してください。
この点を誤ると、消費税の納税額計算に影響が出る可能性があるため、正確な処理が求められます。
リボ払いと分割払いの違い
リボ払いと分割払いの会計処理における仕訳の方法は、基本的に同じです。
どちらの支払方法も、「後払いの取引」であり、「手数料(利息)が発生する」という共通点を持っています。
そのため、購入時には「未払金」を計上し、支払時には元本部分で「未払金」を減らし、手数料部分を「支払利息」として費用計上するという一連の流れに違いはありません。
会計処理上の違いではなく、返済方法そのものに違いがあります。
- 分割払い: 購入時に支払回数を決定し、毎月の支払額(元本+手数料)がほぼ一定です。
- リボ払い: あらかじめ設定した一定額を毎月支払います。支払残高に応じて手数料が変動し、支払期間が定まらない場合があります。
まとめ
この記事では、リボ払いの会計処理における勘定科目と仕訳方法について解説しました。
個人事業主や経理初心者の方がつまずきやすいポイントを整理すると、購入時には「未払金」、手数料には「支払利息」という勘定科目を使うのが基本です。
そして、月々の支払い時には、銀行の引き落とし額だけではなく、必ずカード会社の明細で元本と利息の内訳を確認し、分けて記帳することが正確な会計処理の鍵となります。
特に重要なのは、リボ払いの手数料(支払利息)が経費として計上できる点です。
これを忘れずに処理することで、課税所得を圧縮し、適切な節税につながります。
年に一度の確定申告を慌てて行うと、こうした細かい経費計上を見落としがちです。
日々の帳簿付けの段階から、正しいリボ払いの勘定科目を使い、カード明細と突合しながら正確な仕訳を心がけることが大切です。