スマホ会計アプリfinfinの導入を検討しているものの、実際の評判が気になって一歩踏み出せずにいませんか。
日々の経理を手軽に済ませたいフリーランスや個人事業主にとって、会計ソフト選びは非常に大切です。
この記事では、スマホ会計finfinの評判、使い方や料金体系、そして確定申告への対応まで、あなたが知りたい情報を網羅的に解説します。
本記事のポイント
- finfinの具体的な機能と使い方の流れ
- 無料プランと有料プランのサービス内容の違い
- 確定申告への対応力
- 他の会計アプリとの違いを比較
PR
⚠️ 確定申告、まだ終わってない方へ
「何から手をつければいいか分からない…」という方は、安心プランの「丸投げ仕分け」を使うと、仕訳の着手ハードルが下がります。ただし、最終的な経費・プライベート判断は自分で確認が必要なので、まずは無料期間で動作確認してから判断するのが安心です。
3/16まで提出以外の機能は無料で試せます。
スマホ会計FinFinの評判|基本機能から使い方まで
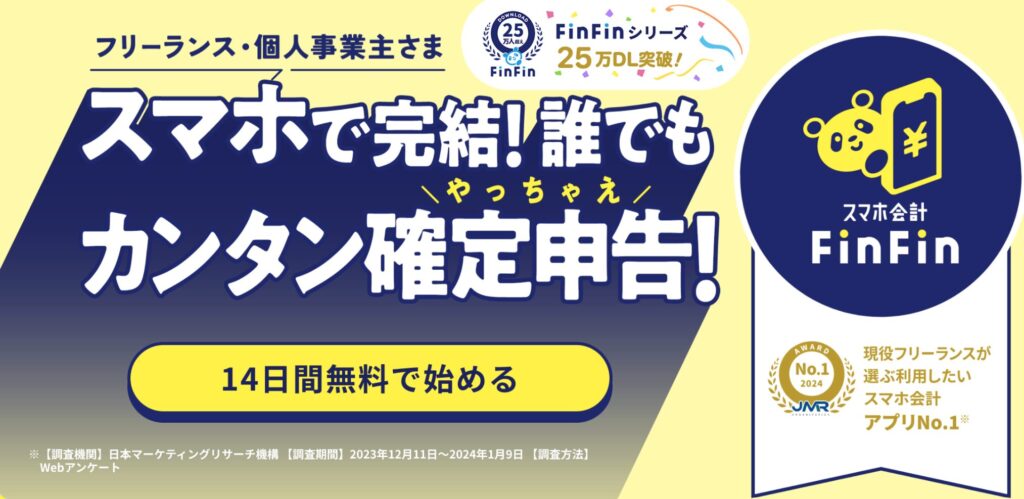
出典:スマホ会計FinFin
ここでは、スマホ会計アプリfinfinの基本的な情報から、具体的な使い方、そしてフリーランスにとって重要な請求書作成や確定申告への対応力までを詳しく解説します。
finfinがどのようなアプリで、日々の経理業務をどれだけ効率化できるのか、その全体像を掴んでいきましょう。
finfinの評判を判断する上で欠かせない、核となる機能をご紹介します。
FinFinとは
フィンフィン(FinFin)とは、ひとことで言えば「スマートフォンだけで経理業務が完結する」ことを目指して開発された会計アプリです。
運営元は、会計ソフト「会計王」シリーズで知られるソリマチグループのフィンテックベンチャー、会計バンク株式会社です。
このアプリの最大の特徴は、多くの会計ソフトがPC利用を前提としている中で、スマホでの操作性を最優先に設計されている点にあります。
そのため、PCを持っていない方や、移動中や休憩時間などのスキマ時間を活用して経理作業を進めたいフリーランス、個人事業主に最適なツールと言えます。
具体的には、日々の取引入力、領収書のデータ化、インボイス制度に対応した請求書作成、そして最終的な確定申告書類の作成から電子申告(e-Tax)まで、一連の会計業務をスマホ一台でこなせる手軽さが魅力です。
事業者モードと副業モードが選択できるため、本業として活動する方はもちろん、副業を始めた会社員の方にもフィットする設計となっています。
\スマホ会計FinFIn公式サイトはこちら/
簡単?スマホ会計finfinの使い方を解説
finfinの使い方は、会計知識がない初心者でも直感的に操作できるよう、非常にシンプルに設計されています。
基本的な流れは、日々の取引を登録し、それを基に確定申告書類を作成するというものです。
アカウント登録から初期設定
まずはアプリをダウンロードし、メールアドレスとパスワードを設定してアカウントを作成します。
その後、事業形態に合わせて「事業者モード」または「かんたん副業モード」を選択します。
ご自身の事業情報を入力すれば、初期設定は完了です。
日々の取引入力方法
取引の入力方法は主に3つあり、状況に応じて使い分けることで効率的に作業を進められます。
- レシート撮影(AI-OCR):手入力の手間が大幅に削減されます。
- 金融機関連携による自動取込:銀行口座やクレジットカードを連携させると、取引明細が自動で取得され、仕訳として取り込まれます。
- 手入力:自動化できない現金取引などは、手入力で登録します。勘定科目も候補から選べるため、簿記の知識がなくても比較的スムーズに入力が可能です。
これらの方法で日々の収支を記録していくだけで、データが自動的に集計され、確定申告の準備が整っていきます。
操作に迷った際は、アプリ内のQ&Aやマニュアルで確認できるため安心です。
請求書と会計の連携機能
finfinは、請求書作成機能と会計機能がシームレスに連携している点が大きな強みです。
これは、フリーランスや個人事業主の業務フローにおいて、非常に効率的な仕組みと言えます。
まず、「スマホインボイスFinFin」という姉妹アプリ、またはfinfin内の機能を利用して、インボイス制度に対応した請求書(適格請求書)を簡単に作成できます。
テンプレートに沿って取引先情報や品目、金額を入力するだけで、制度の要件を満たした請求書が完成します。
作成した請求書は、PDFとしてダウンロードしたり、そのままメールで送付したりすることが可能です。
そして、ここからが重要なポイントです。
この発行した請求書のデータは、自動的に会計機能の「売上」として登録されます。
つまり、請求書を作成するだけで売上の仕訳が完了するため、二重入力の手間が一切かかりません。
この連携機能により、請求業務と会計業務が分断されることなく、一連の流れで処理できます。
売上の計上漏れを防ぐと同時に、経理作業にかかる時間を大幅に短縮できるため、本業に集中したい多忙な方にとって大きなメリットとなるでしょう。
青色申告と確定申告への対応
finfinは、個人事業主の確定申告にもしっかりと対応しています。
日々の取引データを入力していくだけで、確定申告に必要な書類が自動で作成される仕組みです。
確定申告書類の自動作成
finfinに記録された売上や経費のデータをもとに、アプリが自動で集計を行い、「青色申告決算書(または収支内訳書)」と「所得税等申告書」を作成します。
利用者は、アプリ内の質問に答える形で控除情報(医療費控除、ふるさと納税など)を入力していくだけで、複雑な計算をすることなく申告書類を完成させられます。
最近のアップデートでは、マイナポータルと連携することで、源泉徴収票や医療費控除などの情報を自動で取り込む機能も追加され、さらに利便性が向上しました。
e-Taxによる電子申告
作成した確定申告書類は、税務署に足を運んだり、郵送したりすることなく、finfinアプリから直接e-Taxを利用して電子申告が可能です。
マイナンバーカードとスマホさえあれば、自宅からでも申告手続きを完了させられます。
青色申告は、最大65万円の特別控除を受けられるなど節税メリットが大きいですが、複式簿記での記帳が必要なため、初心者にはハードルが高いとされてきました。
しかし、finfinのような会計アプリを利用すれば、日々の取引を入力するだけで複式簿記の帳簿が自動で作成されるため、会計知識に自信がない方でも青色申告のメリットを享受しやすくなります。
finfinの良い評判・メリット
Xなどを見ても、良い評判を多く確認できます。
一例をご紹介します。
確定申告は済ませた?
会計バンクさんの講義を受けてみたら@finfin_app こちら…スマホだけで完結!!
めっちゃ楽~。
今年私は住宅ローンの借り換えもしているから、合わせてサクサク!!
ま、私の場合は特殊ケースで直接来てねって言われているから税務署行かなきゃなのが残念💦#リモラボ— るか|会話で仕事を引き寄せるAI活用デザイナー (@luca__designer) February 19, 2025
これまで医療費や住宅ローン控除の電子申告を
したことはありましたが、個人所得は今回が初めて!フリーランスや副業をスタートしたばかりの方向けの
便利なアプリ(@finfin_app)をセミナーで紹介してもらい、
確定申告のハードルがぐっと下がりました!スマホで完結は助かりますね!✨#リモラボ
— ちはる|図解・スライド制作代行 (@chiharu_online) February 19, 2025
確定申告、今回初めて「スマホ会計Fin Fin」というのを使いました!!(公式 : @finfin_app )
スマホでレシートや領収書を写真撮ると読み込めるし、銀行やカードからの情報取得も可能。情報入力して申告完了までアプリ内でできるので、これのおかげでかなり楽だった…😭😭…— SUZUKA🍺🐶歌酒✈️令和の真尾まお (@nakaharasuzuka) March 3, 2024
その他、利用者のレビューから、特に以下の3点が良い点として多くの方から高く評価されています。
とにかくシンプルで直感的
「会計の知識がなくてもガイドに沿って進めるだけで使えた」「画面がすっきりしていて分かりやすい」といった声が多数見られます。
専門用語が少なく、初心者でも迷いにくい操作性が、特に確定申告が初めての方に支持されています。
スマホだけで確定申告まで完結する手軽さ
レシート撮影から日々の帳簿付け、そして最終的な確定申告書の作成・提出(e-Tax)まで、すべての作業がスマートフォン一台で完結する点が最大の魅力とされています。
PCを持っていない方や、移動中などのスキマ時間を有効活用したいフリーランスにとって非常に便利だという意見が多くあります。
金融機関連携やレシート撮影による自動化
銀行口座やクレジットカードを連携させることで、取引明細が自動で取り込まれ、仕訳の手間が大幅に削減される点を評価する声が目立ちます。
また、レシートをカメラで撮影するだけで経費登録ができる手軽さも、日々の経理作業の負担を軽減しているようです。
finfinの悪い評判・デメリット
一方で、少数ではありますが、Xでネガティブな意見も一部見られました。
スマホの画面で数字の羅列を睨みながら会計の作業なんぞしたくない気がするんだが。RT 時代はクラウド会計からスマホ会計アプリへ! 新サービス、スマホ会計FinFin、スマホインボイスFinFin発表 https://t.co/eVleHDEyRm @PRTIMES_JPより
— tk20130801 (@tk20130801) December 1, 2022
ネット上の評判や口コミも見ると、改善を求める声や利用上の注意点として、以下の点が挙げられています。
AIによる自動仕訳の精度が完璧ではない
レシート撮影(OCR)や金融機関連携による自動仕訳は便利である一方、「日付や金額を読み間違えることがある」「意図しない勘定科目に仕訳される」といった指摘が見られます。
最終的には手動での確認・修正が必要になる場面もあるようです。
機能がシンプルで物足りない場合がある
「使いやすい」というメリットの裏返しとして、事業規模が大きくなったり、より詳細な経営分析を行いたかったりするユーザーからは「機能が物足りない」という意見も出ています。
在庫管理や複雑な経費按分など、高度な会計処理には向いていない可能性があります。
無料プランの機能制限
無料で使い始められる点は魅力的ですが、「無料プランでは請求書の発行枚数やレシート撮影の回数に上限があり、本格的に使うには有料プランが必須」という口コミが見られます。
無料プランは、あくまでお試し用と考えるのが良さそうです。
アプリの動作や一部UIに関する指摘
「アプリの動作が少し重くなる」「日付入力の仕様が毎回手間に感じる」など、アプリのパフォーマンスや細かいユーザーインターフェース(UI)に関する改善を望む声も一部で挙がっています。
こうしたデメリットについては、今後改善される可能性もありますが、現状このような意見があることも念頭に置いて利用を検討することができます。
まずは、無料でお試しができるので、実際に使い勝手を試してみたうえで、継続して利用するかどうかを検討してみて下さい。
\スマホ会計FinFIn公式サイトはこちら/
スマホ会計FinFinの評判を料金や他社比較で検証

ここからは、finfinの評判をより客観的に判断するため、料金プランの詳細や他の会計アプリとの比較に焦点を当てていきます。
どんなに機能が優れていても、コストが見合わなければ継続的な利用は難しいでしょう。
finfinがあなたの事業規模や予算にとって、本当にコストパフォーマンスの高い選択肢なのかを多角的に検証します。
無料プランでどこまでできる?
finfinは、有料プランに移行する前に機能を試せる無料プランが用意されています。
本格的に導入するかどうかを判断するために、無料プランでできることと制限を把握しておくことが大切です。
無料プランの主な機能と制限
無料プランでは、仕訳登録や金融機関連携といった基本的な会計機能は利用できます。
しかし、いくつかの重要な機能に制限が設けられています。
| 機能 | 無料プランでの利用 | 備考 |
|---|---|---|
| 仕訳登録 | 可能 | 件数に制限がかかる場合があります。 |
| 金融機関連携 | 可能 | データの自動取り込みと仕訳ができます。 |
| レシート撮影(OCR) | 可能 | 1日の読み取り枚数に制限があります(例: 1日5枚まで)。 |
| 請求書発行 | 可能 | 月間の発行枚数に制限があります(例: 月10枚まで)。 |
| 確定申告書類 | 作成は可能、提出は不可 | 書類の内容を閲覧することはできますが、e-Taxでの提出はできません。 |
| 消費税申告 | 不可 | – |
無料プランは「会計アプリの操作感を試す」ためのものと考えるのが適切です。
日々の取引件数が少ない副業の初期段階や、取引先が限定的な場合は無料プランでも対応できるかもしれません。
ですが、事業として継続的に活動していく上では、請求書発行枚数や確定申告書の提出機能の制限から、有料プランへの移行が実質的に必要となるでしょう。
料金はいくらですか?
finfinの有料プランは、シンプルな料金体系が特徴です。
ここで注意すべき点は、支払い方法によって料金が異なることです。
Web決済とアプリ決済の違い
結論から言うと、公式サイトから直接申し込む「Web決済」の方が、App StoreやGoogle Playを経由する「アプリ内決済」よりも料金が安く設定されています。
提供される機能は同じなので、少しでもコストを抑えたい場合はWeb決済を選ぶのが賢明です。
具体的な料金プラン
以下に料金の目安をまとめました。
| 決済方法 | 支払いプラン | 料金(税込) | 特徴 |
|---|---|---|---|
| Web決済 | 月払い | ¥840/月 | – |
| Web決済 | 年払い | ¥7,170/年 | 年払いにすると月々あたり約598円となり、月払いよりお得。 |
| アプリ内決済 | 月払い | ¥970/月 | Web決済より割高。 |
| アプリ内決済 | 年払い | ¥8,300/年 | Web決済の年払いと比べると差額が大きい。 |
※上記は2025年7月時点の参考情報です。最新の正確な料金は必ず公式サイトでご確認ください。
これらの料金は、他の主要な会計ソフトと比較しても比較的手頃な価格帯にあります。
特に、スマホだけで経理を完結させたいというニーズに特化している点を考慮すると、コストパフォーマンスは高いと考えられます。
他のスマホ会計アプリとの比較ポイント
会計アプリを選ぶ際には、finfinだけでなく他の選択肢と比較することが不可欠です。
ここでは、主要な会計アプリである「freee会計」や「マネーフォワード クラウド会計」と比較した際のfinfinの特徴を解説します。
finfinの強み
finfinの最大の強みは、徹底的に「スマホ完結」にこだわったシンプルさです。
UI/UXがスマホ操作に最適化されており、PCが苦手な人や、外出先で作業をしたい人にとって、これ以上ない手軽さを提供します。
機能が必要最低限に絞られているため、会計初心者でも迷わず操作しやすい点が魅力です。
freeeやマネーフォワードとの違い
一方、freeeやマネーフォワードは、PCでの利用をメインに据えた高機能なクラウド会計ソフトです。
- 機能の豊富さ: freeeやマネーフォワードは、より詳細な経営分析レポート、部門別会計、API連携によるカスタマイズなど、事業規模の拡大に対応できる豊富な機能を備えています。finfinは、これらの高度な機能は限定的です。
- ターゲットユーザー: freeeやマネーフォワードは、個人事業主から中小企業まで幅広い層をターゲットにしています。対してfinfinは、個人事業主やフリーランス、副業といった「個人のビジネス」に特化しています。
- 料金: 一般的に、freeeやマネーフォワードの本格的なプランは、finfinよりも高額になる傾向があります。
したがって、「多機能で拡張性が高いソフト」を求めるならfreeeやマネーフォワード、「とにかくシンプルで手軽なスマホアプリ」を求めるならfinfin、という棲み分けが考えられます。
競合比較:弥生会計はスマホで使えますか?
会計ソフトの老舗である「弥生」シリーズも、多くの個人事業主に利用されています。
そこで、「弥生会計はスマホで使えるのか?」という点も比較対象として重要になります。
弥生のクラウド版である「やよいの青色申告 オンライン」は、スマホアプリを提供しています。
ただし、その役割はfinfinとは少し異なります。
弥生のスマホアプリの役割
弥生のスマホアプリは、主に「日々の取引入力」や「レシートの取り込み」といった補助的な作業を行うためのものです。
スマホで入力したデータはクラウド上の「やよいの青色申告 オンライン」本体に同期され、最終的な確定申告書の作成や詳細な設定は、PCのブラウザで行うことが前提となっています。
つまり、弥生の場合は「PCでの作業をスマホがサポートする」という位置づけです。
これに対してfinfinは、前述の通り、取引入力から確定申告書の提出まで「全ての工程をスマホだけで完結させる」ことを目指しています。
このため、普段からPCで経理作業を行うことに抵抗がなく、信頼と実績のあるソフトを使いたい方は弥生、PCを開くこと自体が面倒で、すべてをスマホで手軽に終わらせたい方はfinfinが向いていると言えるでしょう。
この記事では、「やよいの青色申告オンライン」の特徴や評判について、また料金や利用の際の注意点などについて分かりやすくご説明しています。 是非最後まで目を通していただいて、利用するかどうかをご検討[…]
スマホで会計ソフトを使うならどれがおすすめ?
最終的に、スマホで会計ソフトを使うならどれがおすすめなのでしょうか。
これは、あなたのビジネスの状況や、会計業務に何を求めるかによって答えが変わります。
シンプルさ・手軽さ最優先なら「finfin」
もしあなたが、「簿記の知識は全くない」「PCは持っていないか、開くのが面倒」「とにかく確定申告を簡単に、スマホだけで済ませたい」というのであれば、finfinは非常に有力な候補となります。
機能が絞られている分、迷うことなく直感的に使えるでしょう。
もし、多少料金は高くなっても、さらに充実した操作性や税務調査に備えた補償を優先させたい場合は、スマホで使えるタックスナップを検討することができます。
予算や会計ソフトに求める機能やサービス内容に基づいて、利用するソフトを検討してみて下さい。
個人事業主やフリーランスにとって、毎年の確定申告は避けて通れない大きな負担です。 日々の経理作業に追われ、本業に集中できないと悩んでいる方も多いのではないでしょうか。 そのような背景から、最近注目を集めているのがタックスナップと[…]
機能性と拡張性を重視するなら「freee」や「マネーフォワード」
一方で、「今後、事業を拡大していく可能性がある」「詳細な経営状況を把握したい」「会計以外の給与計算や請求書管理なども含めて一元管理したい」という場合は、freee会計やマネーフォワード クラウド会計が適しています。
これらのサービスも優れたスマホアプリを提供しており、PCとスマホを併用することで、より高度な経理業務に対応できます。
あなたにとっての最適解を見つけるために
まずは、ご自身の経理スタイルを考えてみましょう。
- 作業場所は?(自宅のPC前、外出先のカフェなど)
- 経理にかけられる時間は?(まとまった時間、スキマ時間)
- 求める機能は?(最低限の帳簿と申告、詳細な分析)
これらの点を踏まえた上で、各サービスの無料トライアル期間などを活用し、実際に操作感を試してみるのが最も確実な方法です。
まとめ:スマホ会計finfinの評判
ここまで、スマホ会計アプリfinfinの評判を、機能、使い方、料金、他社比較といった多角的な視点から検証してきました。
利用者の口コミを総合すると、finfinは「スマホ特化のシンプルさと手軽さ」が高く評価されている一方で、「機能のシンプルさゆえの物足りなさ」を指摘する声もあることが分かります。
これらの情報から導き出される結論は、finfinが「会計初心者で、PCを使わずにスマホだけで経理を完結させたい個人事業主やフリーランス」にとって、非常にコストパフォーマンスの高い優れた選択肢であるということです。
特に、本業が忙しく経理作業に時間をかけたくない方や、確定申告に苦手意識を持つ方にとって、その直感的な操作性は大きな助けとなるでしょう。
ただし、事業規模が大きかったり、詳細な経営分析を求める方には機能が不足する可能性も否めません。
あなたの事業スタイルや求める機能レベルを見極めた上で、この記事で解説したメリット・デメリットを参考に、finfinが最適なパートナーとなり得るかをご判断ください。
まずは無料プランでその手軽さを体験してみることをおすすめします。
\スマホ会計FinFIn公式サイトはこちら/
🔧 当サイト独自の無料診断ツール(個人情報の登録不要)
- 一般家庭の平均と比較して「高い支出」を1分でチェック。勘定科目も表示!(個人事業主・フリーランス向け)
-
🧾 会計ソフト診断あなたの業種・規模に合う会計ソフトを最短で判定









