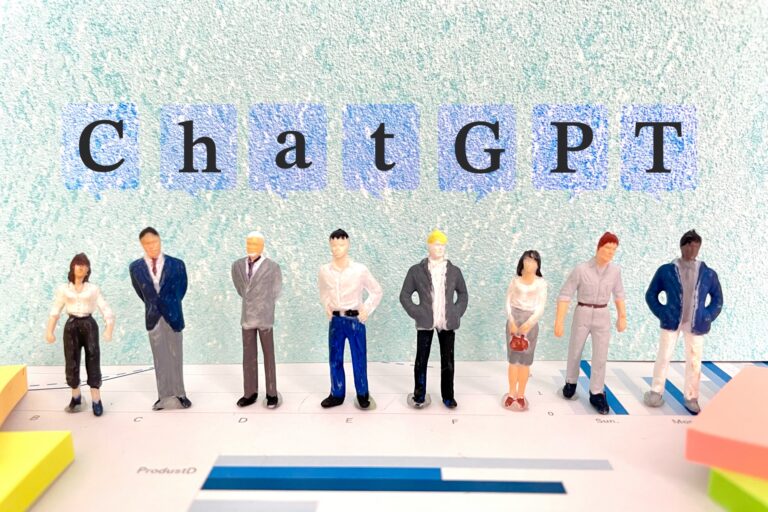ChatGPTは、事業を効率化するための強力なツールとして、個人事業主や法人、フリーランスの間で広く利用されています。
この記事では、ChatGPTを事業で利用する際の経費処理にフォーカスし、勘定科目の選び方や仕訳例をわかりやすく解説します。
また、消費税の適用が始まる2025年以降の対応についても詳しく取り上げています。
ぜひ最後までご覧いただき、日々の会計処理に役立ててください。
2026年1月30日以降、OpenAIが提供するChatGPTの有料プランは、日本の新規ユーザーを対象に円建て・消費税込みの料金表示へと変更されました。
新規契約時の月額料金(税込)
| Plus プラン | 3,000円 |
| Go プラン | 1,400円 |
| Pro プラン | 30,000円 |
これにより、新規ユーザーは為替レートの影響を受けず、毎月の経費金額が固定される形になりました。
一方で、すでにドル建てで契約している既存ユーザーは、ドル建て・為替変動ありの請求が継続されるのか、今回の調整が反映されるのか確認でき次第、記事に反映させる予定です。
⚠️ 経費処理・仕訳時の注意点
- 円建て・税込固定(新規ユーザー): 国内取引に準じたシンプルな処理
- ドル建て・為替換算あり(既存ユーザー): 決済日レートによる換算が必要
※本記事では、上記の両ケースに対応できるよう、勘定科目の考え方や仕訳例を整理しています。
本記事のポイント
- ChatGPTの利用料金を経費計上する際に適切な勘定科目の選び方がわかる。
- ChatGPTを使った場合の具体的な会計処理方法が理解できる。
- 2025年から導入される消費税への対応方法がわかる。
PR
⚠️ 確定申告、まだ終わってない方へ
「何から手をつければいいか分からない…」という方は、タックスナップの「丸投げ仕分け」を使うと、仕訳作業が一気に進みます。私の場合は、未処理だった
667件の取引が約2秒
で仕訳されたので、正直かなりの衝撃でした。ただし、最終的な経費・プライベート判断は自分で確認が必要なので、まずは無料期間で動作確認してから継続利用を判断するのが安心です。
※3/16まで、提出以外の機能は無料で試せます。
ChatGPTの費用は経費計上できる?

事業を行う際にChatGPTを使用する場合は経費計上できます。
なぜなら、経費とは事業を行うために使用した費用のことだからです。
ChatGPTの支払いは経費になるというよりも、自分の事業を行う上で必要な費用だから経費計上できるということです。
例えば、ChatGPTは顧客対応の自動化、データ分析、マーケティングサポートなど、さまざまなビジネスシーンで活用されています。
こうした業務の一部としてChatGPTを利用しているのであれば、その費用は経費として計上できます。
経費計上することで、税金の負担を軽減し、事業運営を効率よく進めることができます。
ChatGPTの勘定科目
ChatGPTの有料プランを契約している場合、使用する勘定科目は通信費や支払手数料です。
ChatGPTに限らず、通常サブスクリプション契約する場合は、上記の勘定科目を使って会計処理を行うケースが大半です。
ただし、具体的にどの勘定科目を選ぶかは、ChatGPTの利用目的や業務内容に応じて決定することが重要です。
例えば、ChatGPTを使用する用途によっては「ソフトウェア使用料」、「業務委託費」、「ITサービス費」、「研究開発費」などの勘定科目で計上することも考えられます。
ですが、小規模な事業を営んでいる個人事業主やフリーランスであれば、基本的には「通信費」や「支払手数料」などの勘定科目で仕訳を行えば問題ありません。
どうしても気になる場合は、税理士などの専門家に相談することも検討できますが、注意が必要なのは、どの勘定科目を使用するかよりも正しい金額で経費処理することです。
ChatGPTは、2024年12月5日から月額料金200ドルのプランが利用可能となりました。
そのため、利用するプランに応じて正しい金額を経費計上する必要があります。
以下では、主な料金プランと利用可能なサービス内容をまとめています。
| プラン | 料金 | 主な特徴 |
| 無料プラン (Free Plan) | 0円 | 基本機能を利用可能、混雑時は制限の可能性 |
| ChatGPT Plusプラン ($20プラン) | 月額約3,000円 | 優先的なアクセス、応答速度向上、高度な問題解決能力 |
| ChatGPT Proプラン ($200プラン) | 月額約30,000円 | ・GPT-4oおよびo1への無制限アクセス ・高度な音声機能への無制限アクセス |
注意が必要なのは、ChatGPTの利用料金は、為替レートによって変動することです。
ChatGPTの有料プランは、月額料金20ドルもしくは200ドルで利用することができますが、実際に事業用の預金口座から引き落とされるときの金額は、毎月異なる可能性が高いです。
そのため、利用しているクレジットカードの明細等で、毎月金額をしっかりチェックして会計処理を行いましょう。
2025年からChatGPTの料金に消費税が導入される
OpenAIは2025年1月1日から、日本国内の利用者に対して10%の消費税を適用し、適格請求書(インボイス)を発行します。
概要と重要なポイント
1. 消費税導入の背景
- OpenAI LLCは日本の消費税法に基づき、日本国内のデジタルサービス利用者に対して10%の消費税を徴収します。
- デジタルサービスのクロスボーダー取引が対象となる規則の一環です。
2. 実施開始日
- 2025年1月1日以降に発生するすべての利用料金に消費税が適用されます。(※2024年までの料金には消費税はかかりません)
3. 適格請求書の発行
- OpenAI LLCは日本の適格請求書発行事業者として登録されます。
- 日本国内の事業者に対して提供される請求書には、適格請求書制度の要件を満たす以下の内容が含まれます。
- 請求書発行事業者の氏名または名称、および登録番号
- 取引内容(サービスの種類など)
- 取引日
- 取引金額(税込価格)
- 消費税額
- 日本円での消費税額が明記されるため、税務申告に利用可能です。
適格請求書のメリット
1. 消費税控除のための要件を満たす
- 適格請求書制度に基づき、消費税の仕入控除を受けるためには、適格請求書の保存が必須です。
- OpenAIが提供する請求書は、正確な経費処理をサポートします。
2. 確実な記録と管理が可能
- 消費税額が日本円で明記されるため、円建ての税額計算が容易になります。
- フリーランスや法人の事業者にとって、正確な税務処理が促進されます。
具体的な影響
- サービス利用料が、ChatGPT Plusプランの場合だと、月額約3,000円($20)の場合、税込価格で約3,300円になります。
- 適格請求書を通じて、消費税の仕入控除が適用可能です。
2025年以降に、仕入税額控除を受ける事業者は、消費税も考慮した会計処理が必要となります。
参照:OpenAI
ChatGPTの仕訳例
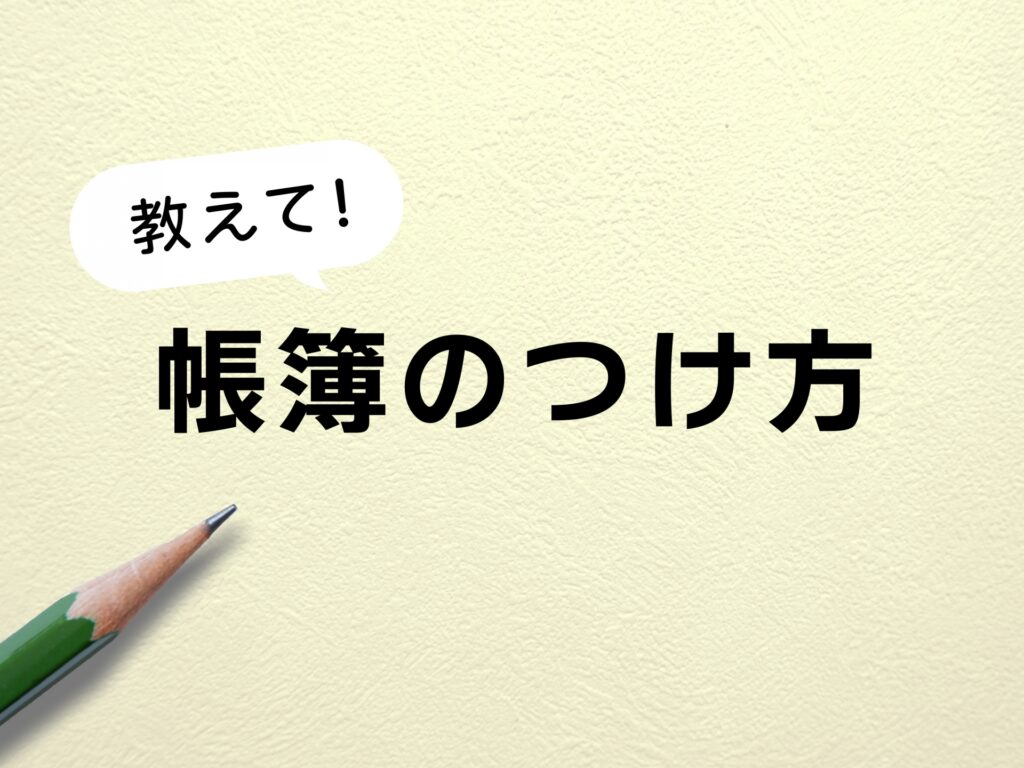
ChatGPTの仕訳例については、実際に私の明細に基づいた利用日や利用金額をもとに作成しました。
なお、決済方法はクレジットカードで、事業用の口座から引き落としが行われています。
- 利用日・・2023年4月25日
- 利用金額・・2,755円(換算レート:1ドル137.75円)
- 支払日・・2023年5月29日
| 日付 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 4月25日 | 通信費 | 2,755 | 未払金 | 2,755 |
| 5月29日 | 未払金 | 2,755 | 普通預金 | 2,755 |
参考記事:未払金の勘定科目と仕訳例
ちなみに、1年後のChatGPT利用料金は以下のようになっていました。
- 利用日・・2024年4月25日
- 利用金額・・3,169円(換算レート:1ドル158.465円)
月額料金20ドルは変わっていませんが、この1年で円安が進んだこともあり、利用金額は400円以上高くなっています。
このように、引き落とされるときの金額は、為替レートの関係で異なりますので、毎月の利用料金はきちんと確認するようにして下さい。
2025年から消費税を含んだ金額が請求されることになりますが、免税事業者であれば税込金額で会計処理すればOKです。
課税事業者の方で、利用料金と消費税を分けて仕訳する場合は、仮払消費税の勘定科目を使用します。
例えば、以下のような条件の場合、次のように仕訳します。
- 利用日・・2025年4月25日
- 利用金額・・3,000円(換算レート:1ドル150円)
- 支払日・・2025年5月29日
| 日付 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 4月25日 | 通信費 | 3,000 | 未払金 | 3,300 |
| 仮払消費税 | 300 | |||
| 5月29日 | 未払金 | 3,300 | 普通預金 | 3,300 |
参考記事:消費税の勘定科目と仕訳例
また、クレジットカード決済の場合、事業とは関係のないプライベート分が含まれていることもあります。
事業とは関係のない支払いについては、事業主貸の勘定科目で処理をおこなうことも重要です。
例えば、以下のような条件の場合は次のように仕訳します。
- クレジット引き落とし金額8,800円
- ChatGPT料金3,300円
- プライベート利用分5,500円
| 日付 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 利用日 | 通信費 | 3,000 | 未払金 | 3,300 |
| 仮払消費税 | 300 | |||
| 引き落とし日 | 未払金 | 3,300 | 普通預金 | 8,800 |
| 事業主貸 | 5,500 |
※2026年からの新料金(円建て)による仕訳例
2026年1月30日以降に新しくChatGPT Plusに加入した方の料金は、月額3,000円(税込)の固定となりました。
これまでは「20ドル」という外貨建てだったため、毎月カード明細が出るまで正確な日本円の金額が分かりませんでしたが、円建て対応により、家計簿や会計ソフトへの入力が非常にシンプルになっています。
【仕訳例】免税事業者の場合(税込経理)
- 利用日:2026年1月30日 / 利用金額:3,000円(税込固定)
- 支払日:2026年2月27日
| 日付 | 借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1/30 | 通信費 | 3,000 | 未払金 | 3,000 |
| 2/27 | 未払金 | 3,000 | 普通預金 | 3,000 |
【仕訳例】課税事業者の場合(税抜経理)
| 日付 | 借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1/30 | 通信費 | 2,727 | 未払金 | 3,000 |
| 仮払消費税 | 273 |
このように、円建てユーザーは為替レートを確認して計算する手間がなくなりました。ただし、以前から継続してドル建てで支払っている方は、引き続きその時々のレートでの処理が必要ですので、自身の請求画面が「3,000円」か「20ドル」かを確認するようにしましょう。
まとめ
今回は、ChatGPTを経費計上する際の勘定科目と仕訳例について取り上げました。
ChatGPTのようなサブスク契約の場合、基本的には通信費か支払手数料の勘定科目を使用します。
どちらを使うにしても、一度使用した勘定科目は、正当な理由がない限り継続して使用するようにしましょう。
また、ChatGPTの費用は、為替レートの変動により金額が変わりますので、クレジットカードの明細等で確認するようにして下さい。
🔧 当サイト独自の無料診断ツール(個人情報の登録不要)
- 一般家庭の平均と比較して「高い支出」を1分でチェック。勘定科目も表示!(個人事業主・フリーランス向け)
-
🧾 会計ソフト診断あなたの業種・規模に合う会計ソフトを最短で判定