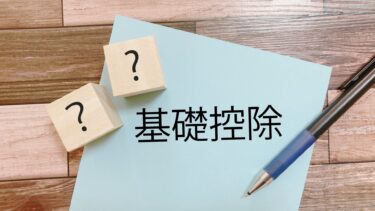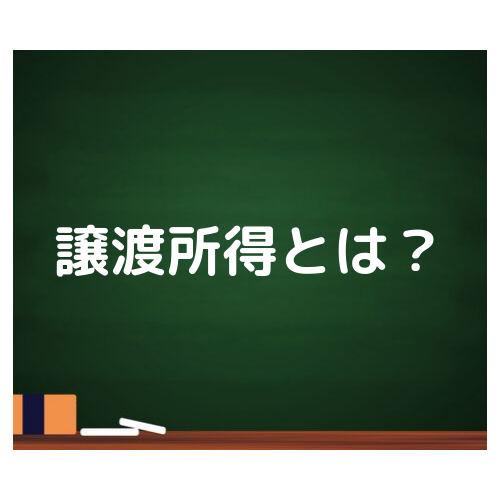利子所得は、日常生活でなじみ深い「預貯金の利子」だけでなく、合同運用信託や公社債投資信託の分配金など、さまざまな収益が含まれる点が特徴です。
これらの所得は、通常、税額が源泉徴収されるため確定申告が不要です。
しかし、中には確定申告が必要となるケースもあります。
本記事では、利子所得の具体例や課税方式、注意点を詳しく解説していますので、ぜひ参考にして下さい。
PR
⚠️ 確定申告、まだ終わってない方へ
「何から手をつければいいか分からない…」という方は、安心プランの「丸投げ仕分け」を使うと、仕訳の着手ハードルが下がります。ただし、最終的な経費・プライベート判断は自分で確認が必要なので、まずは無料期間で動作確認してから判断するのが安心です。
3/16まで提出以外の機能は無料で試せます。
利子所得とは
利子所得とは、公社債及び預貯金の利子(公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。)並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配(以下この条において「利子等」という。)に係る所得をいう。
利子所得とは、所得税法23条1項に定められている通り、下記の利子や収益の分配などが含まれます。
- 預貯金の利子
- 公社債の利子
- 合同運用信託の収益の分配
- 公社債投資信託の収益の分配
- 公募公社債等運用投資信託の収益の分配
「利子所得=預貯金の利子」のイメージが強いと思いますが、それ以外にも利子所得に含まれるものが、意外に多くあります。
大半の方に関係するのは預貯金の利子だと思います。
税金の計算
「収入金額=利子所得」です。
通常であれば、収入から必要経費を差し引いた金額が所得となります。
例えば、事業所得であれば、売上から必要経費を差し引いたものが所得です。
給与所得の場合は、収入金額から給与所得控除を差し引いたものが所得となります。
しかし、利子所得については、収入金額が、そのまま利子所得となります。
利子所得については、収入を得るための経費がかかっていないからです。
課税方式
利子所得の課税方式は、源泉分離課税です。
所得税が15.315%(復興特別所得税0.315%を含む)で住民税が5%かかることになります。
源泉分離課税の場合は、源泉徴収の対象となるため、確定申告の必要はありません。
通帳などに振り込まれている利子については、上記の所得税と住民税をあわせた金額(20.315%)が差し引かれて振り込まれます。
銀行側が税金を計算してくれて、その差額分を振り込んでくれている形になりますので申告は不要です。
利子所得の注意点
日本国外の銀行に預けている場合
利子所得は、基本的には源泉分離課税となりますので確定申告は不要です。
しかし、源泉分離課税とはならないケースがありますので注意が必要です。
例えば、日本国外の銀行に預金をしていて、その預金に対して利子がつくようなケースです。
この場合は、源泉分離課税ではなく、総合課税の対象となります。
源泉徴収されず、確定申告の対象となりますので注意が必要です。
お金を貸し付けた場合
これまで、ご説明してきたとおり、銀行などにお金を預けて、そのお金に対して利子が付く場合には、利子所得となります。
ところが、利子や利息でも、お金を貸し付けた際に得られるものに関しては、利子所得とはみなされず、事業所得や雑所得として処理する必要があります。
金銭の貸付が、事業として行われている場合は事業所得になります。
例えば、個人事業主が取引先に対して、お金を貸し付けて得られる利息などが当てはまります。
金銭の貸付が、事業以外で行われる場合は、雑所得として処理することになります。
例えば、友人や知人に個人的に貸し付けたお金から得られる利息などです。
公社債について
特定公社債
特定公社債とは、下記のようなものを言います。
- 国債
- 地方債
- 外国国債
- 外国地方債
- 公募公社債
- 上場公社債
これらの、特定公社債から得られる利子などは、源泉分離課税ではなく、申告分離課税となります。
源泉分離課税については、確定申告は不要です。
しかし、申告分離課税については、確定申告によって納付することになります。
ただし、確定申告不要の選択をすることも可能ですので、必ず確定申告をしないといけない訳ではありません。
一般公社債
特定公社債以外の公社債のことを言います。私募債などが当てはまります。
私募債とは、一般に募集される公募債などとは違って、少数の投資家にのみ発行される債券を言います。
この、一般公社債に該当する利子に関しては、源泉分離課税となり確定申告は不要です。
ただし、同族会社が発行する社債の利子で、その同族会社の株主がその支払を受ける場合は、総合課税の対象となりますのでご注意下さい。
まとめ
利子所得とは、所得税法23条1項に定められている、利子や収益の分配です。
源泉分離課税となるため、基本的には確定申告は不要です。
ただし、利子や利息といっても、総合課税となるケースや、事業所得及び雑所得として処理する必要のあるケースがあります。
その場合は、確定申告が必要となりますのでご注意下さい。
🔧 当サイト独自の無料診断ツール(個人情報の登録不要)
- 一般家庭の平均と比較して「高い支出」を1分でチェック。勘定科目も表示!(個人事業主・フリーランス向け)
-
🧾 会計ソフト診断あなたの業種・規模に合う会計ソフトを最短で判定