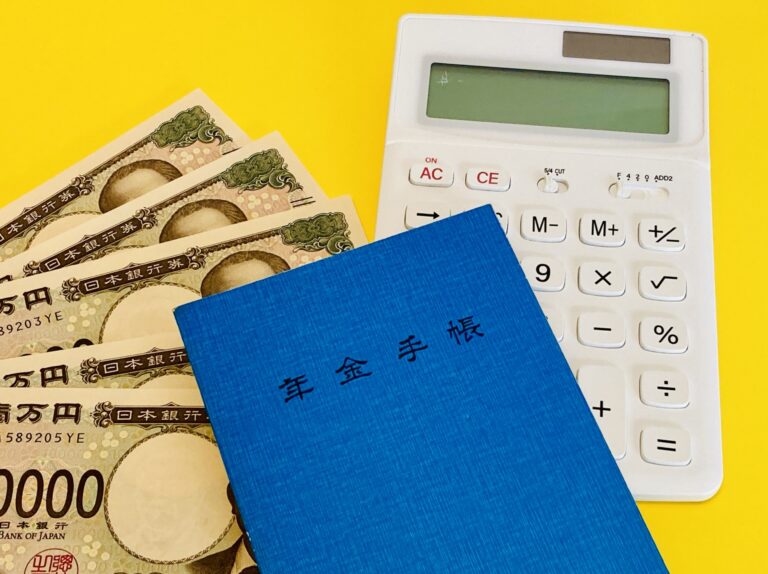国民年金の2年前納を継続してきた人にとって、一度に約40万円という大きな金額を今後も支払い続けることに躊躇するかもしれません。
特に個人事業主やフリーランスとして働いていると、収入が不安定になりがちなため、次回の引き落としを避けたいと考えるのは自然なことです。
また、これから就職する学生の方なども、手続きの停止方法について知りたいかもしれません。
この記事では、2年前納をやめるための具体的な手続き方法や、停止するかの判断材料について詳しく解説します。
本記事のポイント
- 2年前納の自動更新を停止する具体的な方法
- 手続きの期限や必要な書類
- 就職や状況変化でやめたい場合の対処法
- 2年前納を継続するメリットとデメリットの比較
ファイナンシャルプランナー2級・AFP、日商簿記2級、行政書士の資格保有者の個人事業主。詳細は運営者情報をご覧ください。
PR
⚠️ 確定申告、まだ終わってない方へ
確定申告がまだ終わっていない方は、まず仕訳を片付けると一気に気持ちがラクになります。特にタックスナップの「丸投げ仕分け」は、迷いがちな仕訳作業を一気に進められる機能です。
私の場合は、 667件の取引が約2秒 で仕訳されました。ただし端末や通信状況などにより、処理の時間は異なる可能性があります。
3/16までは提出・印刷以外を無料で試せます。無料のうちに使ってみて、合うかどうかを確認してみてください。
※仕訳後に、勘定科目や金額は念のため確認しておくと安心です。
※3/16まで、提出以外の機能は無料で試せます。
クーポンは、初回登録時に入力しておくとスムーズです。合わなければ無料期間中に解約できます。
▶ 無料でタックスナップを試してみる(3/16まで) ※「丸投げ仕分け」の詳細や体験談を確認できる記事はこちら国民年金の2年前納をやめるための手続き

国民年金の2年前納を停止したいと考えたとき、具体的に何をすればよいのでしょうか。
このセクションでは、「2年前納をやめる」のに、必要な手続きを詳しく解説します。
特に見落としがちな口座振替の自動更新を停止する方法や、クレジットカード払いの場合の手続き、就職が決まった際の対処法など、状況に応じた「やり方」を具体的に紹介していきます。
手続きの期限もあわせて確認しましょう。
口座振替の自動更新を止めるやり方
口座振替による2年前納は、一度申し込むと、辞退の申出がない限り自動的に継続される仕組みになっています。
そのため、次回の2年前納の引き落としを止めたい場合は、「国民年金保険料口座振替辞退申出書」という書類を提出する必要があります。
「次回はまとまった金額の支払いを避けたい」と考えている場合、この手続きが不可欠です。
体験談などで「口座の残高を不足させておけば自動的に月払いに切り替わる」といった情報を見かけることがありますが、この方法は確実ではありません。
日本年金機構によると、残高不足で前納分の振替ができなかった場合、その年度は割引のない翌月末振替となり、翌年の4月に再び2年前納の振替が試みられる可能性があります。
意図せず未納期間が発生したり、混乱を招いたりする原因にもなりかねないため、必ず正式な辞退手続きを行いましょう。
手続きは、お近くの年金事務所の窓口、または郵送で受け付けています。振替口座のある金融機関の窓口でも提出可能です。
また、マイナポータル経由で「ねんきんネット」にログインし、オンラインで辞退の申出をすることもできます。
参考:日本年金機構|国民年金保険料の支払いを口座振替にするとき(やめるとき)、振替口座を変更するとき
2年前納の引き落とし日と停止期限
次回の引き落としを確実に停止するためには、手続きの期限を守ることが大切です。
口座振替による2年前納(4月分から翌々年3月分まで)の保険料が実際に引き落とされるのは、原則として「4月末日」です。(※末日が金融機関の休業日の場合は翌営業日)
そして、この4月末の引き落としを停止するための「国民年金保険料口座振替辞退申出書」の提出期限は、「2月末日」(必着)となっています。
この期限は、日本年金機構が金融機関への振替データを作成するスケジュールに基づいています。
2月末日までに申出書が受理されないと、辞退の手続きが間に合わず、4月末に2年分の保険料が引き落とされてしまう可能性があります。
郵送で提出する場合は、郵便物の到着までに日数がかかることを考慮し、余裕を持って投函するようにしてください。
参考:日本年金機構|口座振替でのお支払い
クレジットカード納付への変更方法
2年前納のまとまった支出は避けたいものの、今後も納付忘れを防ぎたい、あるいは少しでも割引を受けたいという理由から、クレジットカードでの月払いや6カ月前納などに変更したい方もいるかと思います。
この場合、前述の「口座振替辞退申出書」の提出とあわせて、新たに「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」を提出します。
この申出書で、今後の納付方法として「毎月納付(翌月末立替)」「6カ月前納」「1年前納」から選択できます。
クレジットカードで前納する場合も割引が適用されます。
なお、納付額に応じたカード会社のポイントについては、公金決済をポイント付与の対象外または減額対象としているカード会社もあるため、ご利用のカード会社の規約を事前にご確認ください。
クレジットカードによる納付も、一度申し込むと辞退の申出がない限り自動的に継続されます。
もし将来的にクレジットカード納付自体をやめたい場合や、別のカードに変更したい場合は、再度「申出書」の提出が必要になる点を覚えておきましょう。
就職した場合の口座振替停止手続き
個人事業主や学生の方が就職し、会社で厚生年金に加入した場合、国民年金の第1号被保険者から第2号被保険者へと資格が切り替わります。
この切り替え手続きは勤務先が行うため、ご自身で国民年金をやめる手続きを行う必要は原則ありません。
参考:日本年金機構|就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き
ただし、注意点があります。
勤務先での手続きから日本年金機構でのデータ反映までに、1〜2カ月程度のタイムラグが生じることがあります。
もし、このデータ反映が完了する前に2年前納の引き落とし日(4月末)を迎えてしまうと、厚生年金に加入しているにもかかわらず、2年分の国民年金保険料が一度引き落とされてしまうケースがあり得ます。
もちろん、払い過ぎた保険料は、後日、日本年金機構から「国民年金保険料還付請求書」が送付され、手続きを行うことで返金(還付)されます。
とはいえ、一時的であっても大きな金額が引き落とされる事態を避けたい場合は、就職が決まった時点で、ご自身で「国民年金保険料口座振替辞退申出書」を早めに提出しておくことをお勧めします。
2年前納は途中からでもできる?
国民年金の2年前納は、必ずしも4月からスタートする必要はなく、年度の途中から申し込むことも可能です。
申込みのタイミングによって、いつから前納が開始されるかが決まります。
例えば、口座振替で従来の「2年前納」区分を選択し、初回振替日が7月末日になったケースを考えます。
この場合、7月分から翌々年の3月分までの21カ月分の保険料が、7月末日に一括で振り替えられます。
この場合も、月数に応じた前納の割引が適用されます。
このように、申込み時期に応じて前納できる月数が変わる仕組みになっています。
途中でやめたい場合
「国民年金を途中でやめたい」というご相談には、いくつかの異なる状況が考えられます。
2年前納という「支払い方法」
前述の通り、「国民年金保険料口座振替辞退申出書」を提出することで、2年前納の自動継続を停止できます。
これにより、次回の引き落としは行われず、ご自身で納付書払い(月払い)に切り替えるか、別途「クレジットカード納付申出書」や「口座振替申出書(月払いや6カ月前納などを選択)」を提出して、納付方法を変更します。
就職や結婚(配偶者の扶養に入る)
こちらも前述の通り、就職して厚生年金に加入する(第2号被保険者になる)場合や、配偶者の扶養に入って第3号被保険者になる場合は、ご自身での「やめる」手続きは原則不要です。
新しい勤務先や配偶者の勤務先を通じて、必要な手続きが行われます。
国民年金制度そのものから脱退したい
日本国内に居住する20歳以上60歳未満の方は、国民年金への加入が法律上の義務となっています。
そのため、上記のような理由(第2号・第3号への変更)や、海外へ転出する場合などを除き、個人の意思で国民年金制度から脱退することはできません。
国民年金の2年前納をやめるかの判断材料

2年前納をやめる手続きは分かりましたが、本当にやめてしまってよいか迷う方もいるかもしれません。
2年前納には大きな割引というメリットもあるため、資金繰りとのバランスが悩みどころです。
このセクションでは、国民年金の2年前納をやめるかどうかを冷静に判断するための材料を提供します。
メリットとデメリットの比較、税金や確定申告への影響、学生や未納の場合のリスクなど、多角的に検討します。
2年前納のメリットと割引額
2年前納の最大のメリットは、保険料が大幅に割引される点にあります。
令和7年度・8年度分の2年間(24カ月分)を例にとると、割引額は以下のようになります。
| 納付方法 | 2年間の保険料(本来額) | 2年前納額 | 割引額 |
|---|---|---|---|
| 口座振替 | 425,160円 | 408,150円 | 17,010円 |
| 現金・クレジットカード | 425,160円 | 409,490円 | 15,670円 |
※令和7年度保険料(17,510円)と令和8年度保険料(17,920円)に基づく計算
口座振替を利用した場合、毎月納付するよりも2年間で17,010円もお得になります。
これは現在の低金利時代において、非常に有利な「運用」と捉えることも可能です。
また、一度の手続きで2年分の納付が完了するため、「納付忘れ」のリスクを完全に防げるという管理上のメリットもあります。
参考:日本年金機構|国民年金保険料の「2年前納」制度
2年前納するデメリット
一方で、2年前納にはデメリットも存在し、これらが「やめたい」と考える直接的な理由となります。
まとまった資金が必要になる
最大のデメリットは、一度に大きな資金(令和7年度で約41万円)が拘束されることです。
特に収入が不安定になりがちな個人事業主やフリーランスの方にとって、この一括支出はキャッシュフローを大きく圧迫する要因になり得ます。
状況変化に対応しづらい
2年分を前納した後に、失業や事業不振などで収入が大幅に減少し、保険料の「免除」や「納付猶予」を申請したい状況になったとします。
この場合、すでに納付済みの期間については、免除や猶予の申請を遡って適用することはできません。
ただし、前述の通り、就職や扶養に入るなどで国民年金の資格自体が変わった場合は、重複して納付した分の保険料は還付されます。
申込期限が厳格
2年前納を利用するには、事前の申込みが必要です。
特に重要な期限は以下の通りです。
- 口座振替・クレジットカードの場合: 毎年2月末日
- 現金(納付書)の場合: 毎年3月末日
これらの期限までに申込みを行う必要があります。
2年前納(4月開始)との違い
令和7年1月から、口座振替による2年前納の申込み方法に、従来の「2年前納」に加えて「2年前納(4月開始)」という選択肢が追加されました。
この2つの違いは、いつから前納がスタートするかにあります。
2年前納(4月開始):「直近の4月から」2年分(24カ月分)の前納を開始したい場合に選択します。
この方法で4月末の振替に間に合わせるには、2月末までに申出書を提出する必要があります。
もし申込みが遅れ、初回振替が5月以降になった場合、その年度は割引のない月払いとなり、2年前納が開始されるのは「翌年度の4月末」からとなります。
従来の「2年前納」:申込み後の最短の振替日から、「翌々年の3月まで」の保険料(13カ月~最大24カ月分)を一括で前納します。
年度の途中からでも、すぐに前納(割引あり)を開始したい場合に適しています。
学生納付特例と2年前納の関係
学生の方に関連する情報としては、学生納付特例制度との関係が挙げられます。
「学生納付特例制度」は、所得が一定以下の学生の国民年金保険料の納付を「猶予」する制度です。
この特例の承認を受けている期間は、保険料の納付が猶予されるため、そもそも保険料を支払う必要がありません。
参考:日本年金機構|国民年金保険料の学生納付特例制度
したがって、学生納付特例を受けている期間中は、2年前納を申し込むことはできません。
もし、以前に2年前納を申し込んでいた方が、新年度から学生納付特例を申請し承認された場合、前納した保険料のうち、特例の承認期間と重複する分の保険料は、後日還付(返金)されます。
逆に、学生であっても所得が基準以上ある場合や、将来の年金額を満額に近づけるために任意で納付する場合は、学生納付特例を申請せずに2年前納を利用し、割引を受けることが可能です。
年金未納が及ぼす悪影響
ここで非常に大切な点を確認します。
「2年前納をやめる」ことは、保険料の納付を「未納にする(払わない)」こととは全く意味が異なります。
2年前納をやめた場合は、必ず「月払い」や「6カ月前納」など、他の方法で納付を継続しなければなりません。
もし保険料を納付せず、未納の期間が2年間発生してしまうと、将来に対して深刻な影響が及びかねません。
将来の老齢基礎年金が減額される
老齢基礎年金は、保険料を40年間(480カ月)すべて納付することで満額が受け取れます。
未納期間が24カ月あれば、その分だけ将来受け取る年金額が生涯にわたって減額されます。
障害年金や遺族年金が受給できない可能性
国民年金は、老後のためだけのものではありません。
万が一、病気やケガで障害が残った場合に支給される「障害基礎年金」や、一家の支え手が亡くなった際に家族に支給される「遺族基礎年金」も、国民年金の重要な保障です。
これらの年金は、保険料の納付要件を満たしていないと、たとえ障害状態や死亡という事態が発生しても、受給することができません。
経済的な理由で納付が困難な場合は、未納のまま放置せず、必ずお住まいの市区町村役場や年金事務所で「保険料免除・納付猶予制度」の相談をしてください。
個人事業主として独立すると、会社員時代とは異なり、年金の支払いを自分自身で管理する必要があります。 その中で、「年金払わないとどうなるのだろうか」という疑問や、収入が不安定な時期には「保険料の支払いが苦しい」といった悩みに直面[…]
2年前納の確定申告
個人事業主にとって、2年前納は税金面でも考慮すべき点があります。
2年分前納で支払った保険料は、全額が「社会保険料控除」の対象となり、所得税や住民税の計算のもととなる所得金額から差し引くことができます。
控除の方法は、以下の2つからご自身で選択が可能です。
- 支払った年に、2年分の全額を控除する
- 各年分(1年目、2年目)に相当する額を、それぞれの年で1年分ずつ控除する
例えば、今年の所得が非常に多く、翌年の所得は減る見込みがある場合、1.の方法を選んで2年分を今年の控除に充てた方が、節税効果が大きくなる可能性があります。
ご自身の所得の見通しに合わせて、有利な方を選択できます。
参考:国税庁|No.1130 社会保険料控除
この記事では、個人事業主に関係する社会保険料控除の種類や書き方、お得な節税の方法についてご説明しています。 本来差し引くことができるものを知らずにいるなら、税金を余計に支払うことになり損をしてしまいます。 ぜひ最後までご覧下さい[…]
まとめ
この記事では、国民年金の2年前納をやめることを検討している方に向けて、その具体的な手続き方法と、やめるかどうかの判断材料について解説しました。
次回のまとまった支出を避けたい場合、最も重要な手続きは「国民年金保険料口座振替辞退申出書」を提出し、自動更新を停止することです。
特に口座振替を利用している方は、2月末日という提出期限を厳守する必要があります。
就職などで厚生年金に切り替わる方も、一時的な二重払いを防ぐために、早めに辞退届を出しておくと安心です。
一方で、2年前納には口座振替で約17,000円という大きな割引メリットがあるのも事実です。
この割引を放棄して手元のキャッシュフローを優先するか、資金を工面して将来の割引メリットを取るかは、ご自身の経済状況次第と言えます。
「2年前納をやめる」ことは、決して「未納にする」ことではありません。
やめた後は、月払いや6カ月前納など、ご自身に合った方法で納付を確実に継続することが求められます。
もし、経済的に支払いが困難な場合は、未納のまま放置せず、必ず免除や猶予の制度を活用してください。