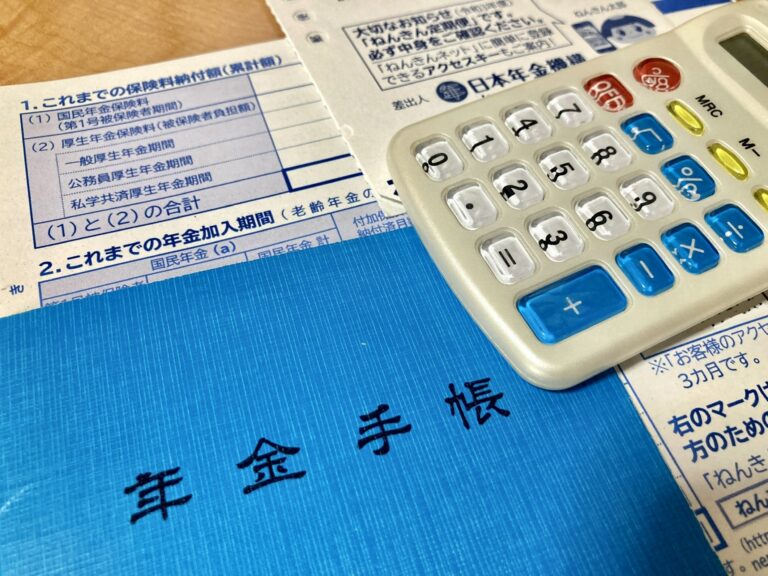「ねんきん定期便」を見て、思ったより将来の年金額が少なく、漠然とした不安を感じていませんか?
特に、過去に国民年金の保険料を払っていなかった期間があると、「あの時の分を今から払うべきか…」と迷う方も多いと思います。
この記事では、国民年金の追納が持つ具体的なメリットと、同時に知っておくべきデメリットや注意点について、専門用語を避け、分かりやすく徹底解説します。
- 追納によって将来の年金が具体的にいくら増えるか
- 追納が持つ「節税(所得控除)」という大きな効果
- 追納を「すべき人」と「しない方がいい人」の特徴
- 追納の手続き方法と「10年」という期限の重要性
ファイナンシャルプランナー2級・AFP、日商簿記2級、行政書士(未登録)の資格保有者の個人事業主。詳細は運営者情報をご覧ください。
PR
⚠️ 確定申告、まだ終わってない方へ
確定申告がまだ終わっていない方は、まず仕訳を片付けると一気に気持ちがラクになります。特にタックスナップの「丸投げ仕分け」は、迷いがちな仕訳作業を一気に進められる機能です。
私の場合は、 667件の取引が約2秒 で仕訳されました。ただし端末や通信状況などにより、処理の時間は異なる可能性があります。
3/16までは提出・印刷以外を無料で試せます。無料のうちに使ってみて、合うかどうかを確認してみてください。
※仕訳後に、勘定科目や金額は念のため確認しておくと安心です。
※3/16まで、提出以外の機能は無料で試せます。
クーポンは、初回登録時に入力しておくとスムーズです。合わなければ無料期間中に解約できます。
▶ 無料でタックスナップを試してみる(3/16まで) ※「丸投げ仕分け」の詳細や体験談を確認できる記事はこちら国民年金|追納のメリットとデメリット

ここでは、国民年金の追納が持つ二大メリットである「年金額の増加」と「節税効果」について具体的に解説します。
また、メリットだけでなく、追納しない方が良いケースや知っておくべきデメリットについても触れ、ご自身にとって追納が本当にお得なのかを判断する材料を提供します。
年金追納のメリット
国民年金の追納には、大きく分けて2つの強力なメリットが存在します。
第一に、将来受け取る老齢基礎年金の金額を増やすことができます。
これは、老後の生活を支える終身年金を満額に近づけられる、という点で非常に大きな安心材料となります。
日本年金機構によれば、例えば1年間分(12ヶ月)の保険料を追納した場合、全額免除を受けていた期間であれば老後の年金が年間で約1万円増加します。
さらに、納付猶予や学生納付特例の期間であれば、年間で約2万円も年金額を増やすことが可能です。
参考:日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」
第二のメリットは、現在の税金が安くなることです。
追納した保険料は、その年に支払った全額が「社会保険料控除」という所得控除の対象になります。
これにより、課税される所得金額が減るため、結果としてその年の所得税や翌年の住民税の負担を軽くできるのです。
これは、特に所得が多い方にとって見逃せないメリットと言えます。
この記事では、個人事業主に関係する社会保険料控除の種類や書き方、お得な節税の方法についてご説明しています。 本来差し引くことができるものを知らずにいるなら、税金を余計に支払うことになり損をしてしまいます。 ぜひ最後までご覧下さい[…]
追納のデメリット
追納を検討する際には、デメリットについても理解しておく必要があります。
最も分かりやすいデメリットは、一時的にまとまった資金が必要になる点です。
例えば、学生時代2年分の保険料(令和7年度の保険料で換算すると約42万円)を一度に納付する場合、家計への負担は決して小さくありません。
また、追納するタイミングが遅れると「加算金」が発生する場合があります。
これは一種の利息のようなもので、免除や猶予の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納すると、当時の保険料に加えて経過期間に応じた加算額が上乗せされてしまいます。
さらに、追納に使う資金を、iDeCo(個人型確定拠出年金)やNISA(少額投資非課税制度)といった他の資産運用に回した場合と比較して、どちらがご自身のライフプランにとって効率的かを考える視点も大切です。
追納しないと年金どれくらい減る?
もし免除や猶予を受けた期間の保険料を、期限までに追納しなかった場合、その期間に応じて将来の年金受給額は恒久的に減額されてしまいます。
特に注意が必要なのは「納付猶予」や「学生納付特例」の期間です。
これらの期間は、年金を受け取るために必要な「受給資格期間」としてはカウントされますが、追納をしなければ年金額の計算には一切反映されません。
つまり、その期間の年金額は0円として扱われてしまいます。
一方で、「全額免除」の期間は、保険料を全額納付した場合の2分の1の金額(2009年3月分までは3分の1)が、追納しなくても年金額に反映される仕組みになっています。
これは、長生きすればするほど、追納しなかった場合の「損」が大きくなることを意味します。
年金追納しない方がいいケースはある?
追納には多くのメリットがありますが、すべての人に当てはまるわけではなく、中には「追納しない方がいい」と考えられるケースも存在します。
代表的なのは、年収が低く、所得税や住民税をほとんど支払っていない方です。
先ほど取り上げたように、追納の大きなメリットの一つは「所得控除」による節税効果です。
したがって、納めるべき税金がほとんどない場合、この節税メリットを十分に享受できません。
学生納付特例を利用した方が、社会人になってすぐに追納すべきか迷う場合も、ご自身の現在の所得状況で判断するのが賢明です。
他にも、生活保護を受給している方は注意が必要です。
追納によって将来の年金収入が増えた場合、その分だけ生活保護費が減額される可能性があるため、追納に使った費用が実質的に無意味になってしまうことも考えられます。
また、退職金や企業年金、個人の資産運用などで、老後の収入源がすでに十分確保できている方も、無理に追納を選択する必要は低いと言えるでしょう。
年金追納の控除シミュレーション
追納によって実際にどれくらい税金が安くなるのかは、その方の所得によって大きく変わります。
節税額の目安は、以下の式で大まかに計算できます。
節税額の目安 = 追納した保険料額 ×(ご自身の所得税率 + 住民税率)
住民税率は多くの場合10%です。
所得税率は、所得が多いほど高くなる「累進課税」が採用されており、所得額に応じて5%〜45%の税金がかかります。
ここでは、2年分(42万円)を追納した場合の節税シミュレーションを、年収モデル別に見てみましょう。
なお、金額は目安としてお考え下さい。
| 課税所得 | 所得税率 | 合計税率(所得税+住民税10%) | 42万円追納時の節税額 |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 10% | 20% | 84,000円 |
| 500万円 | 20% | 30% | 126,000円 |
| 750万円 | 23% | 33% | 138,600円 |
※表の課税所得は追納適用前の金額です。
このように、所得が多い方ほど、追納による節税メリットは大きくなることが分かります。
参考:国税庁 No.2260 所得税の税率
国民年金の追納メリットを活かす方法

追納のメリットを理解したところで、このセクションでは具体的な行動に移すための情報を提供します。
追納の申込手順や支払い方法、一括払いと分割払いのどちらが得か、そして最も重要な「10年」という期限について解説します。
追納のやり方と支払い方法
国民年金保険料を追納するには、まず「追納したい」という意思表示、つまり事前の申請が必要です。
手続きの基本的な流れは以下の通りです。
「国民年金保険料 追納申込書」を入手する
お近くの年金事務所の窓口で受け取るか、日本年金機構のホームページからダウンロードして印刷します。
また、ご自身の年金記録が確認できる「ねんきんネット」の画面上で作成することも可能です。
申込書を年金事務所へ提出する
必要事項を記入し、基礎年金番号がわかるもの(年金手帳や基礎年金番号通知書など)のコピーや、マイナンバーカード・本人確認書類のコピーを添えて、年金事務所の窓口に持参するか、郵送で提出します。
納付書を受け取り、納付する
申込書が受理されると、後日、日本年金機構から専用の納付書が郵送されてきます。
この納付書を使用して、銀行や郵便局などの金融機関、またはコンビニエンスストアの窓口で保険料を支払います。
納付書に記載されている情報を使えば、Pay-easy(ペイジー)による電子納付も可能です。
ただし、追納保険料の支払いには、普段の保険料納付で使える口座振替やクレジットカード払いは利用できない点には注意が必要です。
一括と分割どっちが得?
年金事務所から送られてくる納付書は、対象期間をまとめて支払うための「一括用」と、1ヶ月単位で支払う「分割用」が同封されています。
どちらが得かは、ご自身の資金状況と節税戦略によって異なります。
「一括払い」の最大のメリットは、節税効果をその年に集中させられる点です。
例えば、退職金を受け取った年や、事業が好調で所得が多くなった年にまとめて支払えば、高い税率が適用される部分の所得を大きく減らすことができ、節税効果が最大化されます。
また、手続きが一度で済む手軽さもあります。
一方、「分割払い」のメリットは、家計への負担を分散できる点です。
一度に数十万円の支出が難しい場合でも、毎月少しずつ、あるいは資金に余裕ができた月だけ納付するといった柔軟な対応が可能です。
ただし、分割払いでのんびり納付していると、3年度目以降の「加算金」が発生する期間に入ってしまうリスクもあるため、計画的な納付が求められます。
10年過ぎた場合
国民年金保険料を追納できる期間には、期限が定められています。
それは、「追納が承認された月の前10年以内の免除・猶予期間」に限られるというルールです。
もし、この10年という期限(時効)を過ぎてしまった場合、その期間の保険料を後から納付する権利は失われてしまいます。
例えば、50代の方が「学生時代の分を払おう」と思い立っても、すでに卒業から30年以上経過している場合は、残念ながら追納することはできません。
もし10年の期限を過ぎた後で、どうしても60歳以降の年金額を増やしたい場合は、「任意加入制度」を利用して60歳から65歳までの期間に国民年金保険料を納付する方法や、会社員として厚生年金に加入し続けるといった方法を検討することになります。
参考:日本年金機構「任意加入制度」
注意点をチェック
追納制度を上手に活用し、後悔しないために、特に注意しておきたい3つのルールがあります。
加算金を意識する(早めの追納がお得)
前述の通り、免除や猶予を受けてから3年度目以降に追納すると、当時の保険料に「加算金」が上乗せされます。
余計な負担を避けるためにも、追納する経済的な余裕ができた場合は、できるだけ2年以内に手続きを済ませるのが最もお得です。
納付は「古い順」がルール
追納は、原則として対象期間のうち最も古い月の分から順番に納めていく必要があります。
例えば、「加算金のかからない直近の1年分だけ先に払いたい」といった、期間を選ぶ納付はできません。
年金の受給権発生後は追納できない
すでに老齢基礎年金を受け取ることができる方、つまり年金を受け取る権利が発生した場合は、後から追納することはできません。
追納の検討と手続きは、必ず年金の受給権が発生する前に行う必要があります。
まとめ:国民年金追納のメリットを再確認しよう
この記事では、国民年金の追納制度について、そのメリットとデメリット、具体的な手続き方法を解説してきました。
国民年金の追納は、「将来受け取る終身年金を増やせる」という老後への確実な備えと、「所得控除によって現在の税負担を軽減できる」という短期的な節税効果の、二つの大きなメリットを同時に得られる制度です。
特に50代を迎え、ねんきん定期便を見て老後資金に不安を感じ始めた方にとっては、この追納制度が、確実な公的年金を増やす最後のチャンスになるかもしれません。
一方で、追納にはまとまった資金が必要であり、10年という時効や加算金の注意点も存在します。
また、所得が低く節税メリットを享受しにくい方や、すでに十分な老後資金がある方にとっては、必ずしも最善の選択とは言えない場合もあります。
ですから、年金の追納メリットは大きいものの、万能の解決策ではありません。
まずは「ねんきんネット」でご自身の年金記録を確認し、追納した場合に年金がいくら増えるのかを試算してみてください。
その上で、ご自身の現在の家計状況や所得税率などと照らし合わせ、冷静に判断することが大切です。