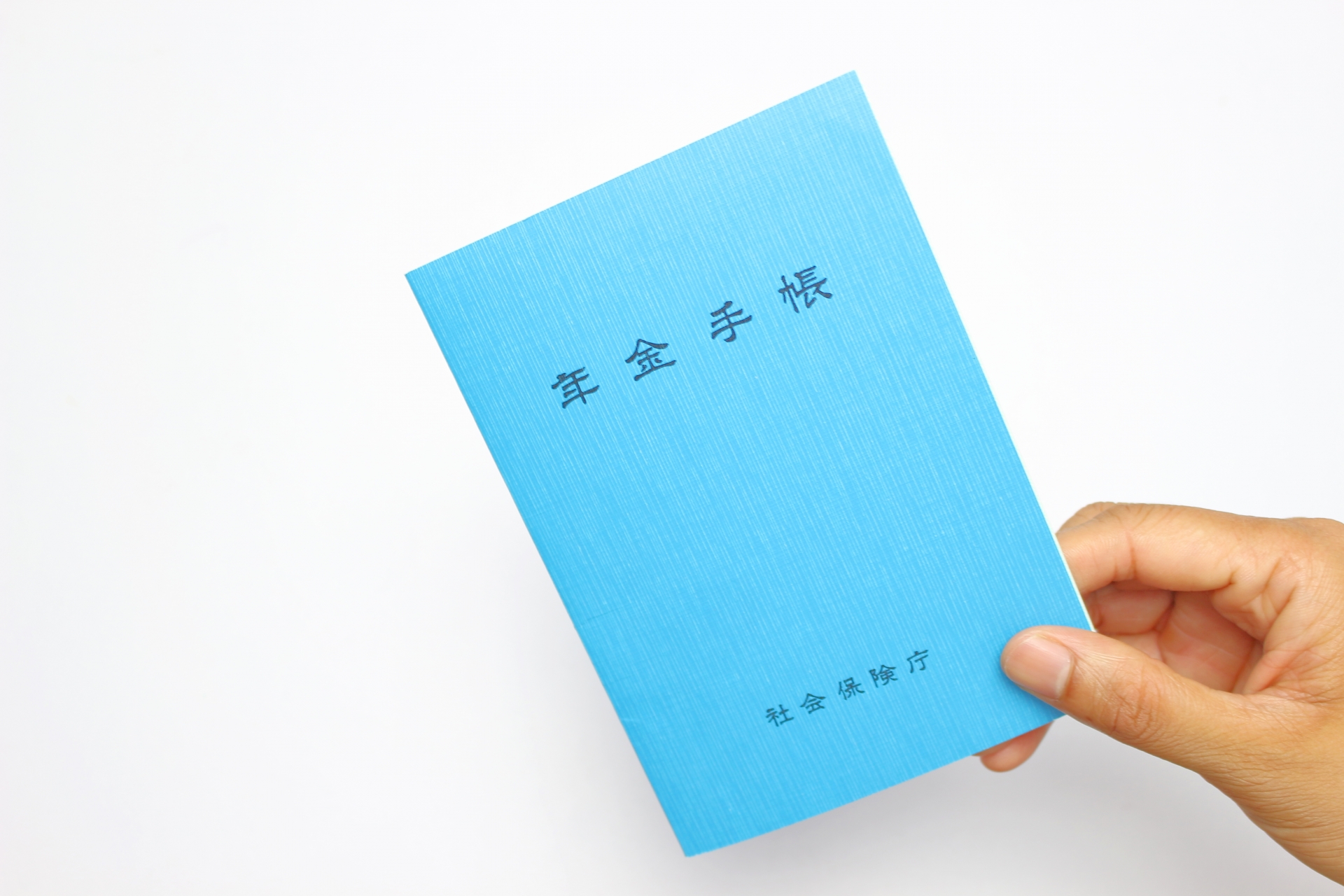「国民年金の支払いが厳しい‥免除制度を使っても大丈夫だろうか」「国民年金の免除はしない方がいいと聞いたけど本当?」と悩んでいませんか。
国民年金の納付書を前に、現在の生活費と将来への不安で板挟みになっている方は少なくありません。
免除制度は経済的に困難な状況を支える大切な仕組みですが、安易に利用すると将来の受給額に影響が出る可能性もあります。
だからこそ、正しい知識を持って慎重に判断することが求められます。
この記事では、免除制度の基本的な仕組みから、利用した場合のメリット・デメリット、そしてあなたの状況に合わせた最適な選択肢は何かを、分かりやすく解説していきます。
本記事のポイント
- 「免除」と「未納」の取り返しのつかない違い
- 免除によって将来の年金額がいくら減るのか
- あなたが免除制度を利用すべきかの判断基準
- 免除した場合に後からできる「追納」の考え方
- 免除申請の具体的な手続きと注意点

国民年金の免除制度について、「利用すると損をする」という漠然としたイメージを持つ方もいるかもしれません。
しかし、この制度は経済的に保険料を納めるのが難しい場合に、将来の保障を完全に失わないための重要なセーフティネットです。
ここでは、制度の基本的な仕組みと、「しない方がいい」と言われる理由であるデメリットについて詳しく見ていきましょう。
そもそも「国民年金の免除」とは?
国民年金の免除制度とは、所得の減少や失業などにより保険料の納付が経済的に困難な場合に、申請して承認されると保険料の納付が免除または猶予される制度です。
これを単に「払わなくてよい制度」と考えるのは早計です。
免除と、何も手続きをしない「未納」とでは、将来に大きな差が生まれます。
免除・猶予制度の種類
免除制度には、所得に応じて4つの区分があります。
- 全額免除: 保険料の全額が免除されます。
- 4分の3免除: 保険料の4分の1を納付します。
- 半額免除: 保険料の半分を納付します。
- 4分の1免除: 保険料の4分の3を納付します。
また、50歳未満の方を対象とした「納付猶予制度」や、学生を対象とした「学生納付特例制度」もあります。
これらは保険料の支払いを先送りにする制度です。
「免除」と「未納」の決定的な違い
最も大切な点は、免除や猶予が承認された期間は、年金を受け取るために必要な「受給資格期間」に含まれるということです。
老齢年金は、この受給資格期間が10年以上ないと1円も受け取れません。
一方で、手続きをせずに保険料を支払わない「未納」の期間は、受給資格期間に全く算入されません。
さらに、万が一の際の障害年金や遺族年金を受け取れなくなるリスクも高まります。
経済的に支払いが困難な場合は、未納のまま放置せず、必ず免除・猶予の申請をすることが将来を守る上で不可欠です。
個人事業主として独立すると、会社員時代とは異なり、年金の支払いを自分自身で管理する必要があります。 その中で、「年金払わないとどうなるのだろうか」という疑問や、収入が不安定な時期には「保険料の支払いが苦しい」といった悩みに直面[…]
国民年金の全額免除がもたらすデメリット
免除制度がセーフティネットとして機能する一方、「免除しない方がいい」と言われるのには明確な理由があります。
最大のデメリットは将来受け取る老齢基礎年金の金額が減額される点です。
全額免除が承認された期間は、保険料を全額納付した場合と比較して、年金額の計算が半分(2分の1)になります。
これは、年金制度が保険料と国庫負担(税金)で成り立っており、全額免除期間は国庫負担分のみが年金額に反映されるためです。
また、もう一つのデメリットとして、将来の年金額を上乗せする制度の利用に制限がかかる点が挙げられます。
各制度で条件が異なるため、個別に確認しましょう。
付加年金
保険料の免除(学生納付特例、納付猶予を含む)を受けている期間は、付加保険料を納めることができません。
ただし、産前産後期間の免除を受けている場合は納付が可能です。
「老後の資金、国民年金だけだと少し不安…」「何か手軽に始められる対策はないだろうか」と感じていませんか。 自営業やフリーランスとして働く方々にとって、将来の年金額は切実な問題です。 そんな中で、付加年金という言葉を耳にし[…]
国民年金基金
保険料の免除期間中は加入できません。
しかし、法定免除を受けている方が「申出納付制度」を利用して保険料を納めている期間や、産前産後免除の期間中は加入できます。
(参考:国民年金基金連合会)
自営業者(個人事業主やフリーランス)の方が、将来貰える年金を増やす方法の一つとして「国民年金基金」を活用することができます。 この記事では、国民年金基金の基本的な内容についてご説明しています。 […]
iDeCo(個人型確定拠出年金)
第1号被保険者の方が保険料の全額または一部免除を受けている場合、原則として加入・掛金の拠出ができません。
障害基礎年金を受給している方など一部例外はありますが、注意が必要です。
特に産前産後免除期間中の加入資格の扱いについては、申し込みの前に必ずiDeCoの運営管理機関または国民年金基金連合会へ最新の条件を確認することをおすすめします。
(参考:iDeCo公式サイト)
国民年金の全額免除でいくらもらえる?
では、実際に全額免除を利用すると、将来の年金額はどのくらいになるのでしょうか。
老齢基礎年金は、20歳から60歳までの40年間(480ヶ月)すべて保険料を納付すると満額を受け取れます。
2025(令和7)年度の満額は年額831,700円です。
前述の通り、全額免除期間は年金額が2分の1で計算されます。
つまり、もし40年間のすべてを全額免除で過ごした場合、将来受け取る年金額は満額の半分である約41.6万円(月額約3.5万円)になります。
この金額だけで老後の生活を賄うのは、非常に厳しいと言わざるを得ません。
免除はあくまで一時的な措置であり、将来の生活設計を考える上では、この減額をどう補うかが課題となります。
全額免除を10年続けるといくらもらえる?
より現実的な例で考えてみましょう。40年間の加入期間のうち、10年間(120ヶ月)を全額免除、残りの30年間(360ヶ月)は全額納付したケースを想定します。
この場合の年金額は、以下のように計算できます。
全額納付した期間(30年分):831,700円 × (360ヶ月 ÷ 480ヶ月) = 623,775円
全額免除した期間(10年分):831,700円 × (120ヶ月 ÷ 480ヶ月) × 1/2 = 103,962.5円
これらを合計すると、年間の受給額は約72.8万円となります。
満額の約83.2万円と比較すると、年間で約10.4万円の減額です。
10年間の免除が、将来にわたってこれだけの影響を与えることを理解しておく必要があります。
国民年金の免除シミュレーション
免除の種類によって年金額への影響は異なります。
ここでは、20歳から国民年金に加入し、3年間(36ヶ月)だけ経済的に納付が困難になった場合の年金額を、2025(令和7)年度の満額(831,700円)を基に比較してみましょう。
| ケース | 3年間の状況 | 将来の年金額(年額) | 満額からの減額分 |
|---|---|---|---|
| 未納の場合 | 未納(手続きなし) | 769,323円 | ▲62,377円 |
| 全額免除 | 全額免除 | 800,511円 | ▲31,189円 |
| 4分の3免除 | 4分の3免除(4分の1納付) | 808,308円 | ▲23,392円 |
| 半額免除 | 半額免除(2分の1納付) | 816,106円 | ▲15,594円 |
| 4分の1免除 | 4分の1免除(4分の3納付) | 823,903円 | ▲7,797円 |
この表から分かるように、たとえ全額免除であっても、未納の場合と比較すると将来の年金額は大きく変わります。
未納のまま放置することが、いかに大きな不利益に繋がるかが明確です。
国民年金は免除しない方がいい?申請と追納の判断

免除制度のデメリットを理解した上で、次に考えるべきは「自分はどう行動すべきか」です。
経済状況が厳しい中で、無理して納付を続けるべきか、それとも免除を申請し、将来の追納にかけるべきか。
ここでは、申請方法から追納の考え方まで、具体的な判断基準を解説します。
国民年金の免除申請の方法と注意点
免除や納付猶予の申請は、住民票のある市区町村の役場や、お近くの年金事務所の窓口で行います。
マイナンバーカードがあれば、マイナポータルを通じた電子申請も可能で、時間や場所を選ばず手続きができて便利です。
申請に必要なもの
申請には、基礎年金番号がわかるもの(年金手帳や基礎年金番号通知書など)や本人確認書類が必要です。
また、失業を理由に申請する場合は、「雇用保険被保険者離職票」や「雇用保険受給資格者証」のコピーなど、失業した事実がわかる書類を添付すると、特例として本人の所得を除外して審査されるため、承認されやすくなります。
申請における注意点
申請する際の注意点として、所得審査の対象が本人だけではない点が挙げられます。
全額免除や一部免除の審査では、申請者本人に加えて、配偶者や世帯主の所得も審査の対象となります。
そのため、本人の所得が低くても、同居する家族の所得が高い場合は免除が承認されないことがあります。
年金の免除申請はしたほうがいいですか?
この問いに対する答えは明確です。
「保険料の支払いが経済的に困難な場合、免除申請は絶対にすべき」と言えます。
繰り返しになりますが、最大の理由は「未納」を防ぐためです。
未納期間は、老齢年金の受給資格期間に算入されないだけでなく、病気や事故で障害を負った際の「障害年金」や、一家の働き手が亡くなった際の「遺族年金」の受給資格にも影響します。
これらの年金は、万が一の事態が発生した際の生活を支える非常に重要な保障です。
免除期間は、これらの年金の納付要件を見る際に「保険料を納めた期間」とほぼ同様に扱われます。
つまり、免除申請をしておけば、不測の事態が起きても年金を受け取れる可能性が残ります。
この一点だけでも、免除を申請する価値は計り知れません。
(参考:日本年金機構「障害基礎年金」)
国民年金の全額免除なのに払ってしまったら
免除の申請と保険料の納付がすれ違いになり、「全額免除が承認されたのに、誤って保険料を納付してしまった」というケースもあり得ます。
このような場合、納め過ぎた保険料は還付(返金)してもらうことが可能です。
通常、日本年金機構から還付に関する通知が届きますので、その案内に従って手続きを進めることになります。
もし通知が届かないなど、不明な点があれば、お近くの年金事務所に問い合わせて状況を確認しましょう。
年金は追納しない方がいい?
免除や猶予を受けた保険料は、10年以内であれば後から納める「追納」ができます。
追納することで、免除期間を「全額納付した期間」として扱えるため、将来の年金額を満額に近づけることが可能です。
一方で、「追納しない方がいい」という意見も存在します。
これは、追納する資金をiDeCoやNISAなどの資産運用に回した方が、将来的により多くの資産を築ける可能性があるという考え方です。
どちらが正解かは一概には言えません。
追納は、将来受け取る公的年金を確実に増やす、いわば元本保証に近い堅実な選択です。
また、追納した保険料は全額が社会保険料控除の対象となり、所得税や住民税が軽減されるという大きなメリットもあります。
現在の家計状況、ご自身の投資に関する知識やリスク許容度、そして老後の生活設計などを総合的に考慮し、追納するかどうかを判断することが大切です。
年金を免除し続けるとどうなる?
もし、20歳から60歳までの40年間、一度も保険料を納付せず、すべて全額免除で通した場合、どうなるのでしょうか。
先ほども触れたように、この場合でも老齢基礎年金を受け取る権利は失われません。
受給資格期間は満たしているため、65歳から年金を受け取ることができます。
ただし、その金額は満額の半分、年間で約41.6万円です。
月額に換算すると約3.5万円となり、この金額だけで生活していくことは現実的ではありません。
貯蓄を取り崩したり、働き続けたり、あるいは他の公的支援に頼ったりする必要が出てくるでしょう。
免除制度はあくまで緊急避難的な措置であり、可能な限り納付または追納することが、安定した老後への備えとなります。
1年免除でいくら減る?
免除による年金額の減額について、より身近な単位で考えてみましょう。
「もし1年間だけ全額免除にしたら、将来の年金はいくら減るのか」という質問はよくあります。
2025(令和7)年度の満額(831,700円)を基準に計算すると、1年間(12ヶ月)の全額免除による年金額の減少分は以下のようになります。
- 831,700円 × (12ヶ月 ÷ 480ヶ月) × 1/2 = 約10,400円
つまり、1年間の全額免除で、将来受け取る年金が毎年約1万円ずつ減額される計算です。
これが20年、30年と続くと、総受給額では数十万円の差になります。
この金額を「わずか」と見るか、「大きな差」と見るかは人それぞれですが、将来への影響を具体的に把握しておくことが判断の第一歩です。
まとめ
「国民年金は免除しない方がいい」という言葉の真意は、「可能であれば全額納付した方が、将来もらえる年金額は最も多くなる」という事実を指しています。
しかし、経済的な事情を無視して無理に納付を続ければ、現在の生活が破綻しかねません。
この記事で解説した通り、保険料の支払いが困難な場合は、将来の保障を失わないためにも、未納のまま放置するのではなく、必ず免除・猶予の申請を行うべきです。
重要なのは、免除制度を正しく理解し、セーフティネットとして賢く活用することです。
免除は一時的な措置と捉え、経済状況が改善した際には、将来の年金額を増やすための「追納」を積極的に検討しましょう。