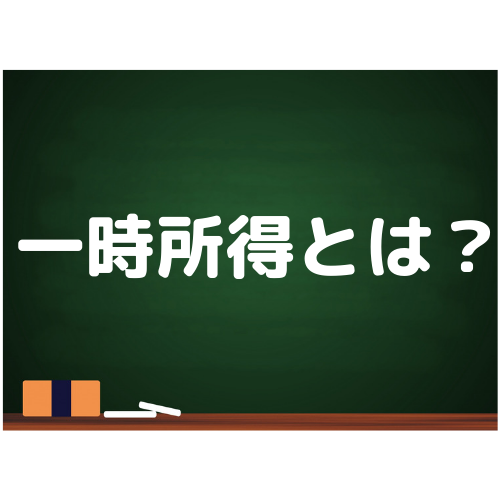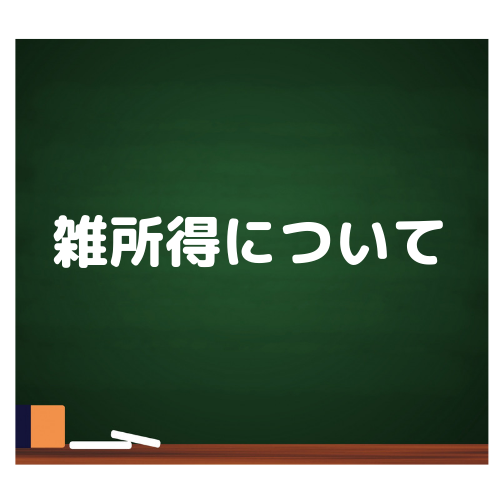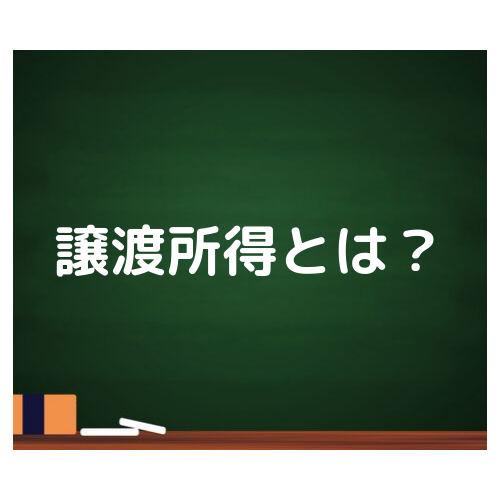この記事では、一時所得について取り上げています。
一時所得に該当する収入の見分け方や雑所得との違い、具体例や計算方法などをまとめています。
PR
⚠️ 確定申告、まだ終わってない方へ
「何から手をつければいいか分からない…」という方は、安心プランの「丸投げ仕分け」を使うと、仕訳の着手ハードルが下がります。ただし、最終的な経費・プライベート判断は自分で確認が必要なので、まずは無料期間で動作確認してから判断するのが安心です。
3/16まで提出以外の機能は無料で試せます。
一時所得とは
一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。
所得税法にある通り、一時所得は他の8つの所得(利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得)に分類出来ない所得となります。
そして、一時所得にも該当しない場合は、雑所得として申告する必要があります。
一時所得と雑所得の金額は、計算方法が異なりますので、どちらの所得に区分されるかによって確定申告の際に計算する税金の金額に違いが生じることになります。
所得区分を間違えてしまうと、正しい税金計算ができなくなる可能性があります。
ですから、一時所得と雑所得の違いについて抑えておくことは大切です。
一時所得と雑所得の違い
一時所得と雑所得の違いについては、所得税法34条1項の内容から判断することが可能です。
営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの
上記の表現から、一時所得は継続性を有しない一時的・臨時的な所得ということになります。
また一時的な収入でも、報酬を受ける目的で働いて得た収入や、資産を売って得た収入などは一時所得には該当しないことになります。
一時所得と雑所得の違いを、簡単にまとめると下記の通りです。
- 一時所得・・一時的な収入(働いて得た収入や物を売って得た収入は一時所得とはならない)
- 雑所得・・一時所得に該当しない収入
一時所得の具体例
一時所得に該当する収入について、主なものをいくつかご紹介したいと思います。
- 生命保険契約等の一時金
- 競馬や競輪の払戻金
- 賞金や懸賞の当選金
- 借家人が受け取る立退料
- 遺失物拾得者や埋蔵物発見者が受ける報奨金や所有権を取得する資産
取り上げた事例は、あくまでも一例です。
また、上記の内容でも状況によっては、一時所得に該当しない場合もありえます。
例えば、競馬で得た収入であっても、営利目的の継続的な行為として得られた所得とみなされ雑所得と判断された事例もあります。
ですから、ご自身で判断が難しい場合は専門家に相談することをお勧め致します。
一時所得の計算について
一時所得の計算に関しては、抑えておく必要のある2つのポイントをご説明したいと思います。
特別控除額
一時所得を計算は、収入金額から支出した金額を差し引き、さらに特別控除額を差し引いて求めます。
一時所得の計算式:収入金額ー支出金額ー特別控除額(最高50万円)
特別控除額は最高で50万円となっています。
ですから、仮に一時所得に分類される収入の合計が50万円以下であれば、一時所得については所得税はかかりません。
総所得金額を計算する際の注意点
総所得金額を求める際に注意すべきポイントがあります。
総所得金額とは、総合課税の所得を合算することです。
一時所得は、総合課税に分類されますので、総合課税に区分されている他の所得に加えて総所得金額を求める必要があります。
この総所得金額に一時所得を加える際は、一時所得に1/2を乗じた金額となります。
先程ご紹介した計算式は一時所得を求めるための式です。
そこで計算した金額を、そのまま総所得金額に加えないようにご注意下さい。
まとめ
一時所得とは次の要件を満たした所得です。
- 8つの所得(利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得)に分類出来ない所得
- 継続性を伴わない一時的な収入で、働いて得た収入や物を売って得た収入ではないこと
一時所得の計算
- 一時所得=収入金額ー支出金額ー特別控除額(最高50万円)
総所得金額の計算
- 総所得金額=収入金額ー支出金額ー特別控除額(最高50万円)×1/2
🔧 当サイト独自の無料診断ツール(個人情報の登録不要)
- 一般家庭の平均と比較して「高い支出」を1分でチェック。勘定科目も表示!(個人事業主・フリーランス向け)
-
🧾 会計ソフト診断あなたの業種・規模に合う会計ソフトを最短で判定