フリーランスや個人事業主として活動していると、収入が不安定な時期もあります。
毎月の国民年金保険料の支払いを重く感じ、「今月、払えるだろうか…」と不安になることもあるかもしれません。
しかし、支払いが困難だからといって「未納」のまま放置するのは、将来のリスクを考えると非常に危険です。
この記事では、経済的に保険料を納めるのが難しい方のために用意されている国民年金保険料の免除・納付猶予制度について、その免除条件や申請方法、注意点を詳しく解説します。
- 免除と納付猶予の具体的な所得基準
- 免除制度を利用するメリットとデメリット
- 失業や無職の場合の特例措置
- 免除申請の具体的な手続き方法
- 申請が却下された場合の対処法
ファイナンシャルプランナー2級・AFP、日商簿記2級、行政書士(未登録)の資格保有者の個人事業主。詳細は運営者情報をご覧ください。
PR
⚠️ 確定申告、まだ終わってない方へ
確定申告がまだ終わっていない方は、まず仕訳を片付けると一気に気持ちがラクになります。特にタックスナップの「丸投げ仕分け」は、迷いがちな仕訳作業を一気に進められる機能です。
私の場合は、 667件の取引が約2秒 で仕訳されました。ただし端末や通信状況などにより、処理の時間は異なる可能性があります。
3/16までは提出・印刷以外を無料で試せます。無料のうちに使ってみて、合うかどうかを確認してみてください。
※仕訳後に、勘定科目や金額は念のため確認しておくと安心です。
※3/16まで、提出以外の機能は無料で試せます。
クーポンは、初回登録時に入力しておくとスムーズです。合わなければ無料期間中に解約できます。
▶ 無料でタックスナップを試してみる(3/16まで) ※「丸投げ仕分け」の詳細や体験談を確認できる記事はこちら国民年金の免除条件の基本を解説

国民年金の支払いが難しいと感じたとき、まず知っておきたいのが「免除」と「納付猶予」の制度です。
このセクションでは、どのような方が対象になるのか、所得(年収)の基準はいくらなのか、そして無職や失業した場合の特例など、基本的な知識をわかりやすく解説します。
免除の条件と年収の基準
国民年金保険料の免除や納付猶予を受けられるかどうかは、原則として申請者ご本人・配偶者・世帯主の「前年所得」によって審査されます。
ただし、申請する時期が1月~6月の場合は「前々年所得」が審査対象となる点に注意が必要です。
ここで大切なのは、フリーランスや個人事業主の場合、「売上」ではなく「所得(売上から経費を差し引いた金額)」が基準になる点です。
制度には「全額免除」「一部免除(4分の3、半額、4分の1)」「納付猶予」があり、それぞれ所得基準が異なります。
なお、以下の表に示す所得基準はあくまで目安です。
特に一部免除の基準額は、確定申告で申告した社会保険料控除額や扶養親族の状況などによって変動するためご注意ください。
| 免除・猶予の種類 | 所得基準の目安(単身・扶養親族0人の場合) | 審査対象 |
|---|---|---|
| 全額免除 | 所得 67万円以下 | 本人・配偶者・世帯主 |
| 4分の3免除 | 所得 88万円以下 | 本人・配偶者・世帯主 |
| 半額免除 | 所得 128万円以下 | 本人・配偶者・世帯主 |
| 4分の1免除 | 所得 168万円以下 | 本人・配偶者・世帯主 |
| 納付猶予(50歳未満対象) | 所得 67万円以下 | 本人・配偶者 |
※全額免除・納付猶予の基準計算式: (扶養親族等の数 + 1) × 35万円 + 32万円
※一部免除の基準額には、扶養親族等控除額や社会保険料控除額などが加算されます。
より詳しい所得基準については、日本年金機構の公式サイトをご確認ください。
「免除」と「納付猶予」の主な違い
「免除」と「納付猶予」は、どちらも経済的に困難な場合に保険料の納付負担を軽減する制度です。
両制度とも、承認されればその期間は将来の年金受給に必要な「受給資格期間」にカウントされます。
これにより、万が一の際の障害年金や遺族年金を受け取るための保険料納付要件にも含まれるため、「未納」を防ぐ上で非常に有効な手段となります。
ただし、この2つの制度には大きな違いがあります。
それは、将来もらえる老齢基礎年金額に反映されるかどうかです。
| 項目 | 免除制度 | 納付猶予制度 |
|---|---|---|
| 対象年齢 | 20歳~60歳未満(被保険者) | 20歳~50歳未満(被保険者) |
| 審査対象 | 本人・配偶者・世帯主 | 本人・配偶者 |
| 年金額への反映
(全額納付時を1とした場合) |
反映される
・全額免除: 4/8 (1/2) ・4分の3免除: 5/8 ・半額免除: 6/8 (3/4) ・4分の1免除: 7/8 |
反映されない(0円として計算) |
| 追納(後払い) | 10年以内なら可能 | 10年以内なら可能 |
納付猶予は年金額に全く反映されないため、将来の受給額を少しでも確保したい場合は、免除制度の方がメリットがあると考えられます。
どちらの制度も、10年以内であれば保険料を後から納める「追納」が可能です。
免除シミュレーション
ご自身が免除や猶予の対象になるか、まずは前年(または前々年)の確定申告書を準備して「所得金額」の欄を確認してみましょう。
例えば、あなたがフリーランスWebデザイナーで、昨年の確定申告での所得金額(売上から経費等を引いた額)が「約180万円」だったとします。(申請が7月以降と仮定)
この場合、前掲の表に当てはめると、所得180万円は「4分の1免除」の基準である「168万円以下」を超えています。
したがって、原則的な所得基準では、免除・猶予制度の対象外となる可能性が高いと判断されます。
免除は失業(自己都合)でも可能
所得基準では対象外だったとしても、まだ諦める必要はありません。
「失業等による特例免除」という制度があります。
これは、失業・倒産・事業の廃止(廃業)などにより保険料の納付が困難になった場合に利用できる特例です。
この特例を申請すると、失業したご本人の前年所得を「0円」として審査してもらえます。
ただし、配偶者や世帯主が審査対象となる場合、その方々の所得審査は通常どおり行われます。
会社員であれば「雇用保険被保険者離職票」などで失業を証明できますが、フリーランスの場合は「廃業届」の控えや、「総合支援資金貸付」の決定通知書の写しなどが、失業に準ずる公的な証明書類として認められる場合があります。
自己都合による退職や廃業であっても、この特例は利用可能です。
前年の所得が基準額を超えていたとしても、この特例を利用すれば、配偶者や世帯主の所得が基準内であれば、免除や猶予が承認される可能性が高くなります。
なお、失業特例が適用される期間は、原則として失業した日(退職日)の翌日を含む月の前月分から、翌々年の6月分までとなります。
納付猶予という選択肢も
無職で所得がない、あるいは前年の所得が基準額以下であれば、国民年金免除の条件に該当する可能性は高いです。
ただし、注意点があります。
先ほども取り上げたように、「免除」制度は申請者本人だけでなく、配偶者や「世帯主」の所得も審査対象になります。
例えば、ご本人が無職で所得が0円でも、実家暮らしで世帯主である父親に十分な所得がある場合、「免除」の申請は却下されることがあります。
このような場合、ご本人が50歳未満であれば、「納付猶予」制度を申請するのが有効です。
納付猶予制度の審査対象は本人と配偶者のみで、世帯主の所得は問われないため、承認される可能性が高まります。
国民年金の免除申請の方法と注意点
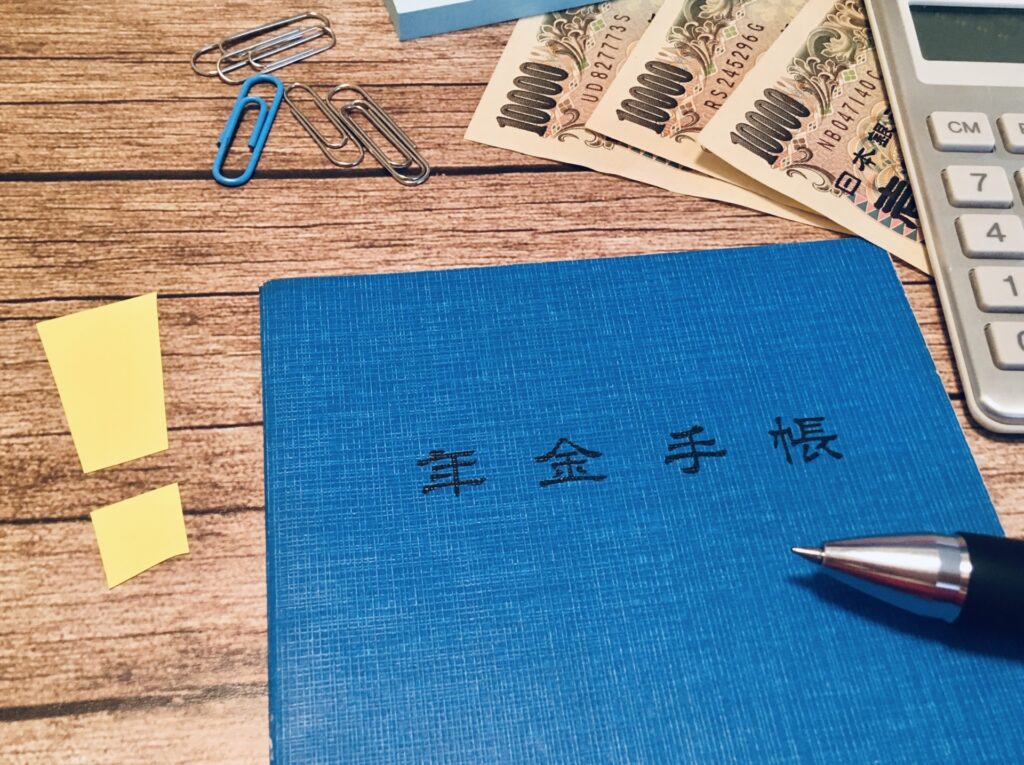
このセクションでは、国民年金免除の申請に必要な書類や手続きの流れ、そして「申請したのに納付書が届いた」「申請が却下された」といったよくある疑問への対処法を解説します。
また、免除制度を利用する前に知っておくべきデメリットや、未納のまま放置するリスクについても触れていきます。
申請方法と必要書類
国民年金免除の申請手続きは、お住まいの市区町村役場の国民年金担当窓口、またはお近くの年金事務所で行います。
申請は原則として毎年度必要です。
申請方法
- 窓口で申請: 市区町村役場や年金事務所の窓口で、申請書に記入して提出します。
- 郵送で申請: 年金事務所から申請書を取り寄せ、または日本年金機構のホームページからダウンロードし、必要事項を記入して管轄の年金事務所に郵送します。
- 電子申請: マイナンバーカードをお持ちであれば、マイナポータルを利用して電子申請も可能です。
必要なもの
- 本人確認書類: マイナンバーカード、または基礎年金番号通知書(年金手帳)と運転免許証など。
- 失業による特例を申請する場合: 雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、廃業届の控えなど、失業の事実が確認できる公的書類のコピー。
申請したのに納付書が届く理由
免除の申請をしたにもかかわらず、日本年金機構から保険料の「納付書」が届くと、「申請が通らなかったのでは?」と不安になるかもしれません。
しかし、心配は不要です。
免除申請の結果が出るまでには、通常2〜3ヶ月程度の時間がかかります。
そのため、申請の審査中に、行き違いで納付書が発送されてしまうことがよくあります。
審査結果は、後日ハガキで届きます。
その結果が届くまでは、手元の納付書で保険料を納付せず、大切に保管しておいてください。
無事に「全額免除」や「納付猶予」の承認通知が届けば、手元の納付書は破棄して問題ありません。
申請が却下される理由と対処法
万が一、免除申請が却下された場合、その理由は何なのでしょうか。
年金の免除申請が却下される理由
却下される最も一般的な理由は、所得基準の超過です。
申請者本人、配偶者、または世帯主のうち、誰かの前年(または前々年)所得が基準額を上回っていると、申請は承認されません。
例えば、前述の通り、ご本人が無職でも実家暮らしで世帯主の所得が高い場合、「免除」が却下されるのはこのためです。
却下された場合の対処法
- 却下理由の確認: まず、送られてきた却下通知書で、なぜ却下されたのか(誰の所得が基準を超えたのか)を確認します。
- 納付猶予で再申請(50歳未満の方): もし「免除」が世帯主の所得が理由で却下された場合、50歳未満であれば「納付猶予」で再申請を検討します。納付猶予は世帯主の所得が審査対象外のため、承認される可能性があります。
- 一部免除の納付: もし「4分の1免除」や「半額免除」が承認された場合は、減額された保険料を納付する必要があります。これを納付しないと、その期間は一部免除が無効となり、「未納期間」として扱われるため注意してください。
- 放置しない: 却下されたからといって保険料を放置すると「未納」となり、将来のリスクが非常に高くなります。必ず保険料を納付するか、年金事務所に相談してください。
デメリットと未納リスク
国民年金の納付は国民の義務ですが、経済的に困難な場合は、免除や猶予制度を利用するために申請すべきです。
ただし、全額免除のデメリットも理解しておく必要があります。
免除のデメリット
- 将来の老齢年金額が減る: これが最大のデメリットです。全額免除の期間は、保険料を全額納付した場合と比べて、将来受け取る年金額が「2分の1」で計算されます。一部免除の場合も、納付した割合に応じて減額されます。納付猶予の場合は「0円」計算です。
- 追納しないと年金額は回復しない: 免除・猶予された保険料は、10年以内であれば追納が可能です。しかし、経済状況が改善せず追納できなければ、年金額は減ったまま確定します。
- 付加年金・国民年金基金に加入できない: 免除・猶予期間中は、将来の年金額を上乗せできる付加年金や国民年金基金に加入することができません。
「未納」のまま放置することが最大のリスク
デメリットがあるとはいえ、免除申請をせずに「未納」のまま放置することは、比べ物にならないほど大きなリスクを伴います。
- 将来の年金がゼロになる可能性: 老齢基礎年金は、受給資格期間が10年未満だと1円も受け取れません。免除期間はカウントされますが、未納期間はカウントされません。
- 障害年金・遺族年金がもらえない可能性: 病気や事故で障害が残ったり、死亡したりした場合、保険料の未納期間が一定以上あると、障害年金や遺族年金が支給されないことがあります。
- 財産の差し押さえ: 納付書や督促状を無視し続けると、最終的には財産が差し押さえられる可能性があります。
これらの点を踏まえると、たとえ年金額が減るデメリットがあったとしても、保険料の支払いが困難な場合は、必ず「免除」または「納付猶予」の申請を行うことが、ご自身の将来を守る最善の選択と言えます。
個人事業主として独立すると、会社員時代とは異なり、年金の支払いを自分自身で管理する必要があります。 その中で、「年金払わないとどうなるのだろうか」という疑問や、収入が不安定な時期には「保険料の支払いが苦しい」といった悩みに直面[…]
まとめ
今回は、フリーランスや個人事業主の方が直面しがちな国民年金の支払いに関する、免除条件を中心に解説しました。
国民年金の免除や猶予は、前年(1~6月申請の場合は前々年)の所得によって承認されるかが決まります。
ご自身の所得が基準を超えていても、フリーランスの方が廃業した場合など失業による特例が適用されれば、免除を受けられる可能性があります。
免除は将来の年金額が減額されますが受給資格期間に含まれ、納付猶予は年金額に反映されませんが、同じく受給資格期間に含まれます。
どちらの制度も、将来の年金額が減るというデメリットはありますが、10年以内の追納で回復させることも可能です。
最も避けなければならないのは、申請もせず未納のまま放置することです。
未納は、将来の老齢年金だけでなく、万が一の際の障害年金や遺族年金を受け取れなくなるリスクや、財産差し押さえのリスクを伴います。
経済的に厳しいときだからこそ、ご自身の免除条件を正しく確認し、適切な手続きを行うことが、将来の安心を守るための第一歩となります。






