会社を退職し、個人事業主やフリーランスとして独立開業を目指すとき、多くの方がお金に関する不安を抱えることでしょう。
特に、退職給付金や失業手当という言葉は耳にしますが、これらの違いを正確に理解しているでしょうか。
独立という大きな一歩を踏み出す上で、二つの公的制度の違いを把握しておくことは、あなたの生活と事業の基盤を支えるために非常に大切です。
この記事では、あなたの新しい挑戦を経済的にサポートするための知識を、分かりやすく解説していきます。
本記事のポイント
- 退職給付金と失業手当の根本的な制度の違い
- 独立を目指す場合に利用すべき公的制度の内容
- 退職後に必要な手続きの種類とそれぞれの申請期限
ファイナンシャルプランナー2級・AFP、日商簿記2級、行政書士の資格保有者の個人事業主。詳細は運営者情報をご覧ください。
PR
⚠️ 確定申告、まだ終わってない方へ
確定申告がまだ終わっていない方は、まず仕訳を片付けると一気に気持ちがラクになります。特にタックスナップの「丸投げ仕分け」は、迷いがちな仕訳作業を一気に進められる機能です。
私の場合は、 667件の取引が約2秒 で仕訳されました。ただし端末や通信状況などにより、処理の時間は異なる可能性があります。
3/16までは提出・印刷以外を無料で試せます。無料のうちに使ってみて、合うかどうかを確認してみてください。
※仕訳後に、勘定科目や金額は念のため確認しておくと安心です。
※3/16まで、提出以外の機能は無料で試せます。
クーポンは、初回登録時に入力しておくとスムーズです。合わなければ無料期間中に解約できます。
▶ 無料でタックスナップを試してみる(3/16まで) ※「丸投げ仕分け」の詳細や体験談を確認できる記事はこちら退職給付金と失業手当の違いを解説|独立予定の方にも関係する内容とは?

ここではまず、言葉の定義を整理します。
退職給付金と失業手当の違いだけでなく、退職給付金に含まれる公的給付の種類や、自己都合退職の場合のルール、受給期間延長といった基礎知識を分かりやすく解説します。
※この記事における「退職給付金」という言葉について
はじめに、この記事で用いる「退職給付金」という言葉についてご説明します。
これは法律で定められた単一の制度を指すものではなく、退職後に受け取れる可能性のある失業手当や傷病手当金といった公的な給付を広く指す通称として使用しています。
会社の退職金(退職手当)は含みません。
利用すべき制度の違い
退職後の生活を支える制度を考える上で、独立を目指す場合にまず理解すべき点は、「今の自分が働ける状態か」「いつ開業する予定か」によって、利用すべき制度とその順番が全く異なるということです。
例えば、心身ともに健康で、すぐにでも事業を始められる状態であれば、失業手当の手続き後に早期開業し、「再就職手当」を受け取るのが賢明な選択肢と考えられます。
一方で、体調不良が理由で退職した場合は、まず健康保険の「傷病手当金」で療養に専念し、回復してから雇用保険の「失業手当」に切り替えることを検討できます。
このように、退職給付金や失業手当は、単にもらえるお金というだけでなく、あなたの状況に合わせて計画的に活用するべき制度です。
退職給付金の一覧
一般的に「退職給付金」という言葉は、広い意味で「退職後に受け取れる公的な給付の総称」として使われることがあります。
これには、失業手当以外にも様々な種類が含まれます。
主な給付金の種類は以下の通りです。
- 失業手当(雇用保険の基本手当):働く意思と能力があるにもかかわらず、失業状態にある方の生活を支え、再就職を支援するための給付です。
- 再就職手当:失業手当の受給資格がある方が、早期に安定した職業に就いた(または事業を開始した)場合に支給される、お祝い金のような一時金です。
- 傷病手当(雇用保険):ハローワークで求職活動中に、病気やケガで15日以上働けなくなった場合に、失業手当の代わりに支給されるものです。
- 傷病手当金(健康保険):業務外の病気やケガで働けなくなり、給与が支払われない場合に、生活を保障するために健康保険から支給されます。退職後も一定の条件を満たせば継続して受給が可能です。
これらの給付金は、それぞれ目的や支給元、受給条件が異なります。
特に、傷病手当(雇用保険)と傷病手当金(健康保険)は名前が似ていますが全く別の制度であり、混同しないよう注意が求められます。
自営も対象の再就職手当とは?
独立を目指す方にとって、最も注目すべき制度が「再就職手当」です。
この制度のポイントは、会社への再就職だけでなく、個人事業主としての開業やフリーランスとしての事業開始も支給対象となる点にあります。
しかし、いくつかの重要な要件を満たす必要があり、特に自己都合で退職した方はタイミングに注意が不可欠です。
主な要件を以下にまとめます。
- 7日間の待期期間を満了した後に、就職または事業を開始していること。
- 就職日の前日までに失業の認定を受け、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること。
- 自己都合退職などで給付制限がある場合、待期満了後1か月間については、ハローワーク等の“紹介で雇用される就職”だけが再就職手当の対象です。(※この期間の自営開始は原則対象外となります)
最後の点が特に重要で、自己都合で退職した方が自営で再就職手当を受けたい場合は、「待期7日+給付制限1か月」が過ぎてから開業し、開業の翌日から1か月以内に申請してください。
参考:厚生労働省「再就職手当のご案内」
自己都合退職の給付制限と受給期間延長
失業手当の受給を考える際、退職理由が「自己都合」か「会社都合」かは大きな違いを生みます。
自己都合退職の給付制限
ご自身の意思で退職した「自己都合退職」の場合、7日間の待期期間に加えて、原則として1か月間の「給付制限」が設けられます(2025年4月1日以降の離職者)。
この期間中は失業手当が支給されません。
独立を考えている方は、この給付制限期間が明けた後に開業届を提出し、再就職手当を申請するのが一般的な流れとなります。
受給期間の延長制度
病気やケガ、妊娠、出産、介護などの理由ですぐに働けない場合は、「受給期間の延長」を申請できます。
本来、失業手当を受け取れる期間は離職日の翌日から1年間ですが、この手続きを行うことで、働けない期間分だけ受給期間を先延ばしにすることが可能です(最大で本来の1年+3年間)。
参考:ハローワーク インターネットサービス「基本手当について」
退職金と失業保険は2重にもらえるか?
多くの方が疑問に思う点ですが、「会社の退職金」と「国の失業手当(雇用保険)」は、全く別の制度であるため、両方を受け取ることが可能です。
会社の退職金の有無やその額は、失業手当の支給要件に原則として影響しません。
しばしば「高額な退職金をもらうと失業手当は受けられない」という話を聞くことがありますが、これは誤解です。
もちろん、失業手当を受けるには、離職理由や就労の意思、被保険者期間など、定められた要件を満たすことが大前提となります。
ただし、注意点として、健康保険の傷病手当金と雇用保険の失業手当を同時に受け取ることはできません。
これらは「働けない状態」と「働ける状態」という、相反する状況を対象としているためです。どちらか一方を選択して受給する形になります。
手続き期限で見る退職給付金と失業手当の違い
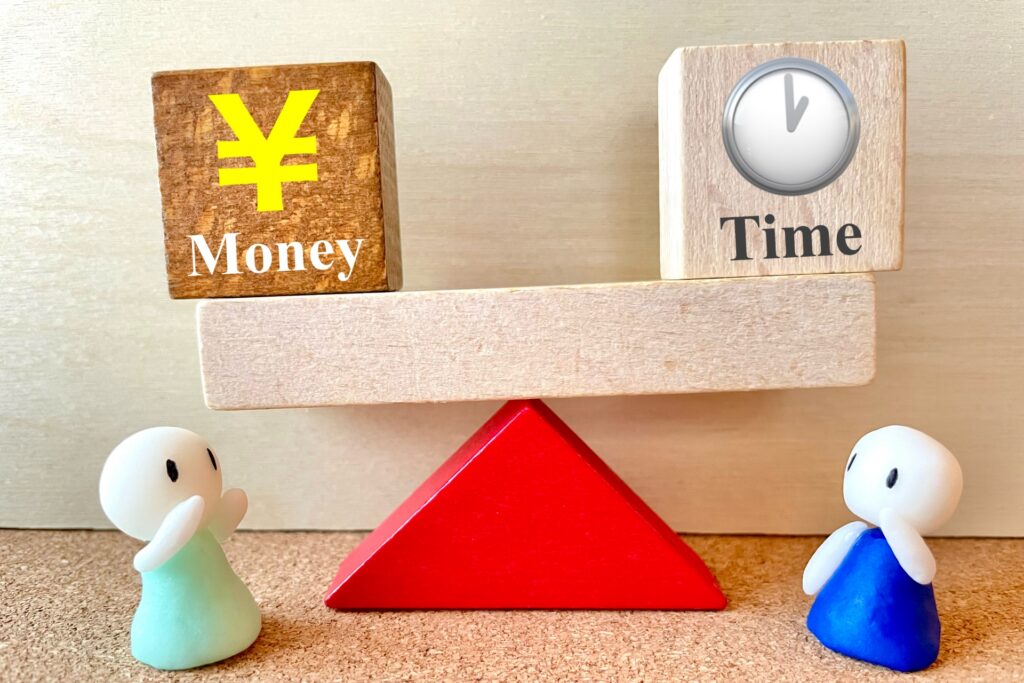
このセクションでは、より実践的な手続きと注意点に焦点を当てます。
ハローワークでの申請方法から、独立する上で最も重要な再就職手当の申請期限、さらには国民健康保険や年金などの各種手続きのタイムラインまでを網羅しています。
退職給付金はハローワークで手続き?
退職後に受け取れるお金の手続き先は、その種類によって異なります。
特に「退職給付金」という言葉が指す範囲が広いため、どこで何を申請するのかを正確に把握しておくことが大切です。
- 失業手当・再就職手当など雇用保険関連:これらの手続きは、すべてあなたの住所地を管轄するハローワークで行います。会社から交付される「離職票」などの必要書類を持参して、求職の申し込みを行うことから始まります。
- 傷病手当金(健康保険):こちらは、あなたが加入していた健康保険組合や協会けんぽが申請先です。申請書には、医師の証明が必要となるため、医療機関との連携も求められます。
なお、退職金(会社独自のもの)については、勤務先の人事部や総務部が手続きの窓口です。
通常、退職手続きの一環として会社側から案内があります。
このように、申請先は一つではありません。
自分がどの制度を利用したいのかを明確にし、それぞれ正しい窓口で手続きを進める必要があります。
申請期限1か月!再就職手当の注意点
独立を目指す方にとっての切り札とも言える再就職手当ですが、申請には厳格な期限が設けられており、これを逃すと受給できなくなるため細心の注意が求められます。
最も大切なルールは、「事業を開始した日(開業届の提出日など)の翌日から1か月以内」に申請を完了させることです。
例えば、6月1日に開業届を提出した場合、7月1日までにハローワークへ再就職手当の申請書を提出しなければなりません。
起算日は6月2日です。1か月は「起算日に応当する日の前日」に満了するので、 7月1日が最終日となります。
※期間末日が役所の閉庁日に当たる場合は、原則、翌開庁日が期限になります(民法の期間満了の特例)。
参考:総務省 申請期間の末日が「行政機関の休日」に当たる場合の申請期限の取扱い
開業準備で忙しい時期と重なるため、うっかり期限を過ぎてしまうケースも少なくありません。
前述の通り、自己都合退職の場合は、待期期間満了後の最初の1か月に開業すると原則対象外になるため、この1か月が経過した後に開業し、そこから1か月以内に申請するというスケジュールを組む必要があります。
退職後の主な手続き期限チェックリスト
退職後は、公的な給付金の申請以外にも、健康保険や年金の切り替えなど、期限が定められた手続きが数多く存在します。
タイミングを逃すと不利益を被る可能性があるため、一覧で確認しておきましょう。
| 手続きの期限 | 手続きの内容 | 主な提出先 |
|---|---|---|
| 14日以内 | 国民健康保険・国民年金への切り替え | 市区町村役場 |
| 20日以内 | 退職後の健康保険「任意継続」の申出 | 健康保険組合・協会けんぽ |
| 1か月以内 | 開業届の提出(事業開始から) | 税務署 |
特に、健康保険は「国民健康保険に切り替える」か「会社の健康保険を任意継続する」かの選択が必要です。
任意継続は退職後20日以内と期限が短いため、事前に保険料を比較検討し、どちらにするか決めておくことをお勧めします。
退職給付金を受け取るデメリットと難所
公的給付金は退職後の大きな支えとなりますが、利用する上でのデメリットや、手続きにおける難所も存在します。
デメリット・注意点
- 扶養に入れない可能性がある:失業手当の受給額によっては、配偶者の社会保険の扶養に入れない場合があります。扶養から外れると、自分で国民健康保険と国民年金の保険料を納付する必要があり、家計全体の負担が増える可能性があります。
- アルバイト収入に制限がある:失業手当の受給中にアルバイトをする場合、収入額や労働時間によっては手当が減額されたり、支給が先送りされたりします。ルールが複雑なため、働く前に必ずハローワークに確認することが不可欠です。
手続きの難所
- 書類の不備や遅延:特に、会社から交付される「離職票」がなかなか届かない、記載内容に誤りがあるといったトラブルは少なくありません。これが原因で、ハローワークでの手続きが遅れてしまうことがあります。
- 制度の切り替えタイミング:傷病手当金と失業手当は同時に受給できません。体調が回復し、働ける状態になったタイミングで、健康保険から雇用保険へスムーズに手続きを切り替える必要がありますが、この判断や手続きが煩雑に感じられることがあります。
これらの点を事前に理解しておくことで、予期せぬトラブルを避け、計画的に制度を活用できます。
複雑な手続きに不安なら専門サポートの活用も
近年、企業の退職金制度の変化や早期退職の増加、またインフレによる将来への経済的な不安などを背景に、退職後に受け取れる公的な給付金を最大限活用したいというニーズが高まっています。
しかし、ここまで見てきたように、制度は複雑で手続きには多くの注意点が伴います。
こうした状況で、一人で手続きを進めることに不安を感じる方に向けて、「退職給付金サポート」といった専門サービスも登場しています。
例えば「退職前アドバイザー」のようなサービスは、社会保険給付金の申請に関する助言を提供してくれます。
主な特徴は以下の通りです。
- 相談者の97%が受給済
- 平均受給額400万円~
- 最長28カ月の長期受給にも対応
- 申請の手間を任せ、再就職・独立準備に専念できます
特に、費用が「後払い」で、万が一給付金が全く受け取れなかった場合に「全額返金保証」が付いている点は、利用者が金銭的なリスクを負わずに相談できる大きなメリットと言えるでしょう。
一方で、利用を検討する際は、サービスが提供するのはあくまで申請に関する「助言」であり、「申請代行」ではないことを理解しておく必要があります。
より手厚いサポートを求める場合の選択肢として、こうした専門サービスの活用も検討できます。
退職給付金に関するよくある質問
ここでは、退職後の給付金に関して多くの方が抱く疑問についてお答えします。
Q. 開業すると失業手当はすぐに止まりますか?
開業届を提出するなど事業を開始したとみなされると、「失業状態」ではなくなるため、失業手当の支給は止まります。
ただし、先ほども取り上げたように、一定の要件を満たしていれば、残りの給付日数に応じた「再就職手当」を受け取れる可能性があります。
Q. 扶養に入ったまま失業手当はもらえますか?
失業手当の基本手当日額が一定額以上の場合、被扶養者として認定されないのが一般的です。
収入基準は健康保険組合によって異なりますが、多くは日額3,611円(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は5,000円)が目安とされています。
この額を超えて受給する場合は、扶養から外れる手続きが必要です。
参考:全国健康保険協会「被扶養者とは?」
Q. 国民健康保険と任意継続、どちらが得ですか?
一概にどちらが得とは言えず、個人の状況によって異なります。
国民健康保険料は前年の所得に基づいて市区町村が計算しますが、任意継続の保険料は在職時の標準報酬月額が基準となります。
一般的に、扶養家族が多い場合は任意継続の方が有利になる傾向がありますが、まずは市区町村役場と健康保険組合の両方で保険料を確認し、比較検討することが不可欠です。
会社を退職した後に直面する手続きの中でも、健康保険の選択は特に悩ましい問題の一つです。 これまで会社が手続きしてくれていた健康保険は退職日の翌日に資格を失い、自身で新たな保険に加入し直さなければなりません。 主な選択肢と[…]
まとめ:退職給付金と失業手当の違い
この記事では、独立を目指す方に向けて、退職給付金と失業手当の違いについて多角的に解説しました。
これらの制度は名称が似ていますが、支給元、目的、受給条件が全く異なることをご理解いただけたかと思います。
独立や自営を前提とするあなたにとって、最も重要なのは、これらの違いを理解した上で、自身の状況に合わせた最適な「順番」で制度を活用する計画を立てることです。
健康状態に不安があるなら傷病手当金を、元気にすぐ事業を始めたいなら再就職手当を狙う、といった戦略的な視点が求められます。
退職後の手続きには14日、20日、1か月といった厳しい期限が設定されているものも多いため、事前にスケジュールを把握しておくことが、円滑な独立への鍵となります。
この記事で得た知識を元に、まずはご自身の状況を整理し、必要な手続きは何かを確認することから始めてみてください。
あなたの新しいキャリアが、経済的な不安なくスタートできることを願っています。






