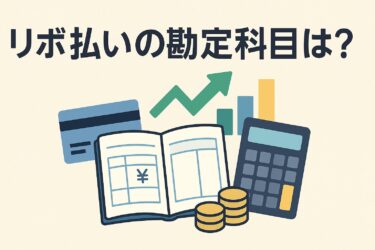定額減税の通知が届き、安堵した個人事業主の方も多いのではないでしょうか。
しかし、その後の仕訳でどの勘定科目を使えば良いのか、頭を悩ませていませんか。
もし処理を間違えれば、本来受けられるはずの恩恵が減ってしまう可能性もあります。
この記事では、個人事業主が定額減税の給付金を受け取った際の、正しい勘定科目と具体的な仕訳方法を分かりやすく解説します。
この記事を読むことで、以下の点が明確になります。
- 定額減税の調整給付に使うべき正しい勘定科目
- 具体的な仕訳の記帳例
- 具体的な仕訳の記帳例会計ソフトでの入力方法
広告・PR
⚠️ 確定申告の準備はお済みですか?
2月、3月になってから領収書を整理するのはもう終わり!
スマホでスワイプするだけの次世代アプリ「Taxnap」なら、今からでも間に合います。
※副業・フリーランス・個人事業主向け
年払い契約で招待コード【 SC5RJEQK 】
を入力すると1,500円割引で利用できます。
【個人事業主向け】定額減税の勘定科目
個人事業主の方が定額減税の給付金を受け取った際の会計処理には、事業特有の考え方が必要になります。
会社員とは異なり、事業と個人の資金の境界を正しく帳簿上で示すことが大切です。
このセクションでは、給付金の性質を理解した上で、どの勘定科目を選び、どのように記帳すればよいのか、基本的なルールを一つずつ確認していきましょう。
定額減税の調整給付の勘定科目は?
定額減税において減税しきれない分として受け取るお金は、制度上、「調整給付」や「不足額給付」と呼ばれています。これは事業の売上ではありません。
あくまで事業主個人の税負担を軽減するための、個人的な性質を持つお金です。
したがって、会計処理で用いるべき勘定科目は「事業主借(じぎょうぬしかり)」が最も適切と考えられます。
もし、これを「雑収入」などの事業収入にあたる科目で処理してしまうと、課税対象の所得として計算されてしまう恐れがあるからです。
その結果、追加で所得税や住民税、国民健康保険料が発生し、せっかくの減税効果が薄れてしまうことになりかねません。
この給付金が非課税とされる根拠は、法律によって定められています。
知恵袋でよく見る個人事業主の悩み
Yahoo!知恵袋などのQ&Aサイトを見ると、多くの個人事業主の方が同様の疑問を抱えていることが分かります。
「このお金は非課税と聞いたけど、帳簿にどう書けばいいの?」「雑収入で処理してしまったけど大丈夫?」といった投稿は後を絶ちません。
また、「間違った処理をすると税務調査で指摘されるのではないか」という不安の声も多く見受けられます。
これらの悩みは、個人事業主特有の会計ルールと、今回の制度の複雑さが相まって生まれるものです。
この記事では、そうした不安を解消できるよう、根拠と共に正しい処理方法を解説します。
個人事業主の定額減税は4万円ですか?
はい、納税者本人一人あたり合計4万円の減税が基本となります。
この4万円の内訳は、以下の通りです。
- 所得税から3万円
- 個人住民税から1万円
また、同一生計配偶者や扶養親族がいる場合は、その人数分の減税額が加算されます。
例えば、扶養している配偶者と子どもが一人いる場合、合計3人分の減税が適用されます。
計算式は「4万円 × 3人 = 12万円」となり、合計12万円の税負担が軽減される仕組みです。
ただし、これはあくまで納めるべき税金から差し引かれる「減税」が基本です。
納める税額が4万円に満たない場合に、その差額が調整給付として支給されます。
具体的な帳簿の付け方と仕訳記帳
実際に調整給付が事業用の普通預金口座に振り込まれた際の、具体的な帳簿の付け方を解説します。
ここでは、3万円が振り込まれたケースを例に見ていきましょう。
仕訳は以下のようになります。
| 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
| 普通預金 | 30,000円 | 事業主借 | 30,000円 | 定額減税 調整給付 |
この仕訳は、「事業用の普通預金という資産が3万円増え(借方)、その理由は事業主個人から3万円を借り入れた(貸方)から」という取引を示しています。
摘要欄には「定額減税」など、後から見て内容が分かるように記載しておくと親切です。
この記帳により、課税所得に影響を与えることなく、口座の残高を正しく合わせられます。
事業主貸と事業主借は、個人事業主特有の勘定科目です。 正しく会計処理をする上で、この2つの勘定科目の使い方を押さえておく必要があります。 この記事では、事業主貸と事業主借の勘定科目の仕訳例や決算時の相[…]
弥生会計などソフトでの入力方法
弥生会計やfreee、マネーフォワード クラウドといった会計ソフトを利用している場合も、考え方は同じです。
多くの場合、銀行口座と連携していれば、調整給付の入金は自動で取引データとして取り込まれます。
その未処理の取引データに対して、正しい勘定科目を設定する作業が必要です。
入力の手順
- 会計ソフトにログインし、銀行口座の取引明細を確認します。
- 自治体からの入金データ(例:「〇〇ク チョウセイキュウフ」など)を見つけます。
- 取引の登録画面を開き、勘定科目の選択欄で「事業主借」を検索し、選択します。
- 摘要欄に「定額減税 調整給付」などと入力し、取引を登録します。
ソフトウェアによっては、AI機能が勘定科目を推測して「雑収入」などを提案してくることも考えられます。
しかし、その提案に頼るのではなく、ご自身で内容を確認し、必ず手動で「事業主借」に設定することが大切です。
個人事業主として事業を運営する上で、正確な会計処理やスムーズな税務申告は欠かせません。 しかし、日々の記帳や青色申告の準備は大変な作業となりがちです。 そこで、本記事では、初心者の方でも扱いやすい会計ソフトや無料で利用できる会計[…]
まとめ:定額減税の勘定科目の最終確認
今回の記事では、個人事業主の定額減税の会計処理について解説しました。
個人事業主本人が受け取る調整給付に関する定額減税の勘定科目は、非課税の性質を持つため「事業主借」で処理します。
これを誤って事業収入としてしまうと、不要な税負担が生じる恐れがあります。
会計記帳の参考になれば幸いです。
参考:国税庁 定額減税 特設サイト