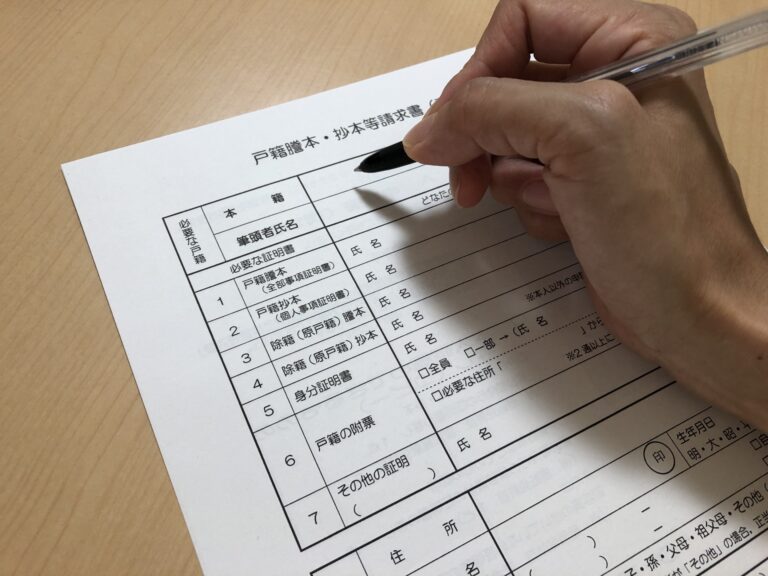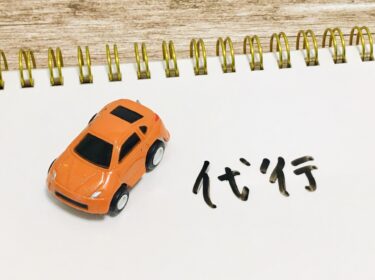本記事では、戸籍謄本取得にかかる費用を適切に処理するための勘定科目について解説します。
また、仕訳の具体例についてもご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
無料診断ツール
✅ 会計ソフト選びで迷っていませんか?
「結局どれが自分に合うの?」
そんな悩みは、当サイト独自の「無料診断」で解決しましょう。
※3つの質問に答えるだけで完了します
スマホ派? PC派? 農業?
10秒で診断して、失敗しない選択を。
戸籍謄本の勘定科目
戸籍謄本を取得する際、個人事業主の方がどの勘定科目を使用すればよいか悩むことがあるでしょう。結論から言うと、戸籍謄本の取得費用は「租税公課」として処理するのが一般的です。
租税公課とは、国や地方公共団体に支払う税金や手数料を含む勘定科目です。
戸籍謄本の取得費用も地方公共団体に対して支払われる手数料であるため、この勘定科目が適しています。
参考記事:租税公課とは?経費にできる税金や仕訳例
戸籍謄本の仕訳例を具体的に解説
戸籍謄本を取得する方法は複数ありますが、取得方法によって使用する勘定科目や取得金額が異なるケースがあるため、以下に3つの取得方法について取り上げます。
市役所に直接出向いて取得する
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 租税公課 | 450 | 現金 | 450 |
コンビニのマルチコピー機で取得する
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 租税公課 | 400 | 現金 | 400 |
この仕訳については、市役所で取得する際の仕訳と同じ形ですが、コンビニで戸籍謄本を取得する場合、手数料が異なるケースがあります。
例えば、福岡市の場合ですと、コンビニで戸籍全部(個人)事項証明書を取得することができ、手数料も50円安くなります。
定額小為替を使って郵送で取り寄せる
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 租税公課 | 450 | 現金 | 450 |
| 支払手数料 | 200 | ||
| 通信費 | 84 |
この仕訳例は、戸籍謄本を1通取得するのに、以下の費用がかかったと想定しています。
- 定額小為替・・450円
- 定額小為替購入の手数料・・200円
- 返信用封筒に貼る切手代・・84円
厳密には、郵送費用としての切手代も別途かかりますし、戸籍謄本を複数取得する場合は、その分費用がプラスされます。
仕訳の際は、経費計上できる金額に漏れがないようご注意下さい。
また、定額小為替を購入する際には、購入金額に関わらず一律200円の手数料がかかります。
定額小為替の詳細は、以下の記事でご説明していますので参考にして下さい。
戸籍謄本には消費税はかかる?
結論から言いますと、戸籍謄本には消費税はかかりません。
この費用は非課税です。
消費税の対象となる取引は、事業者が対価を得て行う資産の譲渡やサービスの提供です。
しかし、戸籍謄本の取得は、地方公共団体が提供する行政サービスの一環であり、消費税の課税対象には含まれません。
例えば、市役所や区役所で戸籍謄本を取得する際に支払う手数料は、非課税です。
このような行政サービスに対する手数料は、税法上、消費税を課さないことが定められています。
記事のまとめ
今回の記事では、戸籍謄本を経費計上する際の勘定科目と仕訳例について取り上げました。
以下に、記事の主なポイントをまとめます。
- 戸籍謄本の取得費用は「租税公課」として処理するのが一般的
- 取得方法によって金額が異なったり複数の勘定科目を使用することがある
- 戸籍謄本の手数料は非課税