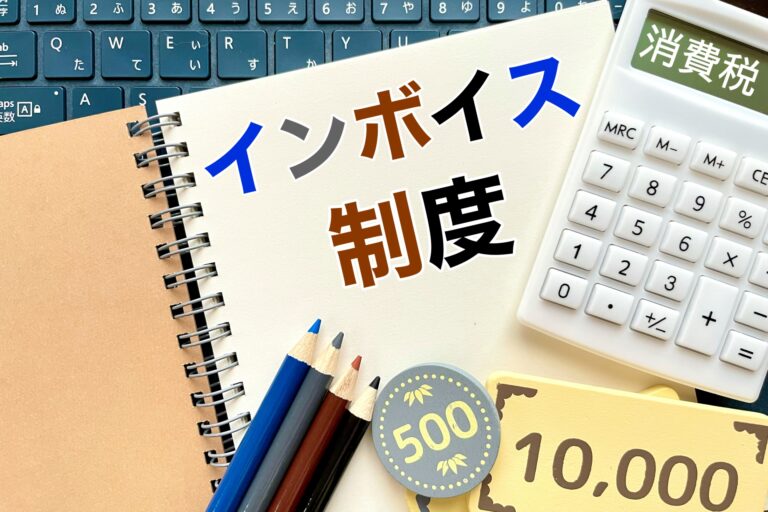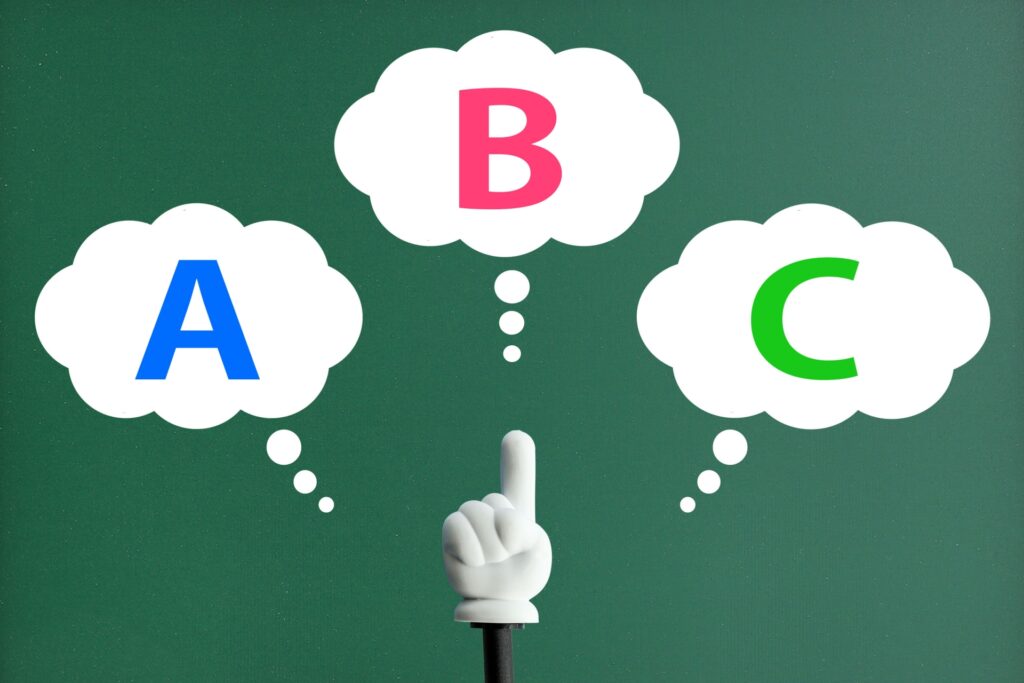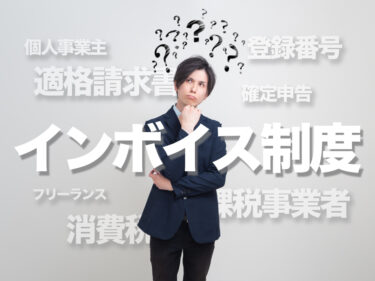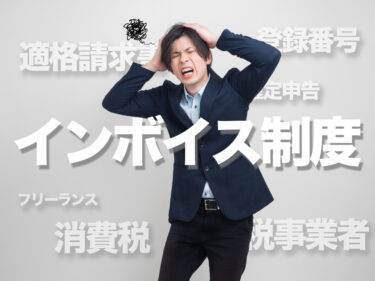インボイス制度が2023年10月から始まります。
この制度が導入されることで、免税事業者の個人事業主やフリーランスに大きな影響が生じることが予想されています。
今回の記事では、インボイス制度について分かりやすく解説するとともに、個人事業主やフリーランスに生じる可能性のある影響についても取り上げていますので参考にして下さい。
PR
⚠️ 確定申告、まだ終わってない方へ
「何から手をつければいいか分からない…」という方は、タックスナップの「丸投げ仕分け」を使うと、仕訳作業が一気に進みます。
私の場合は、 667件の取引が約2秒 で仕訳されました。
ただし、使用しているスマホや通信状況などにも左右されるため、まずは無料期間で動作確認してから継続利用を判断するのが安心です。
※自動仕訳後は「勘定科目の最終確認」だけは行うのがおすすめです。
※3/16まで、提出以外の機能は無料で試せます。
インボイス制度とは
インボイス制度とは、課税事業者が仕入税額控除を行うために適格請求書などの保存が求められる制度のことです。
インボイス制度の正式名称は、「適格請求書等保存方式」と言い、請求書などに一定の記載要件が求められます。
一定の記載要件を満たしている請求書等を保存することで、仕入れを行う課税事業者は仕入税額控除が受けられます。
一方で、この要件を満たした請求書等を発行するには、適格請求書発行事業者である必要があり、そのためには申請手続きが必要です。
免税事業者の場合、現状のままでは適格請求書が発行できないため、対応するには申請手続きをすることが求められます。
手続きをして適格請求書発行事業者になるだけであれば、問題がないように思うかも知れませんが、免税事業者が適格請求書発行事業者になると消費税の納税が必要となります。
これまで消費税を納める必要がなかった事業者にとっては、消費税を納める負担や手間が生じることになります。
事業者でない方からすると、すべての事業者は消費税を支払っていると思っていたかもしれません。
ですが、年間売上高1000万円以下などの条件に当てはまる小規模事業者であれば、消費税の申告は不要です。
ですから、売上により受け取った消費税が仕入れなどで支払った消費税よりも多ければ、消費税を納付せずに自分の手元に置いておけます。
これだけ聞くと「小規模事業者は得をしている」と思うかも知れません。
確かに顧客から受け取った消費税を国に納付しないのは違和感がありますが、小規模事業者が事業を続けていく上では仕方がない面もあります。
小規模事業者は一般的に、「買い手」「売り手」のどちらにも弱い立場にあります。
例えば、仕事を発注してくれる業者から値下げを求められた場合、今後の仕事がなくなることを恐れ値下げに応じてしまうケースは多いでしょう。
また、 消費税分を顧客に転嫁するのも難しいケースが多いはずです。
このように小規模事業者の多くは、厳しい価格競争にさらされていることから、消費税の納税を免除されているのは、ある意味、仕方がない面もあります。
しかし、今後は適格請求書発行事業者が発行する請求書でなければ、取引先は消費税の控除を受けられなくなるため、様々な影響が懸念されているのです。
インボイス制度による影響
インボイス制度には、様々な影響が懸念されますが、もっとも大きな影響は、インボイスに対応しない事業者との取引が減っていく可能性が高いことでしょう。
取引相手から見ると、仕入れなどで支払った消費税10%分の控除が受けられないのは、大きなデメリットです。
ダイレクトに業績に影響が出るため、インボイスに対応してる業者と取引するようになるはずです。
年間売上高が1000万円以下の場合でも、インボイス業者になれますが、インボイス業者になってしまうと、今度は消費税を国に納めなければなりません。
小規模事業者にとって10%は非常に大きな影響があります。
ぎりぎりで経営をしているような事業者であれば、最悪の場合、倒産のリスクもあるでしょう。
このように、 インボイス制度は、小規模事業者に深刻な影響を与えてしまう可能性があるのです。
売上高1000万円以下の免税事業者の選択肢は2つ!
インボイス制度の発足に伴い、小規模事業者の選択肢は2つです
- このまま免税事業者でいる
- 課税業者になる
売上高1000万円以下でも課税事業者にはなれますが、メリットとデメリットを比較考慮して慎重に決定する必要があるでしょう。
では、このまま免税業者でいることと課税業者になることには、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?
これから具体的に考えてみましょう。
免税事業者のままでいるメリットとは?
免税事業者のままでいることのメリットとしては、次の点が考えられます。
- 消費税の支払いが不要
- 面倒な会計処理が不要
消費税の支払いが不要
免税事業者のままでいるメリットは、ずばり、引き続き消費税の支払いを行わなくて良いことです。
現在の日本の財政状況を考えると、さらに消費税が上がる可能性がないとはいえません。
もし、さらに今後、消費税が上がった場合、消費税の支払いが免除されるのは大きなメリットでしょう。
現在でも、10%とかなり高い消費税を支払わなくても良いのはメリットですが、増税された場合、 さらなるメリットになります。
面倒な会計処理が不要
消費税の会計処理は面倒です。
例えば、取引の種類に応じて課税・非課税・免税・不課税の区分処理が求められたり、取引が軽減税率の対象であるかどうかなども確認して仕訳を切る必要があります。
こうした面倒な会計処理が不要なことも、免税事業者のメリットと言えるでしょう。
免税事業者のままでいるデメリットとは?
免税事業者のままでいることのデメリットは主に3つです。
- 取引先が減るかもしれない
- 値引きを求められるかもしれない
- 売り上げが減るかもしれない
それぞれのデメリットについてわかりやすく説明します。
取引先が減るかもしれない
免税事業者のままでいると、仕入税額控除に必要な適格請求書の発行ができません。
適格請求書の発行がないと、取引先は仕入税額控除の利用ができないので、結果的に課税事業者と取引する場合と比べて多くのコストがかかります。
例えば、免税業者に税込み330,000円の仕事を依頼した場合、消費税分である30,000円の控除を受けられません。
つまり、課税業者に依頼するよりもコストが高くなってしまうのです。
取引先にとっては自分の会社のせいではなく、仕事を依頼する会社の都合によってコストが大きくなってしまうのは悪い印象につながります。
結果として、インボイス制度に対応しないと、取引先が減ってしまう可能性は十分にあるのです。
値引きを求められるかもしれない
インボイス制度に対応しないと取引先の負担が増えるので、値引きを求められるかもしれません。
取引先からみれば10%多くのコストが発生するため、ある意味当然ともいえます。
また、インボイス制度をきっかけに、いままで値引き交渉をしなかった取引先が、ここぞとばかりに値引き交渉をしてくるのも考えられますので、その場合は大きなデメリットになるでしょう。
売り上げが減るかもしれない
取引先が減ってしまったり値引き交渉に応じざるを得なければ、これらのことが原因で売上が減ってしまう可能性が十分にあります。
もし500万円の売り上げのうち、10%が減ってしまうと50万円の減収になります。
大企業から見れば大した数字ではないかもしれませんが、個人事業主などの小規模事業者にとっては死活問題になる可能性があるでしょう。
売上高を補填するためには、より多くの仕事を取る必要がありますが、業務量過多になってしまう可能性もあります。
また、いつ取引先が減るかわからない恐怖とも戦うことになるでしょう。
課税業者になった場合のメリットとは?
課税業者になった場合のメリットは、適格請求書の発行ができるようになることです。
適格請求書の発行ができることによって、取引先は仕入税額控除を受けられるので、今まで通りの取引を継続してくれる可能性が高まります。
結果として、売上の維持に貢献してくれることになるでしょう。
課税業者になることのデメリットとは?
課税業者になることのデメリットは主に3つです。
- 消費税を納税する必要がある
- 消費税の申告や適格請求書にフォーマットを変えるなどの手間がかかる
- 手元に残るお金が少なくなる可能性がある
それぞれのデメリットについて、わかりやすく説明します。
消費税を納税する必要がある
当然ですが、課税事業者になると消費税の納税をする必要があります。
いままで支払う必要がなかったものを支払わなければならなくなってしまいますし、売り上げの10%という大きな金額を負担しなければなりません。
大きな負担になってしまうのは、課税業者に変更するデメリットと言えるでしょう。
消費税の申告や適格請求書にフォーマットを変えるなどの手間がかかる
課税事業者に変更することによって、消費税の申告が新たに必要になりますので、会計処理や申告の手間がかかります。
特に初めて消費税の申告する場合、戸惑う可能性が高いです。
また、適格請求書にはフォーマットがあるため、今までの請求書とフォーマットを変更しなければなりません。
このように課税業者に変更すると、様々な事務的な負担が増えるのはデメリットになるでしょう。
手元に残るお金が少なくなる可能性がある
当然ですが、課税業者に変更することによって、売り上げの10%が消費税として消えます。
今まで手元に残っていたものが少なくなるのは大きなデメリットです。
いままでの収入を維持するには、単価を上げるか10 %増で仕事をするしかないでしょう。
どちらも決して簡単なことではないので、やはり課税業者に変更するデメリットといえます。
小規模事業者がとるべき方策は3つ!
インボイス制度が始まると、 小規模事業者は、今まで通りの環境で仕事をすることは難しくなります。
小規模事業者が選択しなければならない道は3つです。
- 免税事業者として業務を続ける
- 値下げをする
- 課税事業者に変更する
それぞれの選択肢についてみていきましょう。
免税事業者として業務を続ける
インボイス制度が開始した後も、免税事業者として業務を続けることは可能です。
もちろん、取引業者は仕入税額控除を受けられないので、取引先が減ってしまうなどのリスクはありますが、業務自体は免税事業者として行えます。
もし、商品やサービスを提供するにあたり、他にない強みやスキルなどがあれば、取引先を減らすことなくいままで通り業務を続けていくことも可能でしょう。
値下げをする
免税事業者として営業すること自体には問題がないので、取引先を減らさないためにも、仕入税額控除を受けられない分の値下げをして営業をするのも一つの方法です。
ただしこの方法だと取引先を増やすなどの対策が必要になります。
課税事業者に変更する
インボイス制度に対応するために、課税事業者に変更するのが最もオーソドックスな対応方法でしょう。
もちろん課税されるので、売上を増やすなどの対策は必要になります。
まとめ
今回は、インボイス制度について説明しました。
インボイス制度は、小規模事業者にとって死活問題になりかねません。
事前に内容についてしっかり理解し、時間をかけて対策する必要があります。
ぜひ今回の記事を参考にしていただき、インボイス制度の理解を深めていただければ幸いです。
🔧 当サイト独自の無料診断ツール(個人情報の登録不要)
- 一般家庭の平均と比較して「高い支出」を1分でチェック。勘定科目も表示!(個人事業主・フリーランス向け)
-
🧾 会計ソフト診断あなたの業種・規模に合う会計ソフトを最短で判定