個人事業主の方がふるさと納税を検討する際、適切なシミュレーションを行うことは、節税のメリットを最大限に活かすために不可欠な手続きです。
会社員とは収入の仕組みが異なるため、自分の正確な上限額を把握することに不安を感じる方も少なくありません。
しかし、正しい知識と手順さえ身につければ、誰でも迷うことなく計算できます。この記事では、忙しい個人事業主の方に向けて、失敗しない計算方法と目安を分かりやすく解説します。
本記事のポイント
-
入力する数字は売上ではなく経費や控除を差し引いた事業所得である
-
個人事業主におすすめのシミュレーションツールと正しい入力手順
-
事業所得ごとの寄付上限額の目安がひと目でわかる安全な早見表
PR
⚠️ 確定申告、まだ終わってない方へ
確定申告がまだ終わっていない方は、まず仕訳を片付けると一気に気持ちがラクになります。特にタックスナップの「丸投げ仕分け」は、迷いがちな仕訳作業を一気に進められる機能です。
私の場合は、 667件の取引が約2秒 で仕訳されました。ただし端末や通信状況などにより、処理の時間は異なる可能性があります。
3/16までは提出・印刷以外を無料で試せます。無料のうちに使ってみて、合うかどうかを確認してみてください。
※仕訳後に、勘定科目や金額は念のため確認しておくと安心です。
※3/16まで、提出以外の機能は無料で試せます。
クーポンは、初回登録時に入力しておくとスムーズです。合わなければ無料期間中に解約できます。
▶ 無料でタックスナップを試してみる(3/16まで) ※「丸投げ仕分け」の詳細や体験談を確認できる記事はこちら個人事業主のふるさと納税シミュレーションと計算手順

ふるさと納税を効果的に活用するためには、まずご自身の寄付上限額を正確に把握することから始まります。
ここでは、個人事業主ならではの計算ルールや、シミュレーションツールを利用する際の具体的な入力ポイントについて、順を追って解説していきます。
ふるさと納税の金額の計算方法は?
個人事業主がふるさと納税の限度額を計算する際、最も重要なのは所得の定義を正しく理解することです。
会社員は給与収入(額面)を基準に計算しますが、個人事業主は事業所得を基準にします。
具体的には、以下の計算式で導き出される金額を使用します。
- 事業収入(売上) - 必要経費 - 青色申告特別控除 = 事業所得
この事業所得から、さらに基礎控除や社会保険料控除などの所得控除を差し引いた金額が課税所得となり、これをもとに寄付上限額が決定されます。
つまり、売上が同じ金額であっても、経費の多寡によって所得は変動し、それに伴いふるさと納税の上限額も変わるのです。
まずは、昨年の確定申告書や今年の帳簿を整理し、この事業所得を正確に算出することから始めましょう。
計算シミュレーションの基礎
シミュレーションを行うための基礎知識として、どの数字をツールのどの項目に入力すべきかを知っておく必要があります。
一般的なシミュレーターには年収(給与収入)と所得の入力欄が用意されていますが、専業の個人事業主であれば年収欄には0を入力します。
そして、その他の所得や事業所得の欄に、先ほど計算した事業所得の金額を入力します。
ここで陥りやすい間違いが、経費を引く前の売上を入力してしまうことです。
これを誤って入力すると、本来よりも大幅に高い上限額が表示されてしまい、結果として自己負担額が2,000円を超えて損をしてしまうリスクがあります。
必ず利益(所得)を入力するように注意してください。
事業所得シミュレーションのポイント
より精度の高いシミュレーションを行うためのポイントは、青色申告特別控除(最大65万円)の扱いです。
シミュレーションツールに入力する事業所得は、原則として青色申告特別控除を差し引いた後の金額を用います。
確定申告書の控えをお持ちであれば、所得金額のセクションにある事業(営業等)という欄の記載数字をそのまま使用するのが最も確実です。
もし年の途中で、まだ確定申告書が作成できていない場合は、現時点での売上から経費を引き、さらに65万円(青色申告の場合)を引いた額を見込みの事業所得として計算に用いてください。
このひと手間をかけることで、より実態に近い上限額を知ることができます。
個人事業主に対応したシミュレーションのおすすめサイト5選

個人事業主のふるさと納税において、最も重要なのは「正確な上限額の把握」と「実務効率の良いポータルサイト選び」です。
会社員と異なり、自分で確定申告を行う個人事業主は、税金の計算が複雑になりがちです。そこで、「事業所得」や「小規模企業共済」などの項目に対応した詳細なシミュレーターを提供しているサイトを選ぶことが失敗しないコツです。
また、2025年10月の制度改正により、ポータルサイト独自のポイント付与や、寄付額に応じたギフト券プレゼントといった「過度な還元競争」は終了しました。
そのため、今後は「ポイント還元率」ではなく、「シミュレーションの精度」「サイトの使いやすさ」「事業に役立つ返礼品の品揃え」という本質的な基準でサイトを選ぶのが、賢い事業主の選択です。
ここでは、特に個人事業主にとって使い勝手が良く、実務的なメリットが大きい主要5サイトを厳選してご紹介します。
1. 楽天ふるさと納税
【詳細シミュレーターの精度が抜群!複雑な所得にも対応】
楽天ふるさと納税の最大の強みは、なんといっても「詳細版シミュレーター」の精度の高さです。
シミュレーション機能は非常に高性能で、事業所得だけでなく、株取引による「譲渡所得」や「配当所得」、不動産収入なども項目別に細かく入力可能です。
入力項目は多く感じるかもしれませんが、その分、複雑な収入源を持つ方でも限りなく正確な上限額を算出できるため、時間をかけて入力する価値は十分にあります。
また、楽天市場と同じID・決済情報を使えるため、備品の購入などで普段から楽天を利用している事業主であれば、管理の手間が増えない点も大きなメリットです。
-
シミュレーション機能: 非常に詳細(譲渡・配当・不動産所得に対応)
-
主な取扱品目: オールジャンル(食品、日用品、旅行、家電など網羅性No.1級)
-
おすすめポイント:
-
複数の所得がある場合でも、精度の高い上限額計算が可能。
-
普段の楽天IDで管理できるため、事務処理がスムーズ。
-
公式サイト:https://www.rakuten.co.jp/
2. さとふる
【配送スピードと管理のしやすさ重視!初心者にも優しい設計】
「さとふる」のシミュレーションツールは、個人事業主にとって非常に親切な設計になっています。特に「詳細シミュレーション」機能では、「給与所得者」と「個人事業主・副業のある方」というタブが明確に分かれているのが特徴です。
このタブを切り替えるだけで、確定申告書のどの項目を参照すればよいかがガイド付きで表示されます。また、個人事業主の節税対策として定番の「iDeCo」や「小規模企業共済等掛金控除」の入力欄も分かりやすく配置されているため、迷うことなく入力を進められます。
-
シミュレーション機能: 個人事業主専用タブがあり、確定申告書を見ながら入力しやすい。
-
主な取扱品目: 食品(特に肉・米・果物)、日用品。
-
おすすめポイント:
-
配送が早い(「最短1週間」や「当日発送」対応品もあり、年末の駆け込みにも安心)。
-
「配送カレンダー」や「マイステップ」機能で、配送状況や手続きの進捗を一目で管理できる。
-
公式サイト:https://www.satofull.jp/
![]()
3. ふるさとチョイス
【掲載数No.1!ニッチな特産品や体験型を探すなら】
掲載自治体数・返礼品数ともに日本最大級を誇る老舗サイトです。税理士監修の「詳細シミュレーション」では、住宅ローン控除など複数の控除も考慮した、より精度の高い計算に対応しています。
他のサイトにはないニッチな伝統工芸品や、現地での体験型チケットなども豊富に取り扱っています。「単なるモノ」ではなく、地域産業への応援や、事業の視察を兼ねた旅行など、経営者視点でのお金の使い方をしたい事業主におすすめです。
-
シミュレーション機能: 精度が高く、専門家(税理士)監修の安心感がある。
-
主な取扱品目: 圧倒的な品揃え(他サイトにない隠れた逸品も多数)。
-
おすすめポイント:
-
圧倒的な掲載数で、欲しいものが必ず見つかる。
-
伝統工芸品や体験型返礼品など、質の高い「コト消費」が充実。
-
公式サイト:https://www.furusato-tax.jp/
4. ふるなび
【家電が欲しいならここ!仕事環境の充実に最適】
「ふるなび」は、家電製品の取り扱いが非常に充実しているのが特徴です。パソコン、掃除機、空気清浄機など、仕事場の環境改善に役立つアイテムを返礼品として探している個人事業主には打ってつけのサイトです。
ポイント還元などのルールが厳格化された現在において、「実用的なモノ(家電)」で還元を受けることは、最も合理的で満足度の高い選択肢の一つと言えます。
-
シミュレーション機能: 控除上限額の目安が分かりやすい標準的な設計。
-
主な取扱品目: 電化製品(PC、キッチン家電)、旅行券、食品。
-
おすすめポイント:
-
家電のラインナップが豊富で、実質的な設備投資(環境改善)として活用できる。
-
高額な返礼品も多く、控除枠が大きい事業主でも選びやすい。
-
公式サイト:https://furunavi.jp/
5. マイナビふるさと納税
【Amazon Pay対応で決済がスムーズ】
就職・転職サイトでおなじみのマイナビが運営するサイトです。「Amazon Pay」での支払いに対応しており、Amazonアカウントを持っていれば面倒な入力なしで寄付が完了する手軽さが魅力です。
普段Amazonをよく利用し、Amazonアカウントに決済情報を集約している事業主にとっては、クレジットカード情報を新たに入力する手間が省け、スムーズに寄付を完了できます。
-
シミュレーション機能: シンプルで直感的に操作できる。
-
主な取扱品目: 肉、米、海産物などの人気食材が中心。
-
おすすめポイント:
-
Amazon Payが使え、Amazonアカウントでスムーズに決済可能。
-
サイトが見やすく、シンプルな操作性を好む方に最適。
-
公式サイト:https://furusato.mynavi.jp/
個人事業主向けふるさと納税の早見表
ツールへの入力が手間に感じる方のために、事業所得ごとの大まかな寄付上限額がわかる早見表を作成しました。
以下の表は、独身または共働きの個人事業主を想定した、ふるさと納税の寄付上限額の目安です。
ここでの事業所得は、売上から経費と青色申告特別控除を差し引いた後の金額を指します。
以下の数値は、基礎控除や社会保険料控除(所得の約15%程度と仮定)を考慮した一般的な概算値です。
国民健康保険料や国民年金は自治体や世帯状況により負担額が異なるため、安全のために数値を控えめに設定しています。
| 事業所得(利益) | 寄付上限額の目安 |
|---|---|
| 200万円 | 約15,000円 〜 20,000円 |
| 300万円 | 約30,000円 〜 40,000円 |
| 400万円 | 約45,000円 〜 60,000円 |
| 500万円 | 約65,000円 〜 80,000円 |
| 600万円 | 約85,000円 〜 100,000円 |
| 700万円 | 約110,000円 〜 130,000円 |
※この表はあくまで目安です。扶養家族の有無、iDeCo、医療費控除などの有無によって実際の限度額はさらに下がることがあります。必ず詳細なシミュレーションを行って確認することをお勧めします。
個人事業主のふるさと納税シミュレーションに関連した注意点
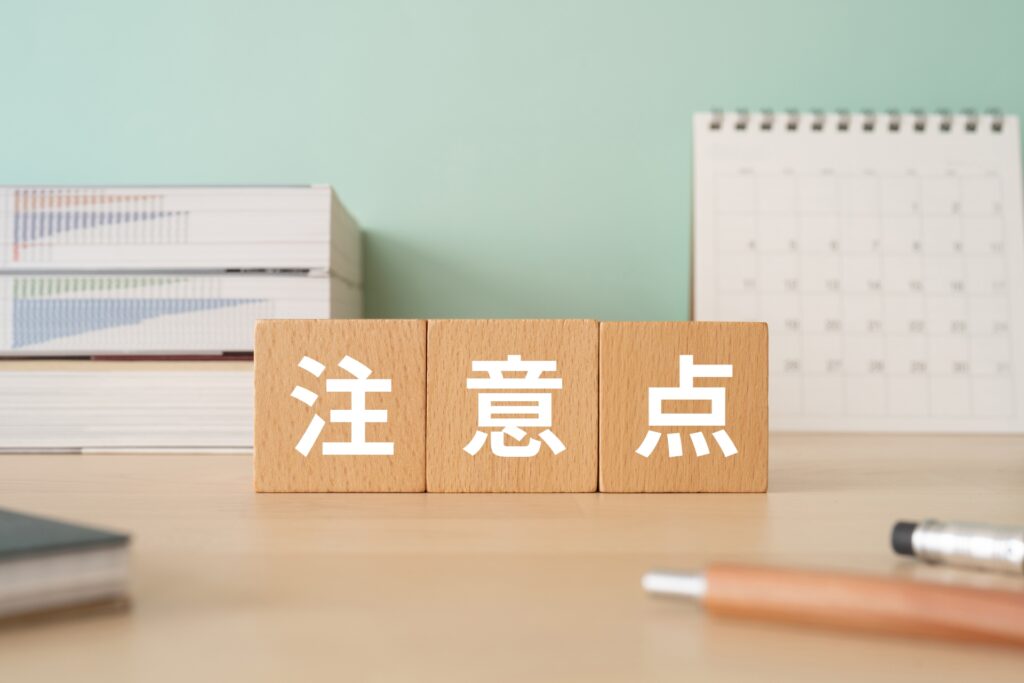
個人事業主には会社員にはないリスクや注意点が存在します。
ミュレーション結果を過信しすぎず、安全にふるさと納税を楽しむための重要なポイントを押さえておきましょう。
いつの所得で判断する?
ふるさと納税の限度額計算に使われる所得は、その年の1月1日から12月31日までの所得です。
つまり、2025年にふるさと納税を行う場合、基準となるのは2024年の所得ではなく、現在進行形である2025年の所得になります。
注意点としては、12月が終わるまで正確な年収が確定しないため、年の途中で上限ギリギリまで寄付をしてしまうと、年末に予想外の経費が発生して所得が減った場合に、上限額を超過してしまうリスクがあります。
したがって、11月頃までは前年の所得を参考にしつつ、少し余裕を持たせた金額(目安の8割程度)で寄付を行うのが安全策と言えます。
シミュレーションの精度を高める
シミュレーションの精度を高めるためには、確定申告書だけでなく住民税決定通知書を活用するのも有効な手段です。
毎年6月頃に自治体から届くこの通知書には、あなたの正確な所得割額が記載されています。
一般的に、ふるさと納税の寄付上限額は個人住民税所得割額 × 20%の計算式で概算することができます。
通知書に記載されている市町村民税と道府県民税の所得割額を合計し、それに0.2を掛けることで、昨年の実績に基づいたリアルな上限額が見えてきます。
所得が昨年と大きく変わらないのであれば、この数字を今年の目安として使うのも賢い方法です。
ふるさと納税をするデメリットは?
個人事業主がふるさと納税を利用する際、ワンストップ特例制度が使えない点はデメリットとして挙げられます。
会社員であれば確定申告なしで寄付金控除を受けられますが、個人事業主はそもそも確定申告が必須であるため、ワンストップ特例を申請しても無効になってしまいます。
そのため、必ず確定申告書の寄付金控除欄に寄付金額を記入し、寄付金受領証明書を保管(またはe-Taxでデータ連携)する必要があります。
手続きを忘れると、単に自治体に寄付をしただけになり、税金が控除されないという事態になりかねませんので、申告時期には十分な注意が必要です。
まとめ
個人事業主がふるさと納税で損をしないための最大のポイントは、売上ではなく、経費や青色申告特別控除を差し引いた事業所得を基にシミュレーションを行うことです。
正確な金額を知るには、さとふるや楽天ふるさと納税といった詳細入力が可能なツールを使い、確定申告書の控えを見ながら数値を入力するのが確実な方法と言えます。
また、年の途中で所得が変動するリスクや、社会保険料の個人差を考慮し、シミュレーション結果の限度額ギリギリを狙うのではなく、8割程度に抑えておくのが安全です。
正しい手順で計算し、確定申告で確実に手続きを行えば、ふるさと納税は個人事業主にとっても大きな節税メリットと楽しみをもたらしてくれます。
まずは昨年の確定申告書を手元に用意して、今年の寄付可能額をチェックすることから始めてみてはいかがでしょうか。






