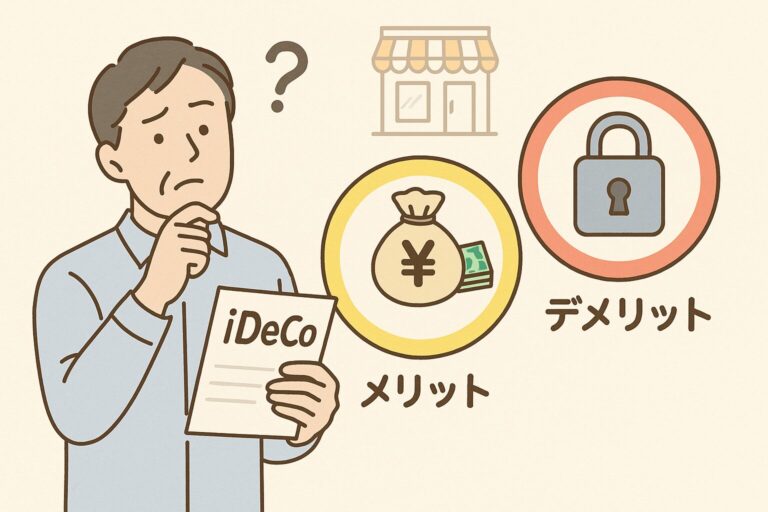「老後の年金が国民年金だけでは、生活できるか不安だ」
「今年の税金が高すぎる。経費以外で合法的に節税する方法はない?」
日々、事業の存続と将来への備えに頭を悩ませている個人事業主やフリーランスの方は多いのではないでしょうか。
会社員のように厚生年金がなく、退職金制度も自前で用意しなければならない自営業者にとって、老後資金の確保は切実な課題です。
そんな個人事業主にとって、最強の自分年金作りとなり得るのが、iDeCo(個人型確定拠出年金)です。
この記事では、iDeCoのメリット・デメリットを徹底解説します。
これを読めば、あなたが今iDeCoを始めるべきか、それとも別の手段を選ぶべきかが明確になるはずです。
本記事のポイント
- 個人事業主ならではの掛金上限と具体的な節税シミュレーション
- 資金拘束や手数料など事前に知っておくべきデメリット
- 「国民健康保険料は安くならない」という誤解の真相
- 「iDeCo」と「小規模企業共済」の最適な使い分けと併用戦略
- 退職金控除を活かして税金を抑える出口戦略
ファイナンシャルプランナー2級・AFP、日商簿記2級、行政書士の資格保有者の個人事業主。詳細は運営者情報をご覧ください。
PR
⚠️ 確定申告、まだ終わってない方へ
確定申告がまだ終わっていない方は、まず仕訳を片付けると一気に気持ちがラクになります。特にタックスナップの「丸投げ仕分け」は、迷いがちな仕訳作業を一気に進められる機能です。
私の場合は、 667件の取引が約2秒 で仕訳されました。ただし端末や通信状況などにより、処理の時間は異なる可能性があります。
3/16までは提出・印刷以外を無料で試せます。無料のうちに使ってみて、合うかどうかを確認してみてください。
※仕訳後に、勘定科目や金額は念のため確認しておくと安心です。
※3/16まで、提出以外の機能は無料で試せます。
クーポンは、初回登録時に入力しておくとスムーズです。合わなければ無料期間中に解約できます。
▶ 無料でタックスナップを試してみる(3/16まで) ※「丸投げ仕分け」の詳細や体験談を確認できる記事はこちら個人事業主にとってのiDeCo|基本情報と上限額

iDeCo(イデコ)とは、国が定めた「私的年金制度」の一つです。
加入者が毎月一定の掛金を拠出し、自分で選んだ金融商品(投資信託や定期預金など)で運用を行い、60歳以降に年金または一時金として受け取ります。
公的年金に加入している20歳以上65歳未満の方なら、原則として誰でも加入できますが、実はこの制度、個人事業主(国民年金の第1号被保険者)にとって最も優遇された設計になっています。
それは、圧倒的な「掛金枠」の大きさです。
iDeCoの最大の特徴は、職業によって毎月積み立てられる掛金の上限が異なる点です。
- 会社員(企業年金あり):月額2.0万円(他制度との併用枠による)
- 会社員(企業年金なし):月額2.3万円
- 公務員:月額2.0万円 ※
- 専業主婦(夫):月額2.3万円
- 個人事業主(第1号被保険者):月額68,000円
※公務員等の上限額は、2024年12月の制度改正により、従来の1.2万円から原則2万円に引き上げられました。
このように、個人事業主は月額68,000円、年間にして816,000円もの金額を拠出することが可能です。
これは、厚生年金がない自営業者の老後保障を厚くするための国の配慮と言えます。
この大きな枠を使い切ることで、資産形成のスピードも、後述する節税効果も、会社員とは桁違いの恩恵を受けることができるのです。
ただし、この「月額68,000円」という枠は、「国民年金基金」や「国民年金の付加保険料」との合算枠である点には注意が必要です。
これらを既に利用している場合、iDeCoで使える枠はその分少なくなります。
個人事業主にとってのiDeCo|強力な3つのメリット

「単なる貯蓄」や「NISA」ではなく、あえて資金拘束のあるiDeCoを選ぶ理由は、圧倒的な税制優遇にあります。
特に個人事業主にとっては、事業の利益を守るための強力な盾となります。
節税効果
iDeCoの最大のメリットは、支払った掛金の全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除の対象になることです。
個人事業主にとって、税金を減らすためには「経費」を積み上げるのが一般的ですが、無駄な経費を使って利益を減らしては本末転倒です。
しかし、iDeCoは「自分の将来のために貯金したお金」が、控除の対象となり、課税所得を減らしてくれるのです。
節税額のシミュレーション
例えば、課税所得(売上から経費と各種控除を引いた額)が400万円の個人事業主が、iDeCoの上限額である月額68,000円(年額816,000円)を拠出した場合を見てみましょう。
- 所得税(税率20%):816,000円 × 20% =163,200円の減税
- 住民税(税率10%):816,000円 × 10% =81,600円の減税
- 年間の節税合計:約244,800円
年間81.6万円を積み立てるだけで、約24万円もの税金が戻ってくる計算になります。
これは実質的に、拠出した瞬間に約30%の確定利回りが得られるのと同じことです。
どんなに優秀な投資信託でも、確実な30%のリターンを出すことは不可能です。
この強力な節税効果こそが、iDeCoをやるべき最大の理由の1つです。
ただし、個人事業主の私たちにとって注意すべき点もあります。
それは、「iDeCoをやると国民健康保険料も安くなる」という誤解です。
これは多くの自治体では当てはまりません。
なぜなら、国民健康保険料の計算に使われる所得は、通常、所得控除を引く前の金額(所得)を用いるためです。
iDeCoによる節税効果は、あくまで所得税・住民税に対して及ぶものと理解しておきましょう。
参考:国税庁 タックスアンサー No.1135 小規模企業共済等掛金控
運用益が非課税
通常、投資信託や株式の運用で得た利益には、約20.315%の税金がかかります。
しかし、iDeCoの口座内で得た利益はすべて非課税です。
本来税金として引かれるはずの20%分もそのまま再投資に回せるため、長期で運用すればするほど「複利効果」が働き、資産が雪だるま式に増えていきます。
この点はNISAと同様のメリットですが、所得控除とダブルで恩恵を受けられるのがiDeCoの強みです。
差押禁止財産として守られる
個人事業主にとって見逃せないのが、iDeCoの資産は法律(確定拠出年金法)によって差押禁止債権と定められている点です。
万が一、事業が傾いて自己破産せざるを得ない状況になったとしても、銀行預金や自宅、車などは処分の対象になりますが、iDeCoに積み立てた資産は原則として没収されず守られます。(※税金の滞納処分などを除く)
退職金制度のない個人事業主にとって、iDeCoは「最後のセーフティネット」としての機能も果たしてくれるのです。
ここに注意!iDeCoのデメリットとリスク

メリットが大きい反面、事業資金の流動性が命である個人事業主にとって、iDeCoには無視できないデメリットも存在します。
これらを理解せずに始めると、後悔することになりかねません。
60歳まで引き出せない
iDeCoの最大のデメリットは流動性のなさです。
原則として60歳までは引き出せません。(※例外要件は極めて限定的です)
そのため、「数ヶ月分の生活防衛資金」や「当面の事業運転資金」とは別に、完全に老後用と割り切れる余剰資金で行う必要があります。
所得控除の上限枠
前述の通り、月額68,000円の上限は「国民年金基金」との合算です。
すでに国民年金基金に加入している場合、iDeCoの枠はその分少なくなります。
- 国民年金基金:給付額があらかじめ決まっている「確定給付型」で終身年金が選べる。
- iDeCo:運用成績によって受取額が変わる「確定拠出型」でインフレに強い。
どちらが良いかは考え方次第ですが、インフレリスクへの対応や、運用コストの低さを重視するなら、iDeCoの比率を高めるのが現代的な選択肢と言えるでしょう。
事務手数料がかかる
iDeCoは、加入時に2,829円、運用期間中は最低でも月額171円(年間2,052円)の手数料がかかります。
ただし、前述した年間数万円〜数十万円の節税メリットを考えれば、月額171円のコストは十分に回収可能です。
重要なのは、これに上乗せされる金融機関独自の「運営管理手数料」が無料の会社を選ぶことです。
究極の選択:iDeCoと小規模企業共済どっちを優先?

個人事業主が退職金を作る制度として、iDeCoと並んで人気なのが「小規模企業共済」です。
「予算に限りがある場合、どちらを優先すべきか?」
これは多くの個人事業主が抱える悩みです。
以下の比較表を参考に検討してみましょう。
| 項目 | iDeCo(個人型確定拠出年金) | 小規模企業共済 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 老後資産の運用・形成 | 経営者の退職金積立・事業資金の貸付 |
| 月額掛金 | 5,000円~68,000円 | 1,000円~70,000円 |
| 節税効果 | 全額所得控除 | 全額所得控除 |
| 運用の成果 | 自己責任(大きく増える可能性あり) | 予定利率による(元本割れリスク低) |
| 流動性 | 60歳まで一切引き出し不可 | 解約手当金として受取可能 ※1 |
| 資金調達 | 不可 | 契約者貸付制度あり(低金利で借入可) |
※1:納付月数が240ヶ月(20年)未満で任意解約すると、掛金総額を下回る(元本割れする)場合があります。
iDeCoと小規模企業共済のどちらを優先すべきかと聞かれた場合、私の結論と理由は次の通りです。
1. まずは「小規模企業共済」から検討する
資金繰りが不安定な個人事業主にとっては、流動性が何より重要です。
小規模企業共済には、積み立てた範囲内で事業資金を低金利・無審査で借り入れできる「契約者貸付制度」があります。
また、廃業時には年齢に関係なく共済金を受け取れるため、事業を畳む際のリスクヘッジとしても優秀です。
参考:中小機構 小規模企業共済とは
2. 余裕があれば「iDeCo」を併用する
小規模企業共済(最大月7万円)とiDeCo(最大月6.8万円)は併用が可能です。
仮にiDeCoと小規模企業共済を満額かければ、年間最大165万6千円もの所得控除を作ることができます。
小規模企業共済で守りを固めつつ、iDeCoでインフレに負けない資産運用をするというのが、個人事業主の資産形成における王道の戦略だと言えます。
個人事業主のお金の受け取り方|出口戦略を考える

iDeCoを始める前に知っておくべきなのが、60歳以降の「受け取り方」です。
受け取り方には、一時金(一括)と年金(分割)があり、どちらを選ぶかで税金が大きく変わります。
ちなみに、個人事業主は「一時金」受け取りが有利なケースが多いです。
iDeCoを「一時金」として一括で受け取る場合、「退職所得控除」という大きな非課税枠が使えます。
会社員は勤務先からの退職金でこの枠を使ってしまいますが、退職金のない個人事業主は、この控除枠が丸々余っています。
- 加入期間20年以下:40万円 × 加入年数
- 加入期間20年超:800万円 + 70万円 ×(加入年数 - 20年)
例えば、30歳から60歳まで30年間iDeCoに加入した場合、
800万円 + 70万円 × (30年 - 20年)= 1,500万円
までは、一括で受け取っても税金がゼロになります。
運用益を含めて1,500万円以内であれば、完全に非課税で老後資金を手元に移せるのです。
この「退職所得控除」をフル活用できる点も、個人事業主がiDeCoをやるべき大きな理由の一つです。
個人事業主がiDeCoを始める際の手順

Step 1. 金融機関を選ぶ
金融機関選びで重視すべきは以下の2点です。
1. 運営管理手数料が「無条件で無料」であること
2. 低コストの「インデックスファンド」が充実していること
SBI証券、楽天証券、マネックス証券などのネット証券であれば、これらの条件を満たしており、間違いがありません。
銀行の窓口で勧められるプランは手数料が高いケースが多いため、慎重に検討しましょう。
Step 2. 運用商品を決定する
個人事業主は、事業そのものがリスクを負っています。
そのため、iDeCoでの運用リスクをどう取るかは、事業の安定度と相談する必要があります。
攻めの運用(株式型):事業が安定しており、老後まで時間がある場合におすすめです。「全世界株式」や「米国株式(S&P500)」などのインデックスファンドを選び、世界経済の成長を取り込みます。
守りの運用(バランス型・元本確保型):事業の浮き沈みが激しく、資産を目減りさせたくない場合に考慮できます。「バランス型ファンド」や、一部を「定期預金」にする選択もあります。(※定期預金はインフレに弱いため注意が必要)
Step 3. 無理のない範囲で掛金を設定する
「節税したいから」といっていきなり上限の68,000円にするのは危険です。
まずは、無理のない掛金から始めましょう。
iDeCoの掛金変更は「年に1回」しかできません。
毎月の資金繰りを圧迫しない金額でスタートし、決算を終えて「もっと余裕がある」と分かったタイミングで増額するのが賢いやり方です。
iDeCoに関連したよくある質問(Q&A)

Q. 途中で掛金を払えなくなったらどうなりますか?
A. 掛金の拠出を「停止」することができます。(※その間も月額66円などの手数料は引かれ続けます)
ただし、積み立てた資産の運用はそのまま継続されます。
事業の状況が悪化した場合は、無理せず停止の手続きを取りましょう。
Q. 法人成りを検討していますが、iDeCoはどうなりますか?
A. 個人事業主から法人成りして役員になった場合、iDeCoの加入資格は第1号(自営業)から第2号(会社役員)に変更となります。
掛金の上限額が月額2.3万円(企業年金がない場合)などに下がる可能性がありますが、iDeCo自体は継続可能です。
手続きが必要になるため、法人化の際は金融機関に相談しましょう。
Q. 確定申告はどうすればいいですか?
A. 毎年10月下旬頃に、国民年金基金連合会から「小規模企業共済等掛金払込証明書」というハガキが届きます。
確定申告書の「小規模企業共済等掛金控除」の欄に、証明書に記載された合計金額を記入し、証明書を添付して提出します。
これを忘れると節税にならないので、絶対に紛失しないようにしましょう。
まとめ
iDeCoは、退職金のない個人事業主にとって、以下の2つの役割を果たす最強のパートナーです。
- 攻め:投資信託による非課税運用で、インフレに負けない資産を増やす。
- 守り:全額所得控除により、毎年の確定申告で税金を確実に減らす。
「60歳まで引き出せない」というデメリットは、裏を返せば「強制的に老後資金を確保できる」というメリットでもあります。
まだ事業の足場が固まっていない方は、資金調達にも使える「小規模企業共済」から始めるのがお勧めですが、ある程度安定した収入があり、所得税・住民税の負担を重く感じている方は、「iDeCo」の併用を強くおすすめします。
まずは月額5,000円の少額からでも構いません。
資料請求をして口座を開設する。この小さな一歩が、数十年後のあなたに「あの時始めておいてよかった」という大きな安心をもたらしてくれるはずです。