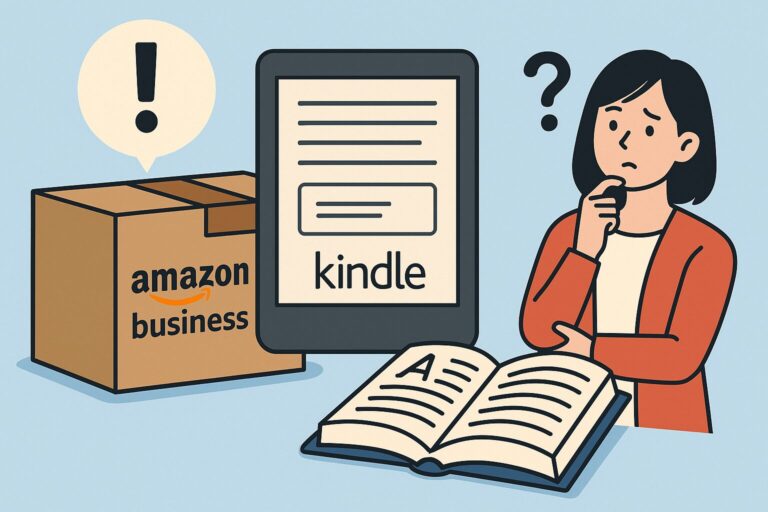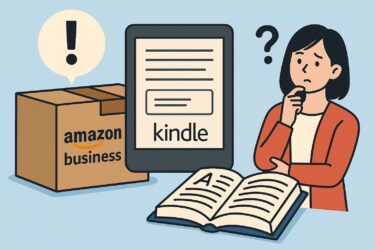個人事業主や小規模企業の経営者として、経費管理を効率化するためにAmazonビジネスの利用を検討されている方も多いと思います。
その中で、「仕事で使う専門書やビジネス書も、AmazonビジネスでKindle版を買って経費にできたら便利なのに」と考えるかも知れません。
この記事では、AmazonビジネスのアカウントでKindleコンテンツを購入しようとした際の注意点や、経費管理の手間を減らしたい個人事業主の方がどう対応すべきか、その具体的な解決策を解説していきます。
本記事のポイント
- AmazonビジネスでKindleコンテンツを購入する際の注意点
- Amazonビジネスと個人向けアカウントの違い
- 経費管理をシンプルにするための現実的な使い分け方法
PR
⚠️ 確定申告、まだ終わってない方へ
「何から手をつければいいか分からない…」という方は、タックスナップの「丸投げ仕分け」を使うと、仕訳作業が一気に進みます。
私の場合は、 667件の取引が約2秒 で仕訳されました。
ただし、使用しているスマホや通信状況などにも左右されるため、まずは無料期間で動作確認してから継続利用を判断するのが安心です。
※自動仕訳後は「勘定科目の最終確認」だけは行うのがおすすめです。
※3/16まで、提出以外の機能は無料で試せます。
AmazonビジネスとKindle本の基本情報と注意点

このセクションでは、AmazonビジネスアカウントでKindle本を購入する際の注意点や、トラブル回避策などを取り上げます。
電子書籍(Kindle)の購入と利用制約
AmazonビジネスでKindle本を経費購入しようとする際、最も注意すべき点があります。
それは、購入すること自体は可能ですが、「アカウントへの紐づき」と「ライブラリの分離」という、利用における非常に大きな制約が存在することです。
Kindleコンテンツは、購入操作を行ったAmazonアカウントのライブラリに保存されます。
たとえ個人事業主の方が「アカウントリンク」機能を使って、個人用アカウントとAmazonビジネスアカウントを連携させて便利に使っていたとしても、両者のKindleライブラリが統合されることはありません。
Kindleの専用端末やスマートフォンのアプリは、基本的に一度に1つのアカウントでしかログインできない仕様になっています。
このため、もしAmazonビジネスアカウントで購入操作を行うと、そのKindle本はビジネスアカウント側のライブラリに保存されます。
一方で、あなたが普段読書に使っているKindle端末が「個人アカウント」でログインしている場合、そのライブラリにはビジネスアカウントで買った本は一切表示されません。
この場合、個人用からビジネス用のアカウントに切り替えることで、購入したkindle本を読むことは可能です。
ですが、その都度、「サインアウト → サインイン」を繰り返すことになり、非常に手間がかかるため、あまり現実的な使い方とは言えません。
Kindle本の法人共有(回し読み)は可能か?
法人やチームで利用する際、「研修用にKindle本を1冊購入し、それを従業員間で共有できればコスト効率が良い」と考えるかもしれません。
しかし、Kindle本の共有は、以下の点から推奨されません。
規約上の制約(ライセンスの問題)
最大の理由は、Kindleストア利用規約にあります。
Amazonの規約では、購入したコンテンツの利用は、基本的に購入者個人に限定されています。
デジタルコンテンツは物理的な書籍とは異なり、購入者が得るのは所有権ではなく利用権です。
そのため、1つのライセンスを複数人で使い回す行為は、規約で想定された利用方法から外れる可能性が非常に高いです。
研修などでの利用はどうすべきか
もし、研修などで従業員複数名に同じ書籍を読ませる必要がある場合、最も規約上も運用上も明瞭な方法は、電子書籍ではなく「紙の書籍」を選択することです。
紙の書籍であれば、Amazonビジネスで必要な冊数を経費購入し、その現物を社内で貸し出すという、通常は問題にならない運用が可能になります。
Kindle本をセールでお得に購入
Kindle本の購入で最もメリットがあるのは、頻繁に行われるセールです。
日替わりセール、月替わりセール、そして大型セールの「Kindle本キャンペーン」など、ビジネス書や専門書も対象になることが多々あります。
あえて管理が複雑になるビジネスアカウントでの購入にこだわるよりも、使い慣れた個人アカウントでセール情報をチェックし、お得なタイミングで購入する方が、結果的にコストメリットも大きくなります。
経費管理という観点からも、Kindle本は個人アカウントで購入し、経費計上するという流れが最もシンプルで、トラブルもないと考えられます。
\kindle本のセール情報を見る/
Amazonビジネスと個人向けとの主な違い

Amazonビジネスは個人向けサービスと何が違うのか、価格やデメリット、そして最も重要な電子書籍の購入がどう扱われるのか、知っておくべき情報を整理して解説します。
主な違い
AmazonビジネスとAmazonの個人向けとの最も大きな違いは、「利用対象者」と「提供される機能」にあります。
個人向けアマゾンが一般消費者を対象にしているのに対し、Amazonビジネスは法人および個人事業主を対象とした購買専用のサービスです。
そのため、ビジネス利用に特化した機能が数多く搭載されています。
例えば、個人向けアカウントでは利用できない「請求書払い」が選択できたり、複数ユーザーでアカウントを管理し、購買承認フローを設定できたりします。
一方で、個人向けAmazonアカウントで利用できるプライム特典の一部、例えばプライムビデオやPrime Musicなどは、Amazonビジネスの有料会員(Businessプライム)では利用できません。
このように、サービス設計の前提が異なっています。
以下の比較表で、主な違いをまとめます。
| 項目 | Amazonビジネス | 個人向けAmazon |
|---|---|---|
| 対象 | 法人・個人事業主 | 一般消費者 |
| 主な機能 | 請求書払い、複数ユーザー管理、法人価格、購買分析 | 通常のショッピング、プライム特典(ビデオ、ミュージック等) |
| アカウント | 事業用の証明書などで審査・登録が必要 | メールアドレスなどで誰でも登録可能 |
どれくらい安くなる?
Amazonビジネスを利用する大きなメリットの一つに、価格設定があります。
ただし、全ての商品が個人向けより安くなるわけではありません。
安くなる主な理由は2つです。
法人価格
一部の商品は「法人価格」として、個人向け価格よりも割安に設定されています。
これはビジネスでの利用頻度が高い商品に適用されることが多いです。
数量割引
同じ商品をまとめて購入する場合に「数量割引」が適用されることがあります。
例えば、「5個以上で5%オフ」「10個以上で10%オフ」といった形で、購入数が増えるほど割引率が大きくなります。
コピー用紙やインクカートリッジ、作業用具といった消耗品を経費でまとめて購入する際には、大きなコスト削減につながる可能性があります。
これらの割引を活用することで、経費支出を抑えることができます。
当サイトでは、Amazonビジネスでどれくらい安く商品を買えるのは、具体的に調査して情報をまとめている記事を掲載していますので、ぜひ参考にしてください。
会社の備品や消耗品を、個人用のAmazonアカウントで立替購入していませんか。 経費精算の手間を感じつつも、「法人用アカウントを作るのは面倒だ」と感じている方も多いかもしれません。 特に気になるのは、「Amazonビジネ[…]
Amazonビジネスのデメリット
多くのメリットがある一方で、Amazonビジネスにはいくつかの注意点や、見方によっては欠点と感じられる部分もあります。
最大の注意点は、個人向けプライム特典との関係です。
前述の通り、Amazonビジネスの有料会員である「Businessプライム」に登録しても、個人向けプライム会員の特典であるPrime VideoやPrime Musicなどのエンタメ系サービスは利用できません。
また、無料のAmazonビジネス会員の場合、Amazonが発送する商品の注文額が合計3,500円未満だと配送料が発生します。(※2024年3月29日改定)
頻繁に少額の注文をする場合は、Businessプライム会員になるか、注文をまとめる工夫が求められます。
ただし、個人事業主やフリーランスの方が、個人向けプライム会員であれば、無料でBusinessプライム会員として登録できるプランがあります。
詳しくは、以下の記事を参考にしてください。
Amazonビジネスに登録しようと考えた際、どうせならお得になる招待コードはないかと探していませんか? しかし、探しても見つからず、登録をためらっているかもしれません。 実は、Amazonビジネスには特定の招待コードがなくても[…]
まとめ
この記事では、AmazonビジネスとKindleの連携に関する疑問について解説してきました。
経費管理を効率化したい個人事業主の方にとって、最も合理的でストレスのない方法は、「モノ」と「デジタルコンテンツ」で購入するアカウントを明確に分けることです。
具体的な使い分けとして、以下の方法をおすすめします。
- Amazonビジネス: Kindle端末本体、紙の書籍、PC周辺機器、オフィス用品など、物理的な「モノ」の購入に特化して使用します。これにより、請求書払いや法人価格、数量割引といったAmazonビジネスのメリットを最大限に享受できます。
- 個人アカウント: Kindle本(電子書籍)やKindle Unlimitedの利用は、すべて個人アカウントで行います。これにより、ライブラリが分散するトラブルを防ぎ、Kindleのセールも活用できます。
経費の計上については、個人アカウントで購入したKindle本の領収書に基づき、会計ソフトや帳簿で仕訳すれば問題ありません。
AmazonビジネスとKindleの特性を理解し、無理に連携させようとせず「使い分ける」ことが、あなたの貴重な時間を節約し、本来の業務に集中するための最善策と言えるでしょう。
🔧 当サイト独自の無料診断ツール(個人情報の登録不要)
- 一般家庭の平均と比較して「高い支出」を1分でチェック。勘定科目も表示!(個人事業主・フリーランス向け)
-
🧾 会計ソフト診断あなたの業種・規模に合う会計ソフトを最短で判定