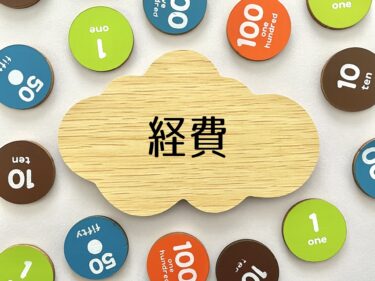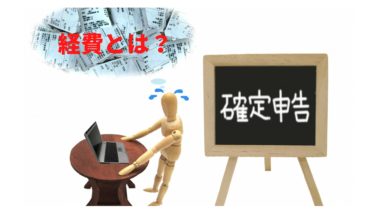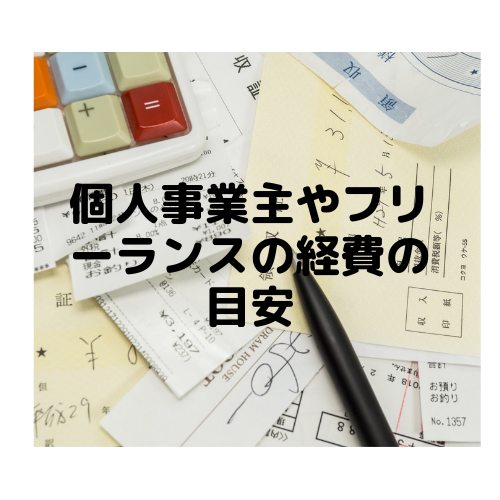必要経費や所得控除をフル活用することで、税金がかからない非課税世帯の個人事業主は少なくありません。
そのため、制度をよく知らない立場から見ると「ずるい」「不公平」と感じられることもあるかもしれません。
しかし、こうした見方は制度の一部だけを切り取ったものであり、実際の個人事業主の生活や負担、そしてリスクは想像以上に大きなものです。
本記事では、「ずるい」と言われる背景や理由をわかりやすく解説します。
また、会社員が個人事業主のメリットを活用する方法についても確認できますので、ぜひ最後までご覧ください。
本記事のポイント
- 個人事業主が非課税になる仕組みと条件
- 「ずるい」と言われる理由とその誤解の背景
- 経費の正しい使い方と税務署のチェック体制
- 会社員との制度上の違いや不公平感の正体
- 副業で個人事業主のメリットを活かす方法
PR
⚠️ 確定申告、まだ終わってない方へ
確定申告がまだ終わっていない方は、まず仕訳を片付けると一気に気持ちがラクになります。特にタックスナップの「丸投げ仕分け」は、迷いがちな仕訳作業を一気に進められる機能です。
私の場合は、 667件の取引が約2秒 で仕訳されました。ただし端末や通信状況などにより、処理の時間は異なる可能性があります。
3/16までは提出・印刷以外を無料で試せます。無料のうちに使ってみて、合うかどうかを確認してみてください。
※仕訳後に、勘定科目や金額は念のため確認しておくと安心です。
※3/16まで、提出以外の機能は無料で試せます。
クーポンは、初回登録時に入力しておくとスムーズです。合わなければ無料期間中に解約できます。
▶ 無料でタックスナップを試してみる(3/16まで) ※「丸投げ仕分け」の詳細や体験談を確認できる記事はこちら個人事業主の非課税が「ずるい」と言われる背景とは

ここでは、個人事業主の非課税が「ずるい」と言われる主な背景や原因について考察します。
原因・理由を考察
「個人事業主はずるい」と感じる人が多いのは、税金や支援制度の仕組みを十分に理解していないことが原因と考えられます。
実際には合法的に行われていることでも、仕組みを知らない立場から見ると「不公平」「ずるい」と誤解されるケースが少なくありません。
まず最も多く聞かれるのが「非課税世帯なのに生活が豊かに見える」という声です。
たとえば、保育料や医療費がほぼ無料だったり、就学援助など各種支援を受けられることで、結果的に生活に余裕が出ているように映るようです。
しかし、これは制度上の条件を満たしている結果であり、ルールに従って申請しているだけに過ぎません。
一方で、個人事業主は自分で帳簿をつけ、毎年確定申告をしなければなりません。
しかも収入が安定していないため、支援がなければ生活が立ち行かなくなることもあります。
支援制度はそのリスクに対するセーフティネットのようなものであり、決してズルをして得ているわけではありません。
つまり、「ずるい」と感じるのは制度の一部だけを見た誤解が多く、実際にはそれなりのリスクや手間、責任を負っているのが個人事業主の実情です。
経費の使い方
個人事業主が「ずるい」と言われる理由のひとつに、経費の使い方があります。
特に会社員と比較されたときに、「そんなものまで経費になるの?」と不公平感を覚える人がいるようです。
経費として認められる範囲は広く、業務に関係していればかなり柔軟に計上できます。
たとえば、打ち合わせを兼ねた外食費や、資料作成のために購入した書籍、さらには自宅の一部をオフィスとして使っている場合の家賃や光熱費も対象になります。
こうした支出を見たときに、会社員の立場からすると「それが税金から控除されるのはずるい」と感じてしまうのも無理はありません。
なぜなら、会社員の場合は給与から源泉徴収された後の「手取り」で生活しているからです。
一方で、個人事業主は経費を差し引いた「利益」に対して課税されるため、支出のコントロール次第で課税額を抑えることが可能です。
しかし、だからといって何でも経費にして良いわけではありません。以下のようなケースでは、実際に「やりすぎ」と見なされるリスクがあります。
- 家族旅行を出張として計上する
- 趣味で購入したガジェットを業務用と偽る
- 実際には使っていないサブスクを経費処理する
このような行為は、本来の経費の趣旨を逸脱しており、税務調査の際に否認される可能性が高くなります。
最悪の場合、追徴課税や罰金が科されることもあるため、慎重な判断が求められます。
経費を正しく使えば、事業を円滑に進めるための大きな助けとなります。
大切なのは「ずるい」と思われないように、透明性を持って適切に処理することです。
帳簿や領収書の管理を徹底し、必要であれば税理士に相談することもひとつの方法です。
「個人事業主が経費計上して節税するのはずるいのか?」というテーマは、議論を呼びがちです。 今回は、「ずるい」と言われる理由や、不正確な申告のリスク、個人事業主の経費に関する基本的な知識について取り上げています。 […]
会社員との違いと不公平感
会社員と個人事業主の間には、働き方・所得の仕組み・税金の取り扱いに明確な違いがあります。
その違いを知らないまま比較すると「会社員だけが損している」といった不公平感を覚えやすくなります。
以下に、主な違いをまとめた表を見てみましょう。
| 項目 | 会社員 | 個人事業主 |
|---|---|---|
| 所得の安定性 | 安定(月給制) | 不安定(売上次第) |
| 所得の計算方法 | 給与-所得控除 | 売上-必要経費-各種控除 |
| 経費の計上 | 不可 | 可(仕事に関連すればOK) |
| 確定申告 | 不要(年末調整) | 必要 |
| 社会保険 | 会社が半分負担 | 全額自己負担 |
| 各種支援制度 | 所得が高くなり対象外になりやすい | 所得を抑えれば対象になることも多い |
この表からわかるように、個人事業主は自由度が高い反面、収入の波が大きく、保険料も全額自己負担となるなどリスクを抱えています。
一方、会社員は安定収入があり、税務処理も簡単ですが、その分制度上の支援を受けにくい仕組みとなっています。
不公平に感じる場面としてよくあるのが、保育料や医療費の自己負担額です。
同じような生活をしていても、収入の見かけ上が低く抑えられている個人事業主は支援を受けられる一方、会社員は支払額が高くなることがあります。
これは課税所得の算出方法が異なることが理由です。
つまり、制度を知れば「仕組みの違い」が原因であることが見えてきます。
重要なのは、「不公平」と感じるのではなく、どうすれば自分にとっても最適な制度を利用できるかを知ることです。
会社員でも副業などで個人事業主の要素を取り入れることで、制度の恩恵を受ける道もあります。
次のステップを考えることが、納得のいく働き方につながるでしょう。
会社員が個人事業主のメリットを利用する方法
会社員であっても、副業として個人事業を持つことで「個人事業主のメリット」を活用することが可能です。
これは節税対策として非常に有効であり、近年では副業解禁の流れとともに注目されています。
そうなると以下のようなメリットが得られます。
- 経費として認められる支出が増える
- 青色申告による65万円控除の適用が可能
- 赤字を本業の所得と相殺できる(損益通算)
以下は、会社員と個人事業主(副業)を併用した場合の主な違いとメリットです。
| 項目 | 会社員のみ | 会社員+副業(個人事業) |
|---|---|---|
| 経費の計上 | 制限あり | 事業に関連すれば可能 |
| 青色申告特別控除 | なし | 最大65万円の控除が可能 |
| 確定申告の必要性 | 年末調整で完結 | 所得が20万円超で申告が必要 |
| 節税の柔軟性 | 低い | 控除や経費で調整しやすい |
ただし、いくつか注意点も存在します。
- 勤務先の就業規則で副業が禁止されていないか確認する
- 経費の計上は「業務に必要な支出」のみ
- 副業の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要
開業届と同時に「青色申告承認申請書」を提出することで、翌年からの青色申告が可能となり、節税効果がより高まります。
このように、会社員であっても副業を通じて個人事業主の恩恵を受けることができます。
収入の柱を増やしながら、上手に税金対策を進めたい方にはおすすめの方法です。
個人事業主として事業収入がある場合、経費に関する知識を学んでおくことは重要です。 経費に関する理解を深めれば、税金の金額を抑えることができ節税に繋がるからです。 今回の[…]
非課税世帯のメリット・デメリットを解説

非課税世帯とは、一定の所得基準を下回ることにより、住民税が課されない世帯のことを指します。
主に低所得者や生活困窮者を対象とした制度であり、国や自治体からのさまざまな支援を受けやすくなっています。
まず、非課税世帯として認定されるためには、所得や家族構成に応じた要件を満たす必要があります。
例えば、単身世帯で扶養家族がいない場合、年収がおおよそ100万円以下であれば非課税となる可能性があります。扶養者がいる場合はその分の控除が加味され、基準額は変動します。
この制度の最大の目的は、「最低限の生活保障」です。
非課税世帯には以下のような多くの支援が用意されています。
- 国民健康保険料や介護保険料の減免
- 保育料の軽減や完全無償化
- 高校授業料の無償化・就学援助制度の対象
- 医療費の自己負担軽減(自治体により異なる)
- 公共料金や税金の減免措置
- 給付金・助成金の対象になりやすい
これらの支援があることで、収入が少ない世帯でも医療や教育など、生活に必要不可欠な支出を抑えることができます。
特に、ひとり親世帯や高齢者のいる家庭では、こうした支援が生活の安定を支える重要な要素となります。
また、2021年には「住民税非課税世帯等臨時特別給付金」など、特別な支援策が国から打ち出されました。このような制度も、非課税世帯が優先して対象となる傾向があります。
一方で、非課税であることが「得している」と誤解されることもありますが、実情はそう単純ではありません。
非課税であることには以下のようなデメリットも存在します。
- 生活に余裕がない
- 住宅ローンやクレジットカードの審査で不利になる
- 納付が免除・猶予されても、将来の年金額が減るリスクがある
このように、非課税であることには多くの支援がある反面、それは「経済的に困難な状態」を示しているという側面もあります。
支援を受けられること自体は必要な制度ですが、長期的な視点で見ると、一定の収入を確保し、税金を納めることで得られる社会的信用や生活の安定性のほうが重要だと考える人も少なくありません。
したがって、非課税世帯の支援を正しく理解し、自分や家族の状況に応じて利用できる制度を活用しながら、将来的には自立した生活を目指す視点を持つことが大切です。
個人事業主の非課税に関連したリスクと注意点
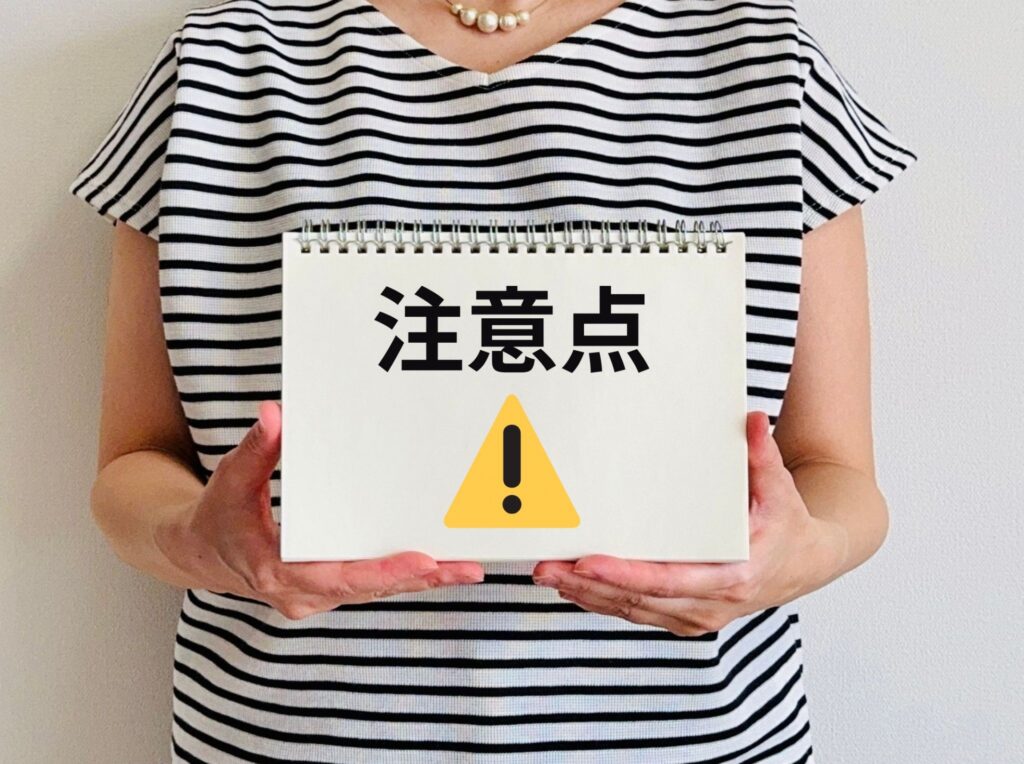
「これはバレないだろう」と軽い気持ちで経費を計上してしまう方がいますが、税務署は決して甘くありません。
とくに個人事業主やフリーランスの申告には、非常に厳しい目が向けられています。
「正しく申告していないといずれバレる」という前提で考えることが、自分の身を守るうえでも重要です。
税務署は、確定申告の内容をもとに様々な視点からリスク判定を行っています。たとえば以下のようなケースは、特に目をつけられやすいとされています。
- 毎年赤字申告が続いている
- 売上に対して経費の割合が極端に高い
- 経費の内容に一貫性がない、領収書が不自然
- 他の同業者と比較して経費が明らかに多い
- 高収入にもかかわらず納税額が極端に少ない
こうした申告は、「意図的に税金を逃れているのでは?」という疑いを持たれる原因になります。
実際、税務署は以下のような手段で申告内容の妥当性をチェックしています。
- 過去の申告データと照合
- 業種ごとの平均的な数値との比較
- AIやデータ分析システムを用いた自動抽出
つまり、以前のように「勘」や「抜き打ち調査」ではなく、論理的かつ統計的に「怪しい申告」を絞り込む体制が整えられているのです。
たとえば、以下のような経費の使い方は特に注意が必要です。
| 経費計上例 | 問題点 |
|---|---|
| 家族との外食を「会食費」にする | 業務との関連性が曖昧でプライベートと見なされやすい |
| 趣味で購入したカメラやPC周辺機器 | 仕事と関係が不明確だと経費否認の対象になる |
| 旅行費を「出張費」として処理 | 宿泊先や目的地の内容次第では私的利用と判断される |
こうした経費は、内容や頻度、支出先の詳細によっては「私的支出の偽装」と判断され、調査対象となる可能性が高まります。
さらに、調査によって不正が発覚した場合には、追加課税に加え、延滞税や重加算税が課されることもあります。
結果的に多くのペナルティを背負うことになり、「節税」のつもりが「損失」になりかねません。
このようなリスクを避けるには、「これは本当に業務に必要な支出か?」を常に意識し、経費の根拠を明確にしておくことが欠かせません。
領収書やレシートだけでなく、日々の帳簿や業務記録もしっかりと残しておくことが、いざというときの信頼につながります。
個人事業主の非課税に関連したよくある質問

自営業で収入をごまかしたらどうなる?
自営業者が収入をごまかす行為、つまり「申告漏れ」や「所得隠し」は、重大なリスクを伴います。
表面上はバレないと思っていても、税務署には高度なチェック体制が整っており、過去の申告内容や業界水準との比較から不正を見つける仕組みがあります。
まず、収入をごまかした場合に考えられる主なペナルティは以下の通りです。
- 過少申告加算税
- 重加算税
- 延滞税
特に、故意に売上を抜いたり、架空の経費を計上して所得を減らす行為は、重加算税の対象になりやすく、税務署は非常に厳しく対処します。さらに悪質と判断されれば、刑事告発される可能性もゼロではありません。
また、税務調査では、以下のような点がチェックされます。
- 売上帳と預金口座の入金額の差
- クレジットカードの使用履歴
- 仕入れ先との取引履歴の整合性
- 現金商売での管理体制
こうした情報をもとに、実際の収入とかけ離れていると判断されると調査が入り、調査後には大きな金銭的ダメージを受けることになります。
一見「少しくらいバレないだろう」と思えるかもしれませんが、長期的に見ればリスクの方が圧倒的に大きいです。
正しく申告し、帳簿をしっかりつけることが、自分を守る最大の防御になります。
非課税が恥ずかしいと感じる人の心理とは
非課税であることに対して、「なんだか恥ずかしい」と感じる人は少なくありません。
その背景には、日本人特有の“人に迷惑をかけない”という価値観や、“税金を納めるのが当然”という社会的意識が深く根付いています。
たとえば、周囲に「税金を払っていない」「社会の支援を受けている」と知られると、「ずるいと思われるのでは?」と不安に感じるケースがあります。
また、扶養控除や給付金などの手続きで、自分の非課税状態を明示しなければならない場面があると、余計にその感情が強まることもあります。
ただし、非課税であることは制度に則った結果であり、何も悪いことをしているわけではありません。
収入状況に応じて支援を受けるのは、社会保障制度の本来の役割です。むしろ、必要な支援を受けずに生活が苦しくなるほうが問題とも言えます。
非課税であることを「後ろめたく思う」よりも、「今の状況を立て直すチャンス」と前向きに捉えることが大切です。
特に個人事業主であれば、今後の事業展開次第で大きく収入が変わる可能性もあります。
現状を正しく理解し、自分に必要な支援をしっかり受けることが、次の一歩につながるはずです。
ぶっちゃけ経費でなんでも落とせる?知恵袋でよくある誤解
「経費」と聞くと、「何でも落とせる」と思ってしまう人も多いようです。
特にインターネット上のQ&Aサイトや知恵袋では、事実とは異なる内容が散見され、誤解を生む原因となっています。
ここでは、よくある誤解とその正しい理解について解説します。
まず、よくある誤解のひとつに「生活費も経費にできるのでは?」という考えがあります。
実際には、仕事に関係のない支出は経費に含めることができません。たとえば、自宅の家賃全額や食費全体を経費にするのは原則NGです。
仕事と私生活を明確に区分することが必要であり、プライベートとの混同は税務署から指摘されるリスクがあります。
また、「レシートさえあれば何でも経費になる」という認識も誤りです。
領収書があっても、それが業務に関係していなければ経費とは認められません。
経費として計上するには、業務との関連性を説明できるように記録を残しておくことが大切です。
一方で、正しく活用すれば、経費は節税に大きく貢献してくれる制度でもあります。
以下に、よくある誤解と正しい内容を整理しておきます。
| よくある誤解 | 実際のルール |
|---|---|
| 家賃や食費はすべて経費にできる | 仕事で使う割合に応じて按分しなければならない |
| レシートがあればOK | 業務関連性を説明できなければ経費にできない |
| 家族への支出も経費で落とせる | 家族従業員でない限り、基本的には認められない |
| 経費が多ければ多いほど得をする | 赤字が続くと税務署から疑われる可能性がある |
このように、ネット上の情報を鵜呑みにするのではなく、正確な知識を身につけることが、個人事業主にとっては非常に重要です。
個人事業主で非課税になる年収はいくらですか?
個人事業主が非課税になる年収には、いくつかの基準があります。
ここでいう「非課税」とは、主に所得税や住民税が課されない水準を指します。ただし、事業の経費や家族構成などによって大きく異なるため、一律で「〇〇万円以下」とは言い切れないのが現実です。
目安として、単身者の場合、年間の所得が48万円以下であれば、所得税は非課税となります。これは「基礎控除」が48万円であるためです。
※令和7年分からは58万円に引き上げ予定です。
参考:国税庁 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
住民税については、43万円の「基礎控除」に加えて、「非課税限度額」と呼ばれる基準があります。
これは、給与所得控除後の所得がこの限度額を下回る場合、住民税が課されない仕組みです。限度額の金額は自治体によって異なりますが、基本的には45万円とされているケースが多く見られます。
詳細は各自治体により異なりますが、概ねこのような条件を満たすと非課税扱いとなります。
さらに、扶養家族がいる場合や、障害者控除、医療費控除などを適用すれば、非課税になる年収の上限はさらに上がります。
売上より経費が多いときの注意点
売上より経費が多くなる状況は、個人事業主にとって珍しいことではありません。
特に開業初年度や設備投資を行った年などは、赤字になってしまうケースもあるでしょう。ただし、このような状態が続くと税務上の注意が必要になります。
まず結論から言うと、「毎年赤字=経営が成り立っていない」と判断される可能性があるため、以下のような点には注意が必要です。
- 継続的な赤字は調査対象になりやすい
- 赤字でも確定申告は必須
- プライベートと事業の支出を明確に区別する必要がある
特に、赤字申告が数年続く場合、「実態のない事業」と見なされるリスクがあり、税務署から調査を受ける可能性が高まります。
たとえば、生活費を「経費」として計上していたり、明らかに事業と関係のない出費が含まれていると、不正申告と判断されるおそれもあります。
経費と認められるためには、「事業に必要な支出であること」が前提となります。
そのため、以下の点をチェックしておきましょう。
| チェックポイント | 内容 |
|---|---|
| 領収書の保存 | 支出ごとに日付・内容を記録 |
| 使用目的の明確化 | プライベートと事業の兼用はNG |
| 経費分類の見直し | 本当に必要な経費かを精査 |
また、赤字だからといって税務申告をしないのは間違いです。
むしろ、赤字申告によって翌年以降の利益と相殺できる「青色申告の繰越控除」を利用することで、将来の節税にもつながります。
売上より経費が多い時こそ、帳簿の記録と経費の根拠づけを丁寧に行い、透明性のある経営を意識することが大切です。
個人事業主やフリーランスの方が、事業を行う上で経費計上できる金額が多ければ節税効果が大きくなります。 ただし、経費については曖昧な部分があり、何が経費として認められるのかは業種などによっても異な[…]
まとめ
個人事業主が非課税になることを「ずるい」と感じる背景には、制度への理解不足や会社員との待遇の違いがあります。
しかし、非課税や経費計上などの仕組みは法律に基づいたものであり、適切に申告・管理していれば決して違反ではありません。
むしろ個人事業主は、収入の不安定さや自己負担の多さといったリスクを背負っているのが現実です。
また、制度の違いを正しく知ることで、会社員でも副業を通じてメリットを得ることが可能です。
経費の扱い方や非課税の条件をしっかりと理解し、「ずるい」と感じる前に制度を味方につける視点が大切です。
本記事を通じて、誤解を解消し、自分に合った働き方や税対策のヒントを得ていただければ幸いです。